「さて、七十人が喜んで帰って来て、こう言った。『主よ。あなたの御名を使うと、悪霊どもでさえ、私たちに服従します。』」(ルカ 10:17)
「霊の戦い」と聞くと、カルト化した教会で被害を被った人たちにとっては、それだけで拒否反応が起こるほどに、カルト化しやすい分野である。
それは、「霊の戦い」を強調する、悪い霊に打ち勝てる自分を誇示する人たちの結ぶ実によるものである。
聖書には、始まりの創世記からサタンが出現し、そこから完成のクライマックスの黙示録に至るまで、霊(信仰)の戦いが描かれている。
キリストも使徒たちも、病に命じ、異なる霊に叱りつけ立ち去らせている。「サタンよ、出ていけ!」「病よ、いやされよ!」「嵐よ、静まれ!」と命じることは聖書に書かれている行動である(マタイ4:10, マルコ1:25, 3:15, 5:8, 6:7, ルカ4:35, 8:29, 使徒16:18など)(マタイ 8:3, マルコ 9:25, ルカ 5:13)(ルカ 8:24-25)。
「信じる人々には次のようなしるしが伴います。すなわち、わたしの名によって悪霊を追い出し、新しいことばを語り、 蛇をもつかみ、たとい毒を飲んでも決して害を受けず、また、病人に手を置けば病人はいやされます。」(マルコ 16:17,18)ともある。
では、どうしてキリスト教界内でもそれぞれの意見が異なる問題となっているのか。
それには、次のようなことが考えられる。
- 神と神に敵対する霊の存在を信じない不信者にとっては、奇異に見える行為である。
- 目に見えないことなので、本当にことばで命じたことによるものなのかという証明ができない(たとえ、そのとおりのことが起こったとしてもいろいろな理由付けで否定できる信仰の世界の出来事である)。
ex. 偶然だろう、思い込みだろう、人によるトリックだ・・・等 - 命じている人たちのふるまい方
ex. 自分がなした功績のようにふるまう、言動がキリストと同等になったかのように自分に権威付けしてしまう、他のクリスチャンとの差別化が見られる・・・等 - 必要を見分けることなく、何でもかんでも命じてしまう。「あなたの神、主の名を、みだりに唱えてはならない。」(出エジプト20:7)(しっかりとした聖書全体からの教育がなされずに実践している。)
ex. 病人には誰にでも、また自分に対して否定的な意見や都合の悪い意見は悪霊の仕業にしてしまう・・・等 - キリストなる神よりも悪霊、サタンに目が行ってしまうことになる。
いろいろ危ないからやめてしまうというのも、聖書的解決ではない。
——————
人をつまずかせないよう注意を払い、心の高慢に陥らないよう、キリストを見上げて、信仰の戦いをしていこう。神から出たか他から出た行為かは、誰の目にもはっきりとわかる時が来る。神を恐れつつ、神が導きによって隣人に仕えていこう。
自分の考えで非難することはいろいろな危険を伴う:
「わたしの天の父がお植えにならなかった木は、みな根こそぎにされます。彼らのことは放っておきなさい。」(マタイ 15:13,14)
「ヨハネがイエスに言った。『先生。先生の名を唱えて悪霊を追い出している者を見ましたが、私たちの仲間ではないので、やめさせました。』しかし、イエスは言われた。『やめさせることはありません。わたしの名を唱えて、力あるわざを行ないながら、すぐあとで、わたしを悪く言える者はないのです。わたしたちに反対しない者は、わたしたちの味方です。あなたがたがキリストの弟子だからというので、あなたがたに水一杯でも飲ませてくれる人は、決して報いを失うことはありません。これは確かなことです。また、わたしを信じるこの小さい者たちのひとりにでもつまずきを与えるような者は、むしろ大きい石臼を首にゆわえつけられて、海に投げ込まれたほうがましです。・・・」(マルコ 9:38-42)
—————-
【編集後記】癒しの出来事:
受洗した教会にてハラスメントを受けたにもかかわらず、ハラスメントに対する理解が及ばなかった頃だったので、それでも和解を試みようと牧師に手紙を出したことがあった。気を配り、失礼な部分がないかという確認のために、何人かの方々に目を通してもらって渡したものであった。その結果、出した手紙はと言えば、「僕は、読まなかったよ。妻に読むように渡したら、読む前に、『この手紙には悪霊がついてますから、追い出します。』と言って追い出していたよ。そんな手紙を読む必要もない。」と言われ、読んでもらえなかったことがわかった。牧師夫人にそのことを尋ねると、「私には、悪霊を叱りつける賜物があるから、わかったんです。」とのことだった。「手紙に、悪霊がついていたのなら、本人には、もっとすごいものがついているでしょう。追い出してください。」と言うと、「もういません。私が追い出しましたから。」と答えられ、ものすごく納得がいかない思いが残った。(「『小羊うるちゃん物語』part 5-4 和解への試み」参照)
この牧師については、この働きを初めて何年かした後に、ある記事を通して理解と癒しを深めることができた。
ある記事とは、キリスト教系のペンテコステ系の雑誌1に3か月にわたって連載された16ページにわたる対談記事なのだが、そこに牧師自身が語った言葉として記されていた。会社員として働いて、素敵な女性と婚約をしていた彼は、とある宣教師の介入により、婚約者との関係を断ち切り、牧師となった。マンツーマンでその宣教師から教えを受け(ちなみに宣教師のルーツは、調べても、ある海外のペンテコステ教会から来たこと以外はいまだ不明である)牧師の道を歩み出し、婚約者には、宣教師のアドバイスに従って、一通の手紙を出して、縁を切ったそうであった。一生懸命書いた手紙だったそうだが、突然のことに婚約者からは、当然のこと、手紙が送られてきた。結婚を夢見ていただろう、あきらめられない彼女は、手紙を出し続けたが、積み上がっていく手紙を「自分にはこれは切れない」と1通も封を切らなかったという。遂に手紙が来なくなって、終わることができたと指導者に従順に従ったことが証しとして語られていた。「優秀な人は神学校へ行かなくてもよい、神学校に行くのは行かざるを得ないから、優秀じゃないから」と対談者の牧師は、マンツーマンでその宣教師から教えを受けたことをほめていた。婚約者の女性の心の傷が気になるところである。キリスト教が大嫌いになっているのではないだろうか・・・。彼女が真理を知って癒されていますように。
きちんとした学術的な神学校は、聖書の背景や大切な事柄を学ぶために、必要な機関である。完全な人間はいず、いろいろな教師から学ぶことによって、吸収できる学びがある。また、専門的な知識を深めている教師たちがいる。不完全な人間だけから学ぶと、支配下に置かれ、その不完全な教えがあたりまえのように受け継がれていく。大きな問題が起こるまで、偏った教理が真理だと疑いもしないかもしれない。弟子は師に似るため、聖書を教わる師は「神であられるキリスト」とし、出会う人々から学んでいく必要がある。
信仰に入りたての時期や、心が弱っている時には、強そうに見える人に頼ってしまいがちになり、支配に気付かずに、年月が経っていく。ずっと気づかないかもしれない。本人が幸せで、キリストにつまずくことが起こらなければ、それはそれでよいかもしれない。受けた教えは、その実を見て、時には疑うことも大切である。主の前に静まり、聖書から教えていただこう。
- 資料:ハーザー(マルコーシュ・パブリケーション) ↩︎

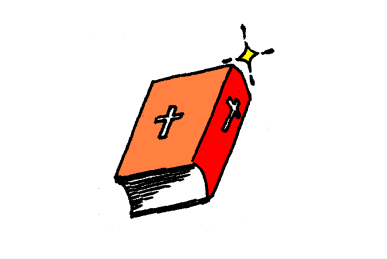


コメント