<– 前の記事:『かもしかや野の雌鹿をさして-干渉の禁止―』
前記事では、無気力になった花嫁が、花婿に、干しぶどうの菓子による力づけとりんごによる元気づけを懇願し、エルサレムの娘たちに、干渉しないことを誓わせたところまでを見た。この後、
 (段落記号、段落を表わす)が入っている。上に愛という花婿の旗じるしを翻し、子やぎを飼う花嫁が、愛に病んで、時が経っていったようである。
(段落記号、段落を表わす)が入っている。上に愛という花婿の旗じるしを翻し、子やぎを飼う花嫁が、愛に病んで、時が経っていったようである。
—————–
聖書個所:雅歌 2:8-3:5(新改訳聖書)
『狐や小狐の退治-自我の解放―』
愛のすれ違い
花嫁の懇願に、花婿は、左の腕を枕にし、右の手で抱きしめようと、駆けつける。「愛する方の声。ご覧、あの方が来られます。山々をとび越え、丘々の上をはねて。」(雅歌 2:8)みことばなるキリストは、みことばを携え、さっそうとすみやかに来られる。花嫁を助けようと・・・。
「私の愛する方は、かもしかや若い鹿のようです。ご覧、あの方は私たちの壁のうしろにじっと立ち、窓からのぞき、格子越しにうかがっています。」(雅歌 2:9)駆けつける姿は、さっそうと雄々しく、まさしくかもしかや若い鹿(
 「雄の子鹿」)のようである。さっそうと駆けつけた花婿は、花嫁のもとに行ったのだが、近寄ることができなかった。壁があったのだ。私たちの壁と花嫁は言っているが、この壁は共同で作ったものではなく、花婿が作って行ったものでもなく、もとからあった土台に花嫁が自分で作り上げたものであった。しかも、これは、窓を開けて入れるようなものではなく、窓にはしっかりと格子がはめ込まれているような頑固なものであった。花嫁は心に頑固な壁を持ち、花婿を遮断していた。しかし、覗いてもらえるような窓はしっかりと作っているのである。いつの間に、このような壁が・・・、花婿は、壁の後ろにじっと立って、窓から格子越しに中を伺った。「私たちの長いいすは青々としています。」(雅歌 1:16)と言って、花婿のかたわらの緑の牧場を理解した花嫁であっても、彼女の意志でできた自我の壁が花婿との間をはばんでいた。壁を作ってしまった花嫁に、花婿は語りかける。壁を壊すことは、花嫁でなければできないのである。壁を壊せるのは、花嫁が自分の思いやプライドを捨てる決意をし、どんな危機の困難の中であっても、花婿を信頼し、心の奥底の主導権を花婿にゆだね渡すことによる。
「雄の子鹿」)のようである。さっそうと駆けつけた花婿は、花嫁のもとに行ったのだが、近寄ることができなかった。壁があったのだ。私たちの壁と花嫁は言っているが、この壁は共同で作ったものではなく、花婿が作って行ったものでもなく、もとからあった土台に花嫁が自分で作り上げたものであった。しかも、これは、窓を開けて入れるようなものではなく、窓にはしっかりと格子がはめ込まれているような頑固なものであった。花嫁は心に頑固な壁を持ち、花婿を遮断していた。しかし、覗いてもらえるような窓はしっかりと作っているのである。いつの間に、このような壁が・・・、花婿は、壁の後ろにじっと立って、窓から格子越しに中を伺った。「私たちの長いいすは青々としています。」(雅歌 1:16)と言って、花婿のかたわらの緑の牧場を理解した花嫁であっても、彼女の意志でできた自我の壁が花婿との間をはばんでいた。壁を作ってしまった花嫁に、花婿は語りかける。壁を壊すことは、花嫁でなければできないのである。壁を壊せるのは、花嫁が自分の思いやプライドを捨てる決意をし、どんな危機の困難の中であっても、花婿を信頼し、心の奥底の主導権を花婿にゆだね渡すことによる。
「私の愛する方は、私に語りかけて言われます。『わが愛する者、美しいひとよ。さあ、立って、出ておいで。』」(雅歌 2:10)「さあ、そこで、防御の殻を作ってないで、殻から出ておいで。」と。「ほら、冬は過ぎ去り、大雨も通り過ぎて行った。」(雅歌 2:11)「冷たく厳しい冬は過ぎたよ、あなたを容赦なく打った大雨も過ぎて行ったよ」と。「地には花が咲き乱れ、歌の季節がやって来た。山鳩の声が、私たちの国に聞こえる。」(雅歌 2:12)十字架にかかる体験、裸(自我が露わ)にされる聖別の体験はもはや終わり、暖かい春がやってきた。地は花が咲き乱れ、美しくよいにおいで満ちている。鳥のさえずる歌声もまるで喜びの賛美のようだ。鳩は平和の象徴。中でも山鳩の特徴は、生涯に一度だけ結婚し、その配偶者に忠誠を尽くす一夫一妻制であるため、愛の象徴としてよく用いられている。平和な愛の風景である。花婿の語りかけは続く。「いちじくの木は実をならせ、ぶどうの木は、花をつけてかおりを放つ。わが愛する者、美しいひとよ。さあ、立って、出ておいで。」(雅歌 2:13)春、花のない無花果(実は、花がないわけではなく、実の中にたくさんの花を蔵している)は、青い実をつける。ぶどうの木は、花をつけ、よいかおりを放つ。来るべき大収穫のための花である。「愛する美しい人よ、恐れないで、立ち上がって出ておいで。大収穫が来るよ。」と花婿は呼びかける。この後、
 (段落記号、段落を表わす)が入っている。「出ておいで。」と呼びかけたが、花嫁の応答はなかったようである。
(段落記号、段落を表わす)が入っている。「出ておいで。」と呼びかけたが、花嫁の応答はなかったようである。
さらに、花婿は呼びかける。「岩の裂け目、がけの隠れ場にいる私の鳩よ。私に、顔を見せておくれ。あなたの声を聞かせておくれ。あなたの声は愛らしく、あなたの顔は美しい。」(雅歌 2:14)「岩の裂け目、がけの隠れ場にいる私の鳩」花嫁の目を鳩のようだと言った(雅歌 1:15)花婿は、ここでも花嫁を素直で温順な鳩に例えている。しかも岩の裂け目、がけの隠れ場にいる鳩である。
以前、集合住宅の9階に住んでいた時のある台風の夜、一羽の鳩が、我が家のベランダに非難してきた。暗い中、鳥目で見えないためか、暴風雨の中、飛び立ったら危険な状態を知っている鳩は、ひとつ場所にじっとしていた。鳩がベランダに住みつくと子作りをしてうるさく、糞害も大変であると聞いていたし、実際に卵を産まれたこともあるため、空き部屋であった隣にでも行ってとばかりに、そばにあったハンガーでつんつんしてみた。つんつんされた鳩は怖かったであろうに、じっとしていた。ハンガーがふれても知らん顔を決め込むように、こちらを見もせず、無視してじっとしていた。人間につんつんされて、怖くないわけではなかったろうに・・・。その姿を見て、いのちがけであることを知り、そのままにしておいた。少しして、少し小柄な鳩も来て、寄せ合うように一夜を過ごし、早朝に飛び立って行ったのか、起きてみると鳩の姿はなかった。ここなら安心とわかっているのか、突付く者があっても目に入れず、嵐が過ぎ去るまで、じっと嵐を見据え、微動だにしなかった鳩、恐れて飛び立ったなら、容赦ない嵐に倒れたかもしれない。「岩の裂け目、がけの隠れ場にいる鳩」とは、まさしくそのような状況である。嵐の中も、必ず嵐は過ぎ去るという信仰をもって、突付く者があっても、主の守りを信じ、見向きもせず、主の守りの中で耐えている花嫁。そのような花嫁に向かって、「危険なところにいたために、頑固な壁を作っているが、私はあなたが鳩のように素直であることを知っているよ。嵐は過ぎ去った。さあ、私に、顔を見せておくれ。」と花嫁は言う。花婿が花嫁の声を聞くことを望んでいるように、主も私たちの祈りの声を望んでおられる。「あなたの声は愛らしく、あなたの顔は美しい。」と言った花婿のように、私たちが祈る姿は、主の御前にとても愛らしく、美しく見えている。この後、
 (段落記号、段落を表わす)が入っている。「声を聞かせておくれ。」と言われても、すぐに喜んで応答できないほどに病んでいる花嫁。
(段落記号、段落を表わす)が入っている。「声を聞かせておくれ。」と言われても、すぐに喜んで応答できないほどに病んでいる花嫁。
「『私たちのために、ぶどう畑を荒らす狐や小狐を捕えておくれ。』私たちのぶどう畑は花盛りだから。」(雅歌 2:15)「私たちのために、ぶどう畑を荒らす狐や小狐を捕らえておくれ。」は、今まで花嫁が花婿に言っていたことばなのである。「そのままにしておいたのは、無視していたわけではない。しっかり聞いていたのだ」ということを伝える花婿。イエスさまはヘロデ・アンテパスを「あの狐」(ルカ 13:32)と言ったように、狐は、キタキツネなどを連想すると、かわいいところもあるが、決してよい動物とは言えない。イソップ物語など、童話に登場する狐は、その性質をよく語っている。狐は、単独で行動し、昼間は、他の動物から奪った穴で休み、夜、行動するという。また荒れ果てた廃墟を好む。雑食性で、ねずみ、うさぎ、きじ、かえるなどの小動物や、果実、特にぶどうを好んで食べる。性質は陰険でずる賢い。花嫁は、このような狐に、悩まされ、翻弄され、またせっかくなった少しのぶどうの実を荒らされた経験もあって、花婿に訴えていたことがあったのである。「私たちのために、ぶどう畑を荒らす狐や小狐を捕えておくれ。」花嫁の切なる訴えであった。花嫁は「花婿のためでもあるのだから、このいらだたせる狐を退治してくれてもよいではないか。」と言っていたのである。しかし、狐や小狐をとらえることは、花嫁にできる仕事なのである。花婿は、花嫁が成長するのをそっと見守り、待っていたのである。花嫁の目には、放置されているように見えたのだが…。狼や獅子を捕らえるのとは違うのである。しっしっと追い払えばよいのである。畑に入れなければよいのである。入ることを許さなければよいのである。その力を花嫁はすでに花婿によって与えられているのである。今、大収穫を予見するように、ぶどう畑は花盛りなのである。10節からのかぎ括弧は、壁の窓の格子越しの花婿のことばである。これまでの花婿と花嫁の応答には、かぎ括弧などついてはいなかった。直情的に応答していたのである。花嫁は、これをかぎ括弧をつけ、第三者的に、遠いことのように耳にしているのである。人間は、自分のしてほしい絶対的なことに固執していると、どのように麗しいことばであっても、他のことに耳を貸すことをしないものである。例えば、この花嫁は、花婿が、さっそうとかけつけ、いじめっ子から助けてくれることを望んでいたのであるが、花婿は、愛のことばを言い残して、立ち去っていった。主も、私たちが何かに固執している限り、これがみこころだといって、無理やり引きずり出したり、怒鳴っておどして連れ出すようなことはなさらない。花婿は、花嫁に、おしんのように我力でただひたすら耐えることを望んでおられるわけではなく(それもすばらしいかもしれないが、花婿と歩むためには妨げとなる)、花嫁自身の足で、立ち上がってついてくることを望んでおられるのである。
立ち去った花婿を思い、花嫁は言う。「私の愛する方は私のもの。私はあの方のもの。」(雅歌 2:16)まだ、自我が捨てきれない花嫁。まず、「私の愛する方は私のもの。自分のもの。」と言っている。次に「私はあの方のもの。」ときている。こう言っていた花嫁が、後には、「私は、私の愛する方のもの。私の愛する方は私のもの。」(雅歌 6:3)と砕かれていくのである。「あの方はゆりの花の間で群れを飼っています。私の愛する方よ。そよ風が吹き始め、影が消え去るころまでに、あなたは帰って来て、険しい山々の上のかもしかや、若い鹿のようになってください。」(雅歌 2:16,17)ゆりの花、下にうつむくようにして咲くゆりの花は、へりくだりの象徴である。自我に固執する花嫁をおいて、花婿は、へりくだりの中で、群れを飼っている。立ち去った花婿を思い、花嫁は帰ってきてくれるように言っている。が、このことばの中には、自我がつまっている。「私の愛する方よ」と呼びかけてはいるが、次のことばは、「これこれこういう時までに、あなたは帰ってきて、こうこうこのようになるように。」と言っているのである。懇願ではなく、少し高い位置から、ことばはやわらかいが命令しているのである。「花婿なら当然よ」と言わんばかりである。これこれこういう時までにとは、どういう時までかと言うと、「そよ風が吹き始め、影が消え去るころまでに、」原文では、「そよ風が吹き始め」は夜のこと、「影が消え去るころ」も夜である。暗闇の時までに、ということである。「まあ、今はなんとか大丈夫だし、このままそっとしておいてほしいけど、もっと大変な暗闇の時になったら、あなたはすみやかに帰って来て、険しい山々の上のかもしかや、若い鹿のようになってくださいよ。」こういったところだろうか。この後、
 (段落記号、段落を表わす)が入っている。時が経った。
(段落記号、段落を表わす)が入っている。時が経った。
砕かれる自我
強がったものの、時が経つとともに、花嫁はだんだん、不安になっていった。すぐに、花婿を探し回ることになる。「私は、夜、床についても、私の愛している人を捜していました。私が捜しても、あの方は見あたりませんでした。」(雅歌 3:1)最初、花嫁のしたことは、捜しながらも、床につくことだった。「床について何もせず、休んでいよう。家宝は寝て待てと言うではないか。楽にして待っていれば、そのうち、時が来て、主(花婿)の方から、来てくださるに違いない。ハレルヤ。主よ、早く来てください。私は待っています。」信仰のように見えても、実は自我の中のあきらめである。寝て待つことは、ことわざであっても、聖書の真理ではない。聖書は、「求め続けよ、たたき続けよ、探し続けよ。」(マタイ 7:7参照)とある。「私が捜しても、あの方は見あたりませんでした。」と何もしていないのだから、達成感もなく、むなしさが残る結果となる。
達成感がないことから、花嫁が次にしたことは、人ごみ、にぎやかな通りを捜し回ることであった。「『さあ、起きて町を行き巡り、通りや広場で、私の愛している人を捜して来よう。』私が捜しても、あの方は見あたりませんでした。」(雅歌 3:2)にぎやかに働いている街中、奉仕に忙しい場所、奉仕の大通りの中、わいわいと華やいで活気づいているところで、捜し始めたのであった。括弧の中は、「私は・・・捜して来よう。」と私が主語の労働である。奉仕は、大切な事柄であるが、主の助けと祝福によってなさせてくださる恵みである。主を捜すためとか、誉れとか、自分のためにという動機でなしたところで、恵みを見出せるものではない。「私が捜しても、あの方は見あたりませんでした。」徒労に終わってしまう結果となる。主についての働きの大切さは、主とともに、主の後から、ということである。
次に花嫁がしたことは、出会った夜回りに聞くことであった。「町を行き巡る夜回りたちが私を見つけました。『私の愛している人を、あなたがたはお見かけになりませんでしたか。』」(雅歌 3:3)「町を行き巡る夜回りたち」群れの監督者であり、見張る者といえば、宗教的な指導者、牧師、教師たちのことである。彼らは、「どうしたの?」と花嫁を見つけて尋ねたことだろう。花嫁は、わらにもすがりたい気持ちで尋ねる。「私の愛している人を、あなたがたはお見かけになりませんでしたか。どこに行けば会えるのでしょうか。」と。しかし、彼らも彼女のための答えは持ってはいず、首をかしげただけであった。いよいよ、花婿に会いたい一心で、花嫁は捜し続ける。主はこのように限界になるまで、信仰をためされる。信仰を引き出し、高めるために。
「彼らのところを通り過ぎると間もなく(
 「僅か、最も少ない、すぐに」)、私の愛している人を私は見つけました。」(雅歌 3:4)床での休息、奉仕の大通り、夜回りでは見つからないことを学んだ花嫁が、捜す場所ももはやわからず、目をやると、偶然にもというか、花婿にしてみれば、この時をずっと待っていて、見守っていたからであるのだが、すぐに花婿を見つけることができたのであった。花嫁は、私は見つけましたと、言っているが、花婿は、花嫁のいる位置をいつも知っていて、待っていたのである。この瞬間を・・・。自我を手放す瞬間を・・・。「この方をしっかりつかまえて、放さず、とうとう、私の母の家に、私をみごもった人の奥の間に、お連れしました。」(雅歌 3:4)花嫁は、もはや、壁を作り、「放っておいてちょうだい。私は愛に病んでいるのだから。」という態度で接したりはしなかった。花婿への愛がほとばしり、目覚めたのである。自我のプライドを捨て、壁を自ら崩したのであった。自分のほうから、しっかりとつかまえて放さず、ことばだけではなく、態度をもっても、花婿の愛に応えたのであった。「私の母」聖霊さまは、私たちにみことばの光を照らし、私たちの霊の中にみことばを宿らせ、命を与えてくださる母なるお方である。聖霊さまの奥の間は、祈りの部屋である。花嫁は、祈りの部屋の戸を開け、花婿を連れて行った。祈り(花婿との語らい)の大切さをも悟ったのである。ぶどうの実を食べる狐、それは、人ではなく、自分の思い、そこから出た行動である。きっかけは、人から来たかもしれないが、狐に心を許し、疑いや不信仰の小狐を産むのは、自分自身である。狐を追い払い、不動の信仰に立つなら、神の国は広がっていく。花嫁は、花婿の呼びかけ、みこころを無視して、自分の意志・やり方で、花婿を捜したことによって、しばらくの間、花婿と離れ離れになるという犠牲を払った。しかし、この経験によって、自我をつつき、自我にしがみつかせようとするずるがしこい狐を追い払い、小狐を産ませないすべを学んだのである。
「僅か、最も少ない、すぐに」)、私の愛している人を私は見つけました。」(雅歌 3:4)床での休息、奉仕の大通り、夜回りでは見つからないことを学んだ花嫁が、捜す場所ももはやわからず、目をやると、偶然にもというか、花婿にしてみれば、この時をずっと待っていて、見守っていたからであるのだが、すぐに花婿を見つけることができたのであった。花嫁は、私は見つけましたと、言っているが、花婿は、花嫁のいる位置をいつも知っていて、待っていたのである。この瞬間を・・・。自我を手放す瞬間を・・・。「この方をしっかりつかまえて、放さず、とうとう、私の母の家に、私をみごもった人の奥の間に、お連れしました。」(雅歌 3:4)花嫁は、もはや、壁を作り、「放っておいてちょうだい。私は愛に病んでいるのだから。」という態度で接したりはしなかった。花婿への愛がほとばしり、目覚めたのである。自我のプライドを捨て、壁を自ら崩したのであった。自分のほうから、しっかりとつかまえて放さず、ことばだけではなく、態度をもっても、花婿の愛に応えたのであった。「私の母」聖霊さまは、私たちにみことばの光を照らし、私たちの霊の中にみことばを宿らせ、命を与えてくださる母なるお方である。聖霊さまの奥の間は、祈りの部屋である。花嫁は、祈りの部屋の戸を開け、花婿を連れて行った。祈り(花婿との語らい)の大切さをも悟ったのである。ぶどうの実を食べる狐、それは、人ではなく、自分の思い、そこから出た行動である。きっかけは、人から来たかもしれないが、狐に心を許し、疑いや不信仰の小狐を産むのは、自分自身である。狐を追い払い、不動の信仰に立つなら、神の国は広がっていく。花嫁は、花婿の呼びかけ、みこころを無視して、自分の意志・やり方で、花婿を捜したことによって、しばらくの間、花婿と離れ離れになるという犠牲を払った。しかし、この経験によって、自我をつつき、自我にしがみつかせようとするずるがしこい狐を追い払い、小狐を産ませないすべを学んだのである。
狐を追い払おうとする時に、やはり、他人の干渉を相手にしている余裕はない。花嫁は、エルサレムの娘たちに、再度、念を押す。「エルサレムの娘たち。私は、かもしかや野の雌鹿をさして、あなたがたに誓っていただきます。揺り起こしたり、かき立てたりしないでください。愛が目ざめたいと思うときまでは。」(雅歌 3:5)狐は、ずるがしこく、自我を突付いてくるかもしれないが、私たちがなさなくてはならないことは、心に侵入し、聖霊の実すらも食べ尽くし、収穫の実をも成らせないようにする狐、小狐から、自分の畑を守ることである。
–> 次の記事:『煙の柱のように-婚礼の時―』

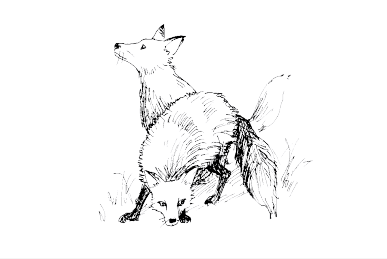


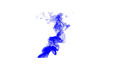
コメント