<– 前の記事:ローマ国教化後の教会~イスラームの台頭
教会で語られている教えの何が歴史的に伝わってきた人間的な教えで、何が聖書の真理であるかを明らかにするために、教会の歴史を見ている。今回は7回目となる。
前回は、教皇側の西ローマ帝国と、皇帝側の東ローマ帝国にローマが東西に分裂したところを見てきた。長く続いてきた多神教色の強いローマの伝統や慣習の影響を断ち、ローマを離れてキリスト教の都を建設するためという考えももって、330年にコンスタンティノープルに遷都してローマ教会とは別に教会が作られた。西ローマ帝国は、ゲルマン人が移動してきたことにより、476年に滅亡したが、フランク王国と手を取り、800年に帝国を復活させた。前回は、国教化後まもなく分裂したローマ教会、ゲルマン人による圧迫と弱体化、イスラーム教の起こり・・・といった内容を見た。
東ローマ帝国では 年表 p5 参照
ゲルマン人による被害を比較的受けなかった東ローマ帝国は、地中海貿易によって繁栄し、中国から養蚕業の技術も取り入れて、発展していき、首都コンスタンティノーブルは、ヨーロッパ最大の商業都市となった。教皇と皇帝は別にして宗教と政治を区別していた西ローマ帝国とは異なり、東ローマ帝国では、皇帝が宗教と政治両方の最高権力者であった。東ローマ帝国は後に「ビザンツ帝国」と呼ばれる。ビザンツというのは、首都コンスタンティノープルの旧名で、16世紀頃に、7世紀以降のギリシャ文化とキリスト教が融合されていった時代の東ローマ帝国を「ビザンツ帝国」と呼ぶようになったと言われている。ギリシャ文化とキリスト教が融合した独自文化を形成し、発展していったビザンツ王国は、ギリシャ正教と呼ばれ、北方のスラブ人やロシア人に広がっていった。
西ヨーロッパに広がっていったキリスト教(ローマ・カトリック教会、カトリックはギリシア語の普遍的、世界的、全体的の意)は、ペテロやパウロが築いたローマ教会を中心に、ローマ教皇主導で政教が分離され、正統派とされていて神学が発展していった。ゲルマン人に布教してキリスト教徒にし、帝国の復活を遂げた西のローマ教会は、わかりやすく伝えられると考えたのか、ゲルマン人の布教にイエスやマリヤの聖像を用いていた。前回見たように、イスラーム教では徹底した偶像崇拝の否定が行われ、キリスト教で行われていた聖像崇拝を厳しく批判し始めていたこともあり、ビザンツ帝国内の聖職者の中にも、聖像崇拝を否定する考えが起こり出し、論争となっていった。
726年、ビザンツ帝国の皇帝レオン3世は、聖像禁止令を出し、聖像の製造禁止と破壊を命じた。イスラーム側からの批判を封じるとともに、反対する教会・修道院領を没収する狙いもあったようである。聖像をめぐっての論争は、東方教会と西方教会の対立に発展していった。ゲルマン人の布教に聖像は不可欠であった西方教会(ローマ・カトリック教会)は、レオン3世皇帝の聖像禁止令に反発し、聖像破壊は最も悪質な反教会的行為とされ、聖像破壊者(イコノクラスト)は異端であると考えられるようになり、次第に東西教会の対立は決定的となった。皇帝側の東ローマ帝国との対立が深刻となった西ローマ帝国では、保護者となる新たな王が必要となり、フランク王国との関係を深めていった。こうして、最終的には西と東の教会は1054年に互いに破門し合って決定的分離となった。聖書ではなく、政治的な考えや人や世に合わせた効率的伝道を取り入れていくと、すぐにはその影響が見えてこないかもしれないが、内部分裂や周囲のつまずきを招き、長年かけて、その実が現われてくる。深刻化した争いは修復できないまま進んでいく。
地中海のほぼ全域を占め発展していたビザンツ帝国であったが、長期の戦争や北のスラブ人などの異民族の移住によって、国力が低下し、1453年にオスマン帝国に滅ぼされ(オスマン帝国:アナトリア半島〈現トルコの小アジア〉の片隅に生まれた小さな君侯国〈君主が治めている国〉から出たイスラームの王朝が発展した世界帝国)、首都のコンスタンティノーブルはイスタンブールと改称された。こうして東ローマ帝国(ビザンツ帝国)は滅んだ。
海岸付近で商業・略奪行為を行っていた北方系のゲルマン人(ヴァイキング)であるノルマン人が建国したノブゴロド国(現在もロシアの地名にある)という商業都市国家があった。そのノブゴロド国から一部のノルマン人が移動して、新しくキエフ公国というロシア国家を作った。先住民のスラブ人(ギリシャ正教)と結婚を繰り返し、同化していき、ビザンツ帝国をまねた独自文化を発展させていった。
モンゴル高原東部の遊牧部族であったチンギス・ハンが、1206年にモンゴルに大帝国を建設していた。そのモンゴルが侵入し、1240年にキエフは占領され、キエフ公国は滅亡し、ロシア地方は厳しい支配化に置かれた。キエフ公国がモンゴルに滅ぼされてから、ルーシ(ロシア)はいくつかの地方政権に分かれたのだが、次第に有力となったのがモスクワ公国であり、その後、領土を拡大していき、モスクワ大公国と呼ばれるようになった。イヴァン3世が国土を統一して、モスクワ大公国の独立を果たした。1472年、イヴァン3世は、ビザンツ帝国の最後の皇帝コンスタンティノス11世の姪ソフィアを2番目の妻とし、自身をビザンツ帝国の継承者であると宣言し、モスクワを(ローマ、コンスタンティノープルに続く)「第3のローマ」と称して、総主教である教会(ロシア正教会)をモスクワに置いた。
一方、ブリテン諸島に渡ったゲルマン人は、先住民を征服し、7つの小王国を建設し、その後、統一しイングランド王国となっていた。911年、ヴァイキングの首領ロロが、ノルマン人を率いてフランス(西フランク)に侵攻した。フランス王シャルル3世は、キリスト教への改宗など西フランク王国の臣下となることを条件に、セーヌ川下流域の定住を認め領地を譲渡した。ロロはその領地に、ノルマンディー公国を建国した。1066年にロロの子孫ウィリアム1世がイングランドを征服し、ノルマンディーとイングランドを併せたノルマン朝イギリスが誕生した。
西ローマ帝国では
西ローマ帝国の東フランク王国(ドイツ)では、フランク人の王の血筋が途絶え、ドイツ王国が形成され、後にドイツ王を中心とした複合国家ができ、ローマ教会のキリスト教世界を守護するという理念から、「神聖ローマ帝国」と言われるようになった。962年にローマ帝国皇帝となったドイツのオットー1世は、国内の有力諸侯たちの力を抑えるために、教会の力を利用しようとした。教会に土地を寄進する代わりに、自分の一族や関係者を司教などの聖職者にし、教会を統制支配する政策を打ち出した(帝国教会政策)。この政策によって、ローマ=カトリック教会の高位聖職者の任免権は、神聖ローマ皇帝が持ち、下位聖職者任免権も国王や領主が持つようになり、世俗化が進むこととなった。
1073年にローマ・カトリック教会の教皇となったグレゴリウス7世は、聖職者の堕落を戒め、教皇の権威を回復するために教会の改革を推進し、1075年に「グレゴリウス改革」を行なった。この改革の一環として、神聖ローマ帝国皇帝を頂点とした「世俗権力が持つ聖職者を叙任できる権利(聖職者叙任権)」を否定した。このことに、神聖ローマ帝国の皇帝ハインリヒ4世はオットー大帝以来の帝国教会政策に立って強く反発したのだが、グレゴリウス7世教皇は教会会議を開催してハインリヒ4世皇帝の破門を決定したのであった。破門が実行されると帝国内の諸侯たちに対する統制力を失うことになるので、困ったハインリヒ4世皇帝は許しを請うために、1077年の正月、厳冬のアルプスを超えて、教皇の滞在するカノッサ城を訪ねた。グレゴリウス7世教皇は会おうとしなかったのだが、ハインリヒ4世皇帝は3日間、雪の中にわずかな修道衣のみの素足で立ちつくし、面会を請うたのであった。カノッサ城主や修道院長のとりなしで会えることとなり、やっと面会に応じたグレゴリウス7世教皇は、皇帝の聖職叙任権の否定を認めさせた上で破門を解いた(カノッサの屈辱)。この事件から、ローマ教皇の権威は強くなっていった。教皇の権力が強くなっていったことが、この後の十字軍へとつながっていく。
この頃になると、キリストや使徒たちが教え、行動に現れていたキリストの精神は、見えてこなくなってしまっている。旧約時代は、神の仰せによって罪と戦い罪を聖絶するためにカナン先住民と戦ったのだが、その形だけを利用しての領土拡大と権威争いが目についてくる。主イエスは、「剣を取る者はみな剣で滅びます。」(マタイ 26:52)と言われ、戦う心を戒められた。「剣で殺す者は、自分も剣で殺されなければならない。ここに聖徒の忍耐と信仰がある。」(ヨハネの黙示録 13:10)とあるように、聖徒に見られるのは、剣の殺し合いではなく、忍耐と信仰である。
イエスは言われた。
「何事でも、自分にしてもらいたいことは、ほかの人にもそのようにしなさい。これが律法であり預言者です。狭い門からはいりなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そして、そこからはいって行く者が多いのです。いのちに至る門は小さく、その道は狭く、それを見いだす者はまれです。」(マタイ 7:12-14)
「努力して狭い門からはいりなさい。なぜなら、あなたがたに言いますが、はいろうとしても、はいれなくなる人が多いのですから。家の主人が、立ち上がって、戸をしめてしまってからでは、外に立って、『ご主人さま。あけてください。』と言って、戸をいくらたたいても、もう主人は、『あなたがたがどこの者か、私は知らない。』と答えるでしょう。すると、あなたがたは、こう言い始めるでしょう。『私たちは、ごいっしょに、食べたり飲んだりいたしましたし、私たちの大通りで教えていただきました。』だが、主人はこう言うでしょう。『私はあなたがたがどこの者だか知りません。不正を行なう者たち。みな出て行きなさい。』」(ルカ 13:24-27)
国教化され、大きく広い門になったキリスト教は、人間の罪も取り込みながら、分派しつつ広がっていった。キリストによって神の教え(みこころ)を伝え、贖いを成し遂げられ、信仰者の助けとなる聖霊を与えられた後、神は人の罪に対し沈黙され、人間の歩みをなすがままにされているかのように、時の為政者たちは神の名のもとに、権威をふるってきた。沈黙されているかのように見える神は、押さえるべきところは押さえ、守られている。現代に至るまで聖書を通じて、神を知ることができている。また、苦しみを経ても耐え忍び神に従おうとする信仰の残りの者たちは、どの時代にも存在している(存在しているからこそ、現在まで信仰が受け継がれてきた)。やがて沈黙されている神が、動かれる時が来る。神の定められた時にである。聖書を通じて示されている神の計画のうちにある終わりの時が来る。その時、どのような兆候があるかは聖書に語られているが、「いつとか、どんなときとかいうことは、あなたがたは知らなくてもよいのです。それは、父がご自分の権威をもってお定めになっています。」(使徒 1:7)とキリストが言われたように、人知を超えた神のみわざであり、その時も「神が定められた時」から超えてはならない。私たち信仰者は、その時の訪れまで、ともしびの油を絶やさずに、神を信じ従っていく(みこころを行なっていく)のみである。神が言われたことを超えて神に属する領域を知りたがるのは、アダムとエバ以来の人間の罪の姿である。わからないことは神に信頼して委ね、満ち足り、平安のうちを歩んでいこう。
–> 次の記事:神の名を語った戦い~罪の広がり
参考:世界史の窓 https://www.y-history.net/index.html
関連記事:「クリスチャンが日曜日に礼拝する理由」

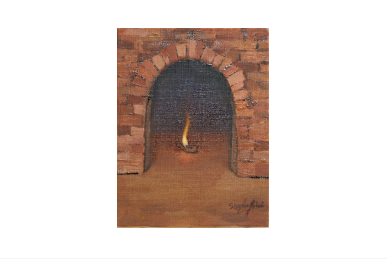


コメント