<– 前の記事:『救いの道-悔い改めと信仰-』
聖書個所:ルカの福音書3章21節~38節(新改訳)
『宣教の前説-王の王であるメシアは人の子として来られた-』
前回は、ヨハネがヨルダン川のほとりのすべての地方で神への悔い改めを説き、バプテスマを授けているところを見た。こうして、主イエスが神の国の福音を宣べ伝える前の道を整え備える役割を担ったのである。そうして、悔いた低い心の者たちに主イエスの救いが届けられていった。
バプテスマを受けられたイエス
「さて、民衆がみなバプテスマを受けていたころ、イエスもバプテスマをお受けになり、そして祈っておられると、天が開け、聖霊が、鳩のような形をして、自分の上に下られるのをご覧になった。また、天から声がした。『あなたは、わたしの愛する子、わたしはあなたを喜ぶ。』」(ルカ 3:21-22)
「私は水であなたがたにバプテスマを授けています。しかし、私よりもさらに力のある方がおいでになります。私などは、その方のくつのひもを解く値うちもありません。その方は、あなたがたに聖霊と火とのバプテスマをお授けになります。」(ルカ 3:16)と言っていたヨハネのもとに、イエスもバプテスマを受けに来られた。自分とは比較にもならない存在、「聖霊と火とのバプテスマを授けるお方」「手に箕を持って脱穀場をことごとくきよめ、麦を倉に納め、殻を消えない火で焼き尽くされるお方」(ルカ 3:17)、そのお方が、他の民衆と同じように、ヨハネからバプテスマを受けようとガリラヤからはるばるやって来られたのである。ヨハネはとても驚いたことだろう。マタイの福音書の方には、驚いたヨハネの言葉が記されている。「ヨハネはイエスにそうさせまいとして、言った。『私こそ、あなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが、私のところにおいでになるのですか。』」(マタイ 3:14)
人としてのイエスは、ヨハネから悔い改めのバプテスマを受ける必要がない罪のないお方であった。「ところが、イエスは答えて言われた。『今はそうさせてもらいたい。このようにして、すべての正しいことを実行するのは、わたしたちにふさわしいのです。』そこで、ヨハネは承知した。」(マタイ 3: 15)神であられるのに、使命をもって人の形をとって地上に来られたイエス。人としての手順をとって無力な赤子の姿で生まれるところから始まり、両親に仕えながら育ち、私たち人間と同じような環境の下で、人間と同じように暮らし、大人になられた。それは、人類が歩むべき模範を示すための必要な手順でもあった。
主イエスは、神と人をつなぎ、とりなす仲介者でもあられるお方だ。ヨハネのもとにバプテスマを受けに来られたのは、模範を示すためにという高い位置から来られたのではない。使命だから仕方がないと強いられて来られたのでもない。いとこのヨハネが行なっているから私も協力しようと人間的な情で受けられたわけでもない。たまたま暇だったからと興味本位で来られたわけでもない。少年イエスの回で見たように、どの時代を見ても一貫していて仲介者であられる主イエスは、罪人と一体になって、その罪を負い、神の前に悔い改めの心をもってヨハネからバプテスマを受けられたのである。「わたしたちにふさわしい」詳訳聖書1を見ると「私たち〈ふたり〉にとって、すべての義を成就するための〈すなわち、正当な事はなんであっても完全に遂行するための〉正当な道だからである」となっている。ヨハネのバプテスマを受けることは、ヨハネとイエスの役割にとって、また完全な道を通るための省略できない事柄であった。
イエスがヨハネからバプテスマを受けられ、祈り(ルカ 3:21)、水から上がられると(マタイ 3:16、マルコ 1:10)、聖霊が、鳩のような形をして、イエスの上に下り、天から「あなたは、わたしの愛する子、わたしはあなたを喜ぶ。」という声がした(ルカ 3:22)。父なる神の声、子なるイエス、鳩のように下った御霊、三位一体が目に見える形で表された尊い出来事である。この後イエスは、神の国を伝える宣教の働きに入られるのだが、その初めに表されたイエスとともにある神の権威。実際に見ても人から伝え聞いても信じない者は存在する一方で、信じる者たちの手によって、福音は伝えられ、聖書が記されていった。
「教えを始められたとき、イエスはおよそ三十歳で、人々からヨセフの子と思われていた。」(ルカ 3:23)「およそ三十歳」ぴったりではない。ちょうど三十歳とは記されていない。そんなに重要ではないところは、限定的に書かれず、ぼかされている。知識を誇る方向に行くと、人は重要でないところで自説を打ち立て、それが論争に発展していく。論争が治まらないと、分裂を招いていく。教会が、互いの愛と神の知恵によって、治められていって、一致を保って、キリストという一枚岩でいられたらよいのだが、歴史を見ても、一枚岩でいられない人間の性質が存在している。聖書は、一致を「作れ」ではなく「保つように」と書かれているが(エペソ4:3「平和のきずなで結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。」、ピリピ 2:2「あなたがたは一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。」)、キリストの名のもとにすでに与えられている一致を散らすのは、人間の業である。本質には関係がないような人間に知らされていないようなことは、わからないでとどまることも時には大切である。イエスは、聖霊によって処女マリアの体に宿り生まれた神の子(神)であったのだが、人々からはヨセフの子と思われていた。
系図の食い違い
次に、「このヨセフは・・・」で始まる系図が書かれている。ルツ記の講解で系図について、下記のように述べた。
・・・書簡によって系図に食い違いがあるのだが、これは、必要に応じて書かれた違いであり、違いがあるからと言って真理に影響するものではない。聖書の系図で重要な事はその書簡が意図する系図の流れである。(マタイとルカのダビデ以降の系図にも違いがあるが、それは「マタイはヨセフによる王の系列、ルカは生まれの系図」「マタイはヨセフ側、ルカはマリア側の系図によってイエスの系統がダビデの血筋であることを示した」「ヨセフの養子と実子の関係性による系図」「ヨセフの母方と父方の系図」等いくつかの仮定による説があるが確証されていない)
https://cvsa.jp/column/『贖いにも手順がある-律法に従って-』/
ルツ記の場合、系図は、ルツ記に記した出来事が、ユダからダビデ王につながる系図につながっていることを表していた。では、マタイとルカは、系図を記すことで何を伝えたかったのだろうか。マタイの福音書は、イエスが旧約の預言者たちによってあらかじめ語られたメシアであることを伝えていて、主にユダヤ人を意識して書かれた書簡であると言われている。ルカの福音書は、イエスの人性が強調されていて、ギリシャ人に伝えることを意識して書かれていると言われている。ルカの福音書は美しいギリシャ語で書かれていて、「かつて記された中で最も美しい本」と言われているのだが、教養や哲学に秀でていたギリシャ人たちの心に届くよう、イエスの生涯の輝かしい美と完全さが描かれている。
「・・・人々からヨセフの子と思われていた。このヨセフは、ヘリの子、順次さかのぼって、」(ルカ 3:23)であるが、いくつかの仮説がある中で、「マタイはヨセフ側、ルカはマリヤ側の系図」と言われるのをよく聞き、新改訳聖書では「ヘリの子」の欄外の「ヘリ」の注釈として「イエスの母マリアの父。ヨセフの義父、『エリ』とも読む」と記されているため、「マタイはヨセフ側、ルカはマリヤ側の系図」というのが正解のように見える。しかし、聖書学者の間で、そうではない説が存在している。
古い伝承(2世紀に記されたマリヤの誕生を記した外典「ヤコブ原福音書」にも書かれている)では、マリアは、ヨアキムという名の大変裕福な男性とアンナという女性のもとに生まれダビデの家系に属していたと言われている。「ヨアキム」は「エリヤキム」でもあるので、「エリ(ヘリ)」はヨアキムの別称ということもできるそうである。マタイとルカの系図の食い違いは、古代教会(2世紀)で早くも論じられてきたような、はっきりしないものである。この食い違いがよくわからず論じられていた証拠として、エウセピオス「教会史」Ⅰ七に保存されたアフリカヌス(160~240年頃)の答案を訳した長い文章が、註解書に掲載されていた(新聖書註解 新約1 いのちのことば社発行 p335)。その記録によると、イスラエルにおける系図は、子なくして死んだ者の名を残す意味で、実の親ではない律法としての幾人かを含むことがあり、食い違いもありうることのため、古代の教会では、ヨセフの系図とマリアの系図の食い違いという受け取り方はしていなかったようである。
聖書から読み取ったマリアの性質(思慮深く謙遜)から見て、私はこの個所にマリアの系図が書かれることに疑問を感じる(控えめにマリアの名を伏せただけという意見もあるかもしれない。しかし、「ヨセフは、ヘリの子」というのが、「ヨセフは、ヘリの子(義理の子だけどね)順次さかのぼって、(ここからは義理ではなく本当の子だよ)マタテの子、…」というような書き方を聖書に記すだろうか???腑に落ちないところである) 。教会には、キリスト教が国教化され、ゲルマン人への布教のため、絵画や聖像を取り入れ、マリアへの尊敬の念以上のマリア崇拝の教理が入り込んだ歴史がある。
なので、現状では、「・・・人々からヨセフの子と思われていた。このヨセフは、ヘリの子、」とここにマリアの名が出てこない以上、なぜ唐突にマリアの系図とするのか疑問が残るため、ヨセフの系図ということにとどまっていたい。(有力な証拠となる情報が出てきたら変わりうるが・・・。ヨセフもマリアもダビデの家系であることを記したという理由も考えうるが、それならば「・・・人々からヨセフの子と思われていた。このヨセフの妻は、ヘリの子、順次さかのぼって、」と書いてもよいところを省き、書いておきたいはずのマリアの名が書かれていない疑問が残る)
イエス・キリストの系図
「このヨセフは、ヘリの子、順次さかのぼって、マタテの子、レビの子、メルキの子、ヤンナイの子、ヨセフの子、マタテヤの子、アモスの子、ナホムの子、エスリの子、ナンガイの子、マハテの子、マタテヤの子、シメイの子、ヨセクの子、ヨダの子、ヨハナンの子、レサの子、ゾロバベルの子、サラテルの子、ネリの子、メルキの子、アデイの子、コサムの子、エルマダムの子、エルの子、ヨシュアの子、エリエゼルの子、ヨリムの子、マタテの子、レビの子、シメオンの子、ユダの子、ヨセフの子、ヨナムの子、エリヤキムの子、メレヤの子、メナの子、マタタの子、ナタンの子、ダビデの子、エッサイの子、オベデの子、ボアズの子、サラの子、ナアソンの子、アミナダブの子、アデミンの子、アルニの子、エスロンの子、パレスの子、ユダの子、ヤコブの子、イサクの子、アブラハムの子、テラの子、ナホルの子、セルグの子、レウの子、ペレグの子、エベルの子、サラの子、カイナンの子、アルパクサデの子、セムの子、ノアの子、ラメクの子、メトセラの子、エノクの子、ヤレデの子、マハラレルの子、カイナンの子、エノスの子、セツの子、アダムの子、このアダムは神の子である。」(ルカ 3:23b-37)
マタイの福音書の系図では、アブラハムからダビデ、ダビデからバビロン移住(移送)まで、バビロン移住からキリストまでに焦点を当て、それぞれ十四代(完成の完全数7×証の数2)とし、古い時代から新しい時代を追って「~に~が生まれ」という表現で描いている。
一方、ルカは、キリストからさかのぼり、ダビデ、アブラハムを通り、アダムまで「(~は)~の子」という表現を用いて記している。
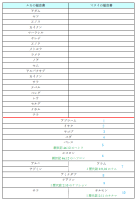
マタイが、アダムからではなく、アブラハムから始めているのは、ユダヤ人にとっては、信仰の父アブラハムまでの系図は熟知していたからで、ルカは、ギリシャ人に向けて人類の始まりから哲学的に記したのだろうことが伺える。ユダヤ人たちに向けてイエスが旧約の預言者たちによって語られているメシアであることを伝えようと、マタイは区切りの時代を十四代にまとめて記した。中間のヨラムとウジヤの間の三代の血縁の王(アハズヤ、ヨアシュ、アマツヤ)と、バビロン捕囚直前のヨシヤとエコニヤの間の血縁の王(エホヤキム)は除かれているが、マタイは、王の王主の主メシアであられるイエスの王としての血縁を描いたのである。
年表 P1~P3参照
除かれている王を見てみよう。ヨシャパテの息子のヨラムの息子のアハズヤは、一年間王であったが、主の目の前に悪を行なった王であった。彼は神がエリヤに与えた預言に従ったエフーの謀反で死んだ(Ⅱ列王9章)。
この謀反の混乱により、アハズヤの母アタルヤが一時的に(6年間)王となった。アタルヤは、息子が死んだと知ると王の一族(息子アハズヤの子孫、自分の孫)をことごとく滅ぼしにかかるような悪魔的な人物であった。アタルヤの手から隠し守られたアハズヤの息子ヨアシュが七歳になった第7年目に、祭司エホヤダの指揮でヨアシュが王になった(Ⅱ列王11章)。
ヨアシュは、祭司エホヤダが生きて指導していた間は、主の目にかなうことを行なったのだが、エホヤダが百三十歳まで長寿を全うした後は、アシェラと偶像に仕えるようになった。主に立ち返るようにという預言者たちの言葉に耳を貸さず、神の戒めの言葉を伝えた祭司エホヤダの息子ゼカリヤを石で打ち殺した。そのような中、アラムの軍勢が攻めてきて民のつかさたちを全員殺し、分捕り物を奪っていった。アラムを恐れたヨアシュは、主の宮の宝物倉にある先祖代々のすべての金をアラムの王ハザエルに送り難を逃れた。こういったことから、40年目に病床に着いていたところ家来たちの謀反の手にかかり、ヨアシュは生涯を終えた。彼は、王の墓には葬られなかった(Ⅱ列王12,13章、Ⅱ歴代24章)とある。
次にヨアシュの息子のアマツヤが二十五歳で王となった。彼は、主の目にかなうことをダビデのようにではなく、父ヨアシュが行なったとおりを行なった。偶像に仕える高き所は取り除かなかった。アマツヤは、王としての地盤が固まってくると、父ヨアシュを殺した家来たちを殺した。そして、北イスラエルの王ヨアシュに戦いを挑み、戦いを避けようとする北イスラエルの王ヨアシュの言葉を聞き入れず、戦ったところ打ち負かされ、エルサレムの城壁をも壊され、主の宮と王宮の宝物倉にあった金銀、器具、人質をサマリヤに奪われた。二十九年目に彼は、エルサレムの人々による謀反で死んだ。
マタイの王の系図では、ヨラム王とウジヤ王の間にあるはずの、このアハズヤ、ヨアシュ、アマツヤの3人の名が省かれているのである。
バビロン捕囚の頃の王でヨシヤの息子のエホヤキムもまた系図から除かれている。エホヤキムの前にヨシヤの息子エホアハズが三か月間王であったが、父ヨシヤを殺したエジプトの王パロ・ネコが、ヨシヤの息子エホヤキムを王に立て、エホアハズを捕らえてエジプトへ連れていった。エホヤキムは、パロ・ネコの要求するだけの金銀を差し出すために、民に重税を課した。エホヤキムの時代にバビロン捕囚を迎えた。
その後は、エホヤキムの息子エホヤキン(マタイ1:11,12のエコニヤ)が王となったが、三ヶ月後にバビロンに連れ去られ、バビロンの王がエホヤキンの叔父のゼデキヤを王とした。このゼデキヤは、バビロン王に反逆し、目の前で子供を虐殺され、両眼を抉り取られ、死ぬまで鎖につながれ、生涯を終えた。エルサレムは陥落した。一方、バビロンに降伏して捕虜としてバビロンに行ったエホヤキンは、三十七年目に釈放されて自由を与えられ、その後は、王の前で食事をし、生活費は王から支給されて生涯を送った(Ⅱ列王23-25章、Ⅱ歴代36章)。
マタイの王の系図では、11年間王であったヨシヤの息子エホヤキムが省かれ、その後王となり3か月目にバビロンに降伏して、バビロンに連れていかれたエホヤキムの息子エホヤキンが名を連ねて、その後は、バビロン移住の後に生まれた(マタイ 1:12)サラテル(ルカの福音書にも存在)に続いている。
信仰的な善い王とか悪い王とかといった単純な理由ではなく、神の霊感による何らかの必要があって、省かれているようである(Ⅱテモテ 3:16「聖書はすべて、神の霊感によるもの」)。
預言されていたメシアであるということを伝えるために、マタイは何らかの目的をもって、十四代に集約して王家を受け継ぐ者として系図を起こして、ルカは、実際の血筋を描いたと思われる。ダビデ以降の系図は、双方、エコヌヤの子のサラテルにたどり着いている。
先ほどふれた「エウセピオス『教会史』Ⅰ七に保存されたアフリカヌス(160~240年頃)の答案」では、ルカの福音書ではヨセフの四代前のメルキと、マタイの福音書でヨセフの二代前に書かれているマタンは、「同じ妻の継続した夫たちで義理の兄弟を生んだ」と書かれている。要約すると、「妻の名はエサと言って、マタンに嫁いでヤコブを産んだが、マタンが死んだため、メルキに嫁いでヘリに至る子を産んだ。ヘリは子をもうけずに死んだため、ヤコブがヘリの妻をめとり、ヘリの妻とヤコブによってヨセフは生まれたので、ヨセフの父は、ルカでは律法上の家系としてヘリの子、マタイでは実際の血縁としてヤコブの子と書かれている。」と書かれていた。2
系図にある真実は、実際のところエビデンスが不十分のため誰にもわからないが、ギリシャ人へのアプローチとユダヤ人へのアプローチという目的による差が、意図的にこの食い違いを作ったようである。それでも言えることは、キリストの福音を伝えたい対象者に向けて、キリストについての宣教内容を語る前に、系図により、今から語ろうとするキリストがどのようなお方であるかを知ってもらいたいという目的で記されたということである。
すでに旧約を知っているユダヤ人には、メシアとしての生まれであるということを、ギリシャ人には、神の子であるが、人としての素性を語るならと、「・・・人々からヨセフの子と思われていた。このヨセフは、・・・」と説明したと思われる。ルカの福音書は、1章から3章の系図の前の個所で、神によって処女マリアから誕生したいきさつが詳しく述べられた後の記述である。
「マタイはヨセフによる王の系図、ルカは生まれの系図」のように思えるのだが、「マタイはヨセフ、ルカはマリアの系図」や他の説が事実であったとしても、他へさほどの影響は与えないところである。実際どうであったかは、天に行ってルカさんにどういうふうに記されたかを聞いてみないとわからない。ともかくも、聖書が語る真理に影響を与えないものであれば、違いはどうであれ、キリストの律法を全うしつつ、一致を保っていきたいものである。
–> 次の記事:『悪魔の誘惑-示された威光-』





コメント