<– 前の記事:『イエスが来られた世-神の愛からの逸脱-』
聖書個所:ルカの福音書5章27節~39節(新改訳)
『両方を長持ちさせる知恵-ひとりも滅びることなく-』
前回は、カペナウムの家で、イエスが人々に教えておられ、そこにパリサイ人や律法学者たちがすわっていたという場面であった。イエスが人の形を取ってこの世に来られ、悔い改めの宣教をなされたこの時代になるまでの、神の民の歩みをおさらいしてみよう。
天と地を造られた神が、「われわれに似るように、われわれのかたちに、人を造ろう。そして彼らに、海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地をはうすべてのものを治めさせよう。」(創世記 1:26)という意図をもって、この世は造られ、人間は存在するようになった。
すべてがよくできていた世界だったが、アダムとエバが蛇の誘惑により、罪を犯し、その後のすべての人類に罪が入ってしまった。そのような人類に、神は、救済の道を与えられた。罪が増大し、ノアの洪水、アブラムの召し出しを経て、神の民を選び出されたのであった。こうして、「罪の結果は永遠の死に至る滅びである」のだが、「すべての人が救われて、真理を知るようになるのを望んでおられ(Ⅰテモテ2:4)、ひとりでも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられる神(Ⅱペテロ 3:9)」は、「人々が永遠の死という苦しみの道」から逃れ、永遠の命に至る救いの道を歩むことができるよう、「律法という神の愛から出た規範」を与えて、いのちに至る道を教えようとされた。信仰による神の民を召し出され、罪から離れるよう忍耐を持って指導されたのである。
神の民が神よりも王を望んだ時も、神は許容し、王制のもとで神に従って生きるよう道を示された。それでも罪は蔓延し、神の民がもう自力では神に立ち返ることができないほどの罪の世界になった時、捕囚という形で、形骸化した神の民の共同体を破壊された。しかし、それは、信仰を矯正(是正)するための一定期間の神の許しの中のことであった。
国を失い、神を知らない他の国に支配されるという苦しみを通り、信仰に立ち返って神に仕える決意をもって、神の民の共同体は形成されていった。時代が変わって帰還する者もいたが、散らされた各地で共同体を形成する者もいた。そのような旧約の神の民の共同体は、律法を守ることに力を注ぎ、言い伝えとともに戒律として教える指導者たちが教えるようになっていた。指導者たちは、社会的地位や主張の違いにより宗派(主にパリサイ派とサドカイ派とエッセネ派)を形成していた。
時は、ローマ支配が強くなる世の中にあり、ユダヤはローマに従属する立場にあった。ローマの機嫌を取りつつ、律法の戒律による宗教的教育を行っているような不安定な状態であり、神に立ち返る人々を起こすためには、神の直接的な介入によって神の愛を知らせることが必要になっていた。
イエスの目に留まったマタイ
さて、イエスが人の形をとってこの世に来られ、宣教を開始され、評判が広まるにつれ、それが気に入らない指導者たちは、イエスを監視するようになっていた。神の権威を帯びたイエスの言動は、彼らにとっては律法に反する「罪」としか見えていなかった。「神の愛」がそこにあるにもかかわらず、自分を基準とし視点が違うと「罪」にしか見えない。イエスにとって、そのような指導者たちは、次章で「いったい、盲人に盲人の手引きができるでしょうか。ふたりとも穴に落ち込まないでしょうか。」(ルカ 6:39)と言われている「盲人」であった。
「この後、イエスは出て行き、収税所にすわっているレビという取税人に目を留めて、『わたしについて来なさい。』と言われた。」(ルカ 5:27)「この後」というのは、束になってイエスを見定めに来ていたパリサイ人、律法学者とのやり取りの後である。神の愛を説かず、半身不随で寝た切りの生活で苦しんでいた中風の人に憐みも示さず、「罪人」という見方をしていた指導者群であるパリサイ人、律法学者たちを前に、イエスが、中風の人に罪の赦しを宣言し、病をお癒しになった後である。中風の人を癒された後、イエスは再び、ゲネサレ湖(ガリラヤ湖)のほとりに行かれた(マルコ 2:13)。その道すがら、収税所の前を通りかかり、そこにすわっている男に目を留められた。当時のユダヤ社会では、病気は何かの罪の結果であり、長年重い病気にかかっている人=罪人と見なされていたが、取税人もまた罪人扱いであった。
取税人の立場
取税人というのは、主にローマ帝国の税金を取り立てることを請け負った下級役人のことである。地方の税金はローマ人が直接徴収することはせず、地方の請負人に請け負わせた。こうすることによって、被征服地域から、危険や暴動を起こされることなく、確実に収入を得ることができた。このような仕組みの中で、取税人たちはできるかぎり金もうけをしようとしていた。ローマ政府は税額の査定をするだけであったため、取税人は自分たちの好きなだけ上乗せして、私腹を肥やすことができた。たとえ民がローマに訴えたとしても、ローマ政府は収入源を失いたくなかったので耳を貸すことはなかった。そういうことにより、取税人はローマの属州の至る所で同胞に憎まれていた。ユダヤにおいても、取税人は強奪者と思われ、嫌悪の的となっていた。また、取税人は常に異邦人(ローマ人)と接触していたことから、汚れた罪人と見なされ、異邦人や遊女と同じように見なされていた。
取税人という職の人たちは、常に自分は罪人であるという意識がつきまとい、それでもローマ支配の属国の中で生きていくために、徴税の仕事についていた人たちであった。罪人の自覚があったため、バプテスマのヨハネの所に、バプテスマを受けに出てきて、「先生、私たちはどうすればよいでしょう。」(ルカ 3:12)と素直に聞けたのである。そのような取税人たちに、ヨハネは仕事をやめるようにとは言わず、「決められたもの以上には、何も取り立ててはいけません。」(ルカ 3:13)とだけ教えられた。それは、決められた税に上乗せはせず、役人としての給料で満足しなさいということであった。
ローマ人と平和にかかわっていこうとする取税人(ユダヤ人)へのユダヤ人たちからの視点は、自分たちの信条と違っている者たちを見下している心が存在している。自分たちは、彼らとは違ってきちんと律法を守っている者であるという視点である。神の愛から離れ、原罪を持つ私たち人間は、差別意識を持ちやすく、自分を上において見がちである。愛によらない律法的な教えによる教育がそれに拍車をかける。そのような憐みに欠けた思いは、イエスの思いに反する思いであると気づき、自分の心に罪の傾向があることを知って注意してへりくだって過ごすのと、律法で正当化して自分は正しい、罪はないと他を貶めて生きるのとでは、行きつく先は大きく違ってくる。
イエスは、そのような社会の中で、見過ごすことなく、収税所にすわっていたレビ(マタイの福音書では「マタイ(主の賜物)」)に目を留められ、声をかけられたのであった。イエスから、「わたしについて来なさい。」と声をかけられたレビ(マタイ)は、「何もかも捨て、立ち上がってイエスに従った。」(ルカ 5:28)「何もかも捨て」「立ち上がって」と書かれている。この一文にマタイの喜びが伝わってくるようだ。このような世の中で、自分も生粋のユダヤ人で神の民であるのに同胞からは忌み嫌われ、ユダヤ社会にもローマ人側にも安心できる居場所がなく、もう何のために生きているのか、しょぼくれてすわっていたのかもしれない。「すわって」→「立ち上がって」イエスに出会ったマタイの見事な転身が表現されている。このような自分を見つけ、しかも「わたしについて来なさい。」と主に属する者として呼んでくださった。もはやヘブル人でありながら、ローマにも属しているように生きる者ではなく、主に属する者として生きてよいのだ。喜んで従うマタイの姿が浮かぶようだ。マタイは、自分を見る主のまなざしと「わたしについて来なさい。」という短い言葉に、何物にも代えがたい神の愛を感じとったのだろう。「わたしの羊はわたしの声を聞き分けます。またわたしは彼らを知っています。そして彼らはわたしについて来ます。」(ヨハネ 10:27)マタイはイエスの声を聞き、イエスについて言った。パリサイ人や律法学者たちは、主のことばを聞いても批判してついてくることはなかったが、マタイはたった一言でつき従ったのである。
主の食卓
大喜びのレビは、イエスをもてなそうと食事に招待した。イエスやイエスの弟子たちのほかに、取税人や罪人(特に悪い罪人〔マタイ 9:10, 詳訳〕重い罪を犯した人〔マルコ 2:15, 詳訳〕)を含む多くの人たちがやってきて、同じ食卓に着いた。「自分の家でイエスのために大ぶるまいをした〔盛大な宴会を催した(新共同訳、口語訳、詳訳)〕が、取税人たちや、ほかに大ぜいの人たちが食卓に着いていた。」(ルカ 5:29)
「すると、パリサイ人やその派の律法学者たちが、イエスの弟子たちに向かって、つぶやいて言った。『なぜ、あなたがたは、取税人や罪人どもといっしょに飲み食いするのですか。』」(ルカ 5:30)前回見たカペナウムの家で人々に混じって座っていたパリサイ人と律法学者たちがいたが、イエスが家を出てからも、ついてきていたのだろう。彼らの目には、先ほど、イエスが「罪を許す権威を主張し神と同等であるとした」場面を見たばかりであり、更に何をするか見ていようという思いが透けて見えるような行動である。
律法研究を積み重ねてきて、正統的であると自負している彼ら(パリサイ人やその派の律法学者たち)にしたら、イエスは道からそれる異端的存在にしか見られなかったのである。人間の言動には、その人の思い(何をどう見ているか)が現われる(マタイ 12:34)。神の民ユダヤ共同体において、「同じ食卓につく(食事を共にする)」という行為は、単に空腹を満たす行為ではなく、神との契約、信頼の中にある交わりを意味していた。同じ食卓につき食事を共にすることは、深い精神的な絆で結ばれていること(強い共同体意識)を表している極めて神聖な行為を意味していた。取税人や罪人どもは、パリサイ人やその派の律法学者たちにとっては、神に忌み嫌われている存在であり、そういう者たちと、食事を共にするということは、罪人と同じ仲間という意味に受け取られた。
イエスのもとに来た罪人たちというのは、誰の目にもわかりやすい罪を犯し、イエスの教えの中に神の愛を見、悔い改めようとする低い心でイエスのもとに来た人たちであったのだが、パリサイ人や律法学者たちは、視点が違うので(神基準の視点ではなく自分基準の視点)そういうことがわからなかった。彼らは、自分を高くしているので、罪の本質がわからないまま、律法に従って生きていたのである。
「なぜ、あなたがたは、取税人や罪人どもといっしょに…」とパリサイ人や律法学者たちは、イエスに言ったのでも大声で皆に言ったのでもなく、イエスの弟子たちに、しかもつぶやきとして言ったのである。イエスの弟子たちに恐れを抱かせ、引き離そうとするかのような行動である。イエスは、このようなつぶやきを放置なさらなかった。「そこで、イエスは答えて言われた。『医者を必要とするのは丈夫な者ではなく、病人です。わたしは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて、悔い改めさせるために来たのです。』」(ルカ 5:31,32)自分が正しいと思っている人は、そのことについてそれ以上他から学ぼうとはしない。人間が知ることには限りがあり、全部を知ることはできない。まして、全知全能の神については、全部を知ることは不可能である。「罪」を知るには、「神」を知ることなしにはできないのだが、「神」も「罪」もすでに知っているという「正しい」人たちには、もはや他の人から学ぼうとする姿勢はなく、イエスの教えは届かなかった。
神について学び直しなさい
マタイの福音書の記事には、31節(「…医者を必要とするのは丈夫な者ではなく、病人です。」)と32節(「わたしは正しい人を招くためではなく…」)の間に、「『わたしはあわれみは好むが、いけにえは好まない。』とはどういう意味か、行って学んで来なさい。」(マタイ 9:13)という言葉が入っている。ここで、イエスは、パリサイ人や律法学者たちにとって、なさないといけないことを明確に言われたのである。イエスの教えが届かないパリサイ人や律法学者たちを切り捨てず、何とかして救おうとされているイエスの姿がある。パリサイ人や律法学者たちには、疲れた人や重荷を負っている人たちに言われた「わたしから学びなさい」(マタイ 11:28)ではなく、「行って学んで来なさい。」と言われている。どこに行ってか。自分たちで研究している学者たちなので、「学び直してきなさい」ということである。
イエスは、ここで、ホセア書を引用された。「わたしは誠実を喜ぶが、いけにえは喜ばない。全焼のいけにえより、むしろ神を知ることを喜ぶ。」(ホセア 6:6)ホセアは、北イスラエルのサマリヤ陥落を目前に「背信のイスラエルは捨てられ、他の諸国民は招かれる」というメッセージを伝えた預言者である。国家全体に罪が蔓延し、神のさまざまな警告にもかかわらず、罪から離れようともせず、自分たちの道を突き進んでいくイスラエルに対し、ホセアは、「さあ、主に立ち返ろう。主は私たちを引き裂いたが、また、いやし、私たちを打ったが、また、包んでくださるからだ。主は二日の後、私たちを生き返らせ、三日目に私たちを立ち上がらせる。私たちは、御前に生きるのだ。私たちは、知ろう。主を知ることを切に追い求めよう。主は暁の光のように、確かに現われ、大雨のように、私たちのところに来、後の雨のように、地を潤される。」(ホセア 6:1-3)と主を知ることを勧めた。捕囚目前の民に向けた悔い改めへの勧告のことばであったのだが、イスラエルは、悔い改めることなく、捕囚を迎えた。時代が変わっても、罪の性質はかわらず、同じことを繰り返す。主を知り、悔い改めることだけが、滅びを逃れる道である。「行って学んで来なさい。」と言われた言葉を受け止めたパリサイ人や律法学者たちがいたのかどうか、マタイだけがこの指示を記している。
断食と祈りについて
「彼らはイエスに言った。『ヨハネの弟子たちは、よく断食をしており、祈りもしています。また、パリサイ人の弟子たちも同じなのに、あなたの弟子たちは食べたり飲んだりしています。』」(ルカ 5:33)これは、前節のパリサイ人たちの会話からの流れではないようで、マタイの福音書では「するとまた、ヨハネの弟子たちが、イエスのところに来てこう言った。」(マタイ 9:14)、マルコの福音書では「ヨハネの弟子たちとパリサイ人たちは断食をしていた。そして、イエスのもとに来て言った。」(マルコ 2:18)に続く言葉となっている。ここでの「彼ら」というのは、よく断食していたヨハネの弟子たちとパリサイ人たちであり、断食や祈りが敬虔の指標となっている人々の素朴な質問である。
そのような疑問にイエスは答えられた。「花婿がいっしょにいるのに、花婿につき添う友だちに断食させることが、あなたがたにできますか。しかし、やがてその時が来て、花婿が取り去られたら、その日には彼らは断食します。」(ルカ 5:34,35)とかく、人間は目に見える外面的なものにとらわれやすい。どれだけ長く断食できたか、どれだけ長く祈っているか、そういったものは誇りやすく(高ぶりにつながっていく)、すごい人という権威付けにつながりやすい。いつでもどこでも断食すればよいものではない(断食を否定するわけではなく)。
聖書に出てくる断食というのは、「ダイエットにもなるし、やってみるか」という軽いものではなく、食を断つ肉体的苦痛を通して、深い罪の自覚と恐れをもって神に近づく者の熱心な祈りと悔改めを表現していて、深い悲しみの中での悔い改めと神のあわれみを求める自発的な行為である。旧約時代の断食の時には、荒布をまとったり、灰をかぶったりしていたが、それは自分の無価値や愚かさを表現していたのである。罪を犯してしまった深い悲しみの中で、悔い改めの心を持って、神の御前に出て、赦しを請う姿である。花婿なるイエスが共にいる喜びに浸っている時に、断食を強いることができるか、断食は、花婿がいなくなったその時にするものであると、主は言われたのである。
祈りについては、「絶えず祈りなさい。」(Ⅰテサロニケ 5:17)とあるように、断食を伴わない普通の祈りというのは、神との交わりであり、常にいつも絶えず、形式にはよらず、である。こうしてイエスと会話し、交わっていること自体が祈りにつながっていく行為とも言えるのだが、この時、主は、祈りについては触れられなかった。(言ったところで、形式的な祈りを重視している相手とは、「祈り」の概念が異なるので、かみ合わなかったことだろう)
古いものと新しいもの
花婿のたとえに引き続き、イエスは一つのたとえを彼らに話された。着物についてとぶどう酒についてが語られているが「一つのたとえ」である。「だれも、新しい着物から布切れを引き裂いて、古い着物に継ぎをするようなことはしません。そんなことをすれば、その新しい着物を裂くことになるし、また新しいのを引き裂いた継ぎ切れも、古い物には合わないのです。また、だれも新しいぶどう酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすれば、新しいぶどう酒は皮袋を張り裂き、ぶどう酒は流れ出て、皮袋もだめになってしまいます。新しいぶどう酒は新しい皮袋に入れなければなりません。また、だれでも古いぶどう酒を飲んでから、新しい物を望みはしません。『古い物は良い。』と言うのです。」(ルカ 5:36-39)着物についてもぶどう酒についても、同じことが語られている。古いものと新しいものを一緒にしてはいけない、心の一新が必要だということを伝えようとされている。新しい着物を引き裂いて布切れを取り出して、古い着物に当てるようなことをすれば、布切れが浮いてしまい、古い着物には似合わず、また、裂いた新しい着物もダメになる。新しいぶどう酒は発酵力が強く、弾力性を失った古い革袋だとその力に耐えることができず裂けてしまい、ぶどう酒も革袋も失ってしまう。そのため、新しいぶどう酒は、新しい革袋に入れないといけない。また、古いぶどう酒にこだわりを持って「良い」としている人は、新しいものを欲しがらない。「また、だれでも古いぶどう酒を飲んでから、新しい物を望みはしません。『古い物は良い。』と言うのです。」は、ルカの福音書のみに書かれている。
この部分、マタイの福音書では「そうすれば、両方とも長もちする。」(マタイ 9:17〈新共同訳〉)で締めていて、マルコの福音書は「新しいぶどう酒は新しい皮袋に入れるのです。」(マルコ 2:22)のところで終わっている。イエスは、古いものを否定されたわけではない。律法という古くからの規範があって、神の民は形成された。その規範は、神の愛から出ていて、世界の模範となるべくよいものであった。神の意図をくみ取り、守っていれば、である。罪が蔓延し、罪や暴虐に満ちた世界がもう戻れないところまで来て、苦しみから贖うための神の介入が必要となり、古い不要なものは一新されないといけなくなる。そうした時、古い形は引き継ぎつつ、新しいものと入れ替える柔軟さが必要である。言い伝えなど、不要な古いものを残しつつ、無理やり継ぎはぎしながら、律法を遵守させようとして、イエスに刃を向けている律法の専門家たちに、心の一新をするよう、イエスはたとえを用いて、間接的に教えられたのである。
古いものに固執している人たちに、新しいものをいきなり当てようとすると、争いが起こり双方がだめになってしまう。聖書からではないような古くから引き継いだ言い伝えを信じて、そこから何らかの利益を得て良い思いを味わっている指導者たちに、直接的に新鮮な真理をぶつけると、激しい戦いとなる。地球は太陽の周りを回っていると言ったガリレオは、宗教裁判にかけられ異端とされた。免罪符の教えの誤りを直接論争しようとしたルターもまた、異端とされ除名排斥された。異言などを伴う聖霊の満たしの経験を受け入れない教派に、自己の聖霊体験を話すと除名とされていた時代がある。かたくなな心は、神のいのちを遠ざけてしまう(エペソ 4:18)。古いものと新しいもの両方を長持ちさせる知恵が必要だ。真理は滅ぶことはなく必ず残るものである。かつて、神がソドムとゴモラを滅ぼそうとされた時に、アブラムに「もしソドムで、わたしが五十人の正しい者を町の中に見つけたら、その人たちのために、その町全部を赦そう。」(創世記 18:26)と言われた。アブラムは心配になったのか、神にとりなし、五十人から四十五人、四十人、三十人、二十人、十人と数を減らしてもらったのだが、結局十人もいずに町は滅びた。すぐに滅ぼされないのは、どうにかして救われてほしいという神の愛による。
イエスという神自身を前にし、その言葉を直接聞いていても、かたくなな心のままに歩み続けた人たちによって、主イエスは十字架にかけられたが、それは、永遠の命に至る救いと永遠の滅びがはっきりと示されるためであった。握りしめていた時間が長ければ長いほど、不要なものだと気づくのは、時間がかかる。古いぶどう酒は古い革袋のまま、長持ちさせておいておくことも、時には必要で大事な時間である。「神のみこころは何か、すなわち、何が良いことで、神に受け入れられ、完全であるのかをわきまえ知るために、心の一新によって自分を変えなさい。」(ローマ 12:2)神のみこころに思いを置き、心を一新し、「愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制」の御霊の実を結びながら歩んでいくことを心がけてまいりましょう。

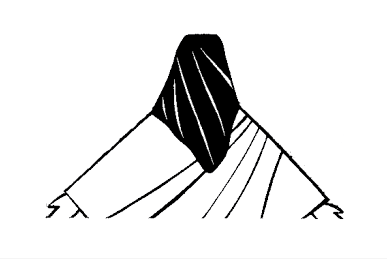

コメント