<– 前の記事:宗教改革の影響~広がって行く過程で
前回までは、ルターから派生した宗教改革が、ヨーロッパに広がっていった様子や、イギリスの国教会となったいきさつを見てきた。人間の罪も神の計画に組み込まれていて、全世界に福音が伝わることを含めた神の計画が進んでいくことが見て取れた。ルターの後の宗教改革が、キリストの愛に基づき、自分を捨て、キリストが与えられた一致を守るよう努力して歩むような改革であったならば、後代には麗しいキリスト教が伝わっていったかもしれないのだが、聖書の教えや神の愛によるみこころに重きを置かず、伝統や自分たちの信条から外れるものを「異端」とし排除していくような宗教と化したキリスト教は、もはや一致して歩むことはできなくなっていた。
士師の時代に神の民は、「そのころ、イスラエルには王がなく、めいめいが自分の目に正しいと見えることを行なっていた。」(士師 17:6, 21:25)という状態だった。モーセやヨシュア、カレブといった信仰者がいなくなり、その都度、さばきつかさが起こされて治められていったが、正しく治める者がいなくなると、人はめいめいが自分の目に正しいと見えることを行なっていった。神の民を正しく治める者は、王のような支配者ではなく、神のみこころを正しく示して、自分の羊たちを牧するキリストに似た者である。キリストの内にある者は、だんだんと聖められキリストの似姿に変えられていく。そういった人物は謙遜な性質を持ち、神の前に自分を語らず、神を恐れる人物である。王が、そのような人物であり続けたなら、よかったのだが、罪の重大さを意識せず、たれ流す王が支配すると、その国は、滅びへと向かっていく。
ヨーロッパのキリスト教社会が、王のような教皇によって統率されていたキリスト教から脱出した結果は、めいめいが自分の目に正しいと見えることを主張していった。マルチン・ルターは、徹底した罪の悔い改めと神性体験と綿密な聖書研究によって、民を救いに導こうとする愛から、改革を始めたのだったが、続いて改革を率いていった者たちはそうではなかったようで、いろいろな思惑が絡んで、プロテスタントは広がって行った。
ヨーロッパ情勢
イギリスでは、1534年にヘンリー8世によって、カトリック様式は受け継ぎながらも、カトリックから独立したイギリス国教会が成立した。スイスでは、1541年にジュネーブにてカルヴァンが神権政治による恐怖政治を始めていた。
ヨーロッパ諸国では、次第に国教が意識されるようになり、国ごとに独立した政治体制が取られるようになっていた。独立した国家としての結束力が強まるとともに、国王が絶対的な権力を握る「絶対王政」が誕生していた。
かつて、イスラエルが王制を敷くにあたり、神は、次のように言われていた。「あなたがたを治める王の権利はこうだ。王はあなたがたの息子をとり、彼らを自分の戦車や馬に乗せ、自分の戦車の前を走らせる。自分のために彼らを千人隊の長、五十人隊の長として、自分の耕地を耕させ、自分の刈り入れに従事させ、武具や、戦車の部品を作らせる。あなたがたの娘をとり、香料作りとし、料理女とし、パン焼き女とする。あなたがたの畑や、ぶどう畑や、オリーブ畑の良い所を取り上げて、自分の家来たちに与える。あなたがたの穀物とぶどうの十分の一を取り、それを自分の宦官や家来たちに与える。あなたがたの奴隷や、女奴隷、それに最もすぐれた若者や、ろばを取り、自分の仕事をさせる。あなたがたの羊の群れの十分の一を取り、あなたがたは王の奴隷となる。その日になって、あなたがたが、自分たちに選んだ王ゆえに、助けを求めて叫んでも、その日、主はあなたがたに答えてくださらない。」(Ⅰサムエル 8:11-18)
スペイン、フランス、イギリスといったヨーロッパの有力国の王家は、互いに婚姻関係を結び、王位継承をめぐって頻繁に争いを起こしていた。そして、スペインのハプスブルク家とフランスのブルボン家の対立が、宗教的な対立と相まって、近世ヨーロッパの形を作っていった。
フランスのユグノー戦争
フランスでは、カルヴァンの思想に影響を受けた新教徒が増加し、カトリック側からユグノー(乞食野郎の意味)と呼ばれていた。カトリックのプロテスタントの対立とフランス貴族間の党派争いが絡み合い、1562年に内戦となり、1598年までの36年間、休戦を挟んで8回の戦いを繰り返した。1562年1月、先代の王アンリ2世の妃で王の死後即位した息子フランソワ2世が幼かったために摂政となったカトリーヌ・ド・メディシスが、新教徒の勢力を利用しようと、新教徒の信仰の自由を認める勅令(オルレアン寛容勅令)を発した。これが発端となり、それに反発した旧教派のギーズ公の軍隊が1562年3月1日にシャンパーニュ地方のヴァッシーで日曜礼拝をしていた新教徒74名を虐殺した。この事件が契機となり、ユグノー戦争が勃発した。戦争が長引く中、摂政カトリーヌ・ド・メディシスは娘のマルグリットと新教派のブルボン家のアンリ(フランス南ア西部の小国ナバラ王)との結婚を画策して、両派の融和をはかろうとした。そのような中、時に起こっていたオランダでの独立戦争で新教のオランダを支援することを新教派の有力者コリニー提督が主張した。
そのオランダ独立戦争で、もしフランスがオランダ側につくと、スペインと戦うことになることを恐れたカトリーヌと旧教派は、1572年8月23日、アンリとマルグリットの結婚式にパリに集まっていたコリニー提督以下の新教徒を殺害した。それは一気にパリ市内での新教徒虐殺に拡大し(約4000人)、さらに地方にも波及し、全国で新教派多数が虐殺される(数万人)という惨状となった(サン・バルテルミの虐殺)。この戦争は、新教側のイギリスや旧教側のスペインなどが新旧両派の支援に介入したりもし、国際紛争の様相も呈する戦いとなった。1
新教派のブルボン家のアンリ(ナバラ王)は、サン・バルテルミの虐殺の後、宮廷にとらわれの身となり、カトリックに改宗するということで死を逃れたのだが、1576年に脱走し、新教徒の拠点ラ・ロシェルに入城し、新教徒に戻って指揮者となった。一方、宮廷の旧教派には摂政に不満な大貴族が新教徒側につくなど、内紛が生じた。旧教側は結束を図り、「カトリック同盟」が結成された。フランソワ2世とその弟のシャルル9世が死んだために王となった弟のアンリ3世(摂政カトリーヌ・ド・メディシスの息子)と、「カトリック同盟」の首領のギーズ公アンリと、新教派のブルボン家のアンリの3人のアンリが王権を巡って互いに戦った(三アンリの戦い)。この三人のアンリは幼なじみであったのだが、アンリ3世には後継者がなく、王位継承法で言えば最も血統が近いのがブルボン家のアンリだった。が、彼が新教徒であるということから、王位を巡って争うことになった。
このようなごたごたを通り、結果として1589年ナバラ王アンリがフランスにおいてカトリックを維持するという宣言書に署名してフランス王アンリ4世となり、新教徒の国王が誕生した。新教徒の国王を認めない「カトリック同盟」は別に国王を立て、フランスは二分されることになった。旧教派の内部でも貴族間の争いが続いていて、「カトリック同盟」は、新しい国王を選出しようとしたが適当な人物がいなかった。そこにスペイン王フェリペ2世が娘をフランス王に、と圧力をかけてきた。そうしたことにより、「カトリック同盟」も動きがとれなくなり、カトリック改宗を条件にアンリ4世を王として認めるしかないと考えるようになっていった。
このような情勢を見たアンリ4世とその側近たちは、国家の安定のために改宗を決意、1593年7月25日にサン・ドニ教会の大司教の前でカトリック信仰にはいることを誓った。その上でスペインと戦って破ったので、カトリック派も抵抗をやめてアンリ4世を国王と認めざるをえなくなった。
1594年3月、アンリ4世はパリに入城し、ノートルダム大聖堂で民衆から歓迎を受け、ようやく王権を巡る争いは、終結を迎えることとなった。翌年1595年1月、アンリ4世はスペイン軍との衝突を機に、スペインに宣戦布告した。この布告には、ユグノー戦争中の「カトリック同盟」に対する支援を口実としたスペインの介入を排除することによって、国内を一致させ、スペインと結ぶカトリック同盟を追い込むねらいがあった。6ヶ月にわたる戦争の結果、スペインと講和し、カトリック同盟の最後の指導者マルクール公もアンリ4世に帰順し、カトリック同盟の抵抗は終わった。
アンリ4世はカトリックに改宗表明していたのだが、新教徒側は当然ながらアンリ4世の改宗に反発していた。アンリ4世は、スペインとの戦争中に、その新教徒勢力と交渉を重ね、1598年4月13日、双方の妥協が成立してナントの王令を出し、カルヴァン派新教徒の信仰も認めた。こうしてフランスの宗教対立は終結した。
オランダ独立の八十年戦争
カトリック国であるスペイン領のネーデルラント(低地諸州、現在のオランダ)は中世以来、毛織物工業の盛んな商業地域であった。カルヴァンの予定説が利益の追求を神から与えられた使命と説いていたので、カルヴァン派が受け入れられ広がっていた。新教カルヴァン派は、カトリック側から軽蔑の意味を込めてヘーゼン(ゴイセン、乞食党)と呼ばれた。1568年にスペイン国王フェリペ2世がカトリックを強制したことでスペインからの独立に向けた戦いが始まった。この戦争は、休戦を挟みながら80年間続き、1648年のウェストファリア条約(80年戦争中の1618年にドイツで起こった三十年戦争の講和条約、オランダはこの三十年戦争で新教徒側を支援した)で、オランダは国際的に独立が認知され終結した。
神聖ローマ帝国の三十年戦争
神聖ローマ帝国では、神聖ローマ皇帝になったフェルディナント2世が、自分の領地を旧教に統一することを強制しようとした。これに対し1618年にベーメン(ボヘミア、現在のチェコ)の新教徒がプラハの市庁舎で皇帝の代理人を窓の外に投げ出すという事件が起こった(ベーメンの反乱)。この事件が発端となり、ドイツ内の新旧両派の対立が、全ドイツに広がっていった。当初は皇帝側の旧教軍が優勢であった。が、新教国のデンマーク、スウェーデンが参戦し、初めは旧教国側だったフランスが新教国スウェーデンを支持するに至り(オーストリア・スペインのハプスブルク家とフランスのブルボン家は覇権を巡り対立していたことにより、旧教国のフランスは新教国側についた)、もはや宗教戦争を超え、ヨーロッパの覇権を巡る大規模な国際紛争となった。この戦争は、火砲(鉄砲)の使用による集団戦という近代的なものになっていて、ルターの宗教改革から約100年後に起こった最後にして最大の宗教戦争となった。戦争の長期化がドイツを荒廃させ、フランスとスペインも戦争継続が困難となったため、1644年から講和交渉が始まり、1648年になってようやくウェストファリア条約で講和が成立した。
この30年戦争で、オランダとスイスが独立し、ドイツ諸侯も独立性が強化され、神聖ローマ皇帝は名目的存在となり、オーストリア・スペインを統治していたハプスブルク家は大打撃を受けた。フランスはアルザス地方を獲得し、大陸最強国となり、スウェーデンも北ドイツの諸要地を獲得し、強国となった。
三十年戦争の影響
三十年戦争は終結し、ウェストファリア条約で、フランス・スウェーデン・オランダとオーストリアのハプスブルク家間の講和が成立したのだが、スペインはこの条約には加わらず、フランスとの戦争を継続した(フランス・スペイン戦争)。1648年にフランス内部で政策への不満から反乱が起きた(フロンドの乱)。スペインはフランスの反国王派を支援するなどの介入を続けた。一方国王派は、スペインに対抗するためピューリタン革命で権力を握ったイギリスのジェントリ(身分は平民だが、地主として地域の名望家となり、州代表の議員になった「貴族より下で、農民よりは上の社会層」でピューリタンが多くいた)のクロムウェルと同盟した。
スペインではそのころフランスと国境を接するカタルーニャでの反乱が起こっており(1640~1652年)、どちらも疲弊し危機を迎えていた。1653年にフロンドの乱が鎮圧され、1658年にフランス軍がスペイン軍(イギリスから亡命してきた王党派も加わっていた)を破り(砂丘の戦い)、翌1659年、ピレネー条約を締結して講和した。カタルーニャでの反乱が起こった1640年に、スペインからポルトガルが独立した。
ピューリタン革命と名誉革命
イングランドは、三十年戦争では、1624年にフランスの呼びかけに応じて、資金を提供し、王室は財政困難に陥っていた。そういった中、アイルランドでは、1641年に旧教派が蜂起し、反乱を起こした。翌1642年にはイングランドでは絶対王政の国教会の信仰の強制に対して、ピューリタンの信仰の自由などを巡っての内戦が勃発した。(ピューリタニズムは16世紀にイングランドで生まれたプロテスタント運動であり、ピューリタンはイングランド国教会に残るローマ・カトリックの教えや慣習をすべて排除・浄化することで、国教会を敬虔な社会に変えることを目指していたカルヴァン派の新教徒である。)
1649年に議会の中心勢力であったジェントリが勝利し、王制が廃止され、共和制となりイングランド共和国が樹立された。スコットランドでは長老派(プレスビテリアン)というカルヴァン派の一派の新教徒が多く、イギリス国教会に反発し、内戦が起こっていた。共和制となったイングランドであったが、この共和制は約10年で終わりを告げた。
イングランドの内戦が、イングランド・スコットランド・アイルランドそれぞれの勝利した陣営によって三つ巴の戦争に発展し、イングランド共和国は安定しなかった。そのため、1660年に議会の権限の尊重を国王に約束させることを条件に、議会はチャールズ1世の子供でオランダに亡命していたチャールズの国王復帰に同意し、王政復古となった。チャールズ2世は議会を尊重することを約束して即位しながら、しばらくすると絶対王政の専制政治を復活させようと策動し、まずカトリック教会を復活させようとした(カトリック教徒であることは死の床に就くまで秘めていた)。2 そのため、国教会の立場に立つ議会との対立は再び深刻になっていった。
チャールズ2世には後継者がいず、王位後継者はチャールズ2世の弟でカトリック信者のジェームズ2世であった。国家安定のため、議会はカトリック信者の王位継承を認めないという法案を上程したのだが、法案は否決となった。議会は、チャールズ2世の死後はオランダ総督に嫁いだメアリかデンマーク王子に嫁いだアンがいずれも新教徒なので、どちらかを迎えればよいと思っていた。チャールズ2世は、1685年2月6日に心臓発作で世を去った。
1688年、議会は、ジェームズ2世を追放し(フランスに亡命)、オランダ(プロテスタントのカルヴァン派の国)からメアリとメアリの夫でオランダ総督のウィリアムを招聘し、二人は「権利の宣言」を受けいれて国王となり、さらに「権利の章典」を制定した(「権利の宣言」は13項目にわたり先王のジェームズ2世の政治を批判し、国民の権利と自由を確認したもので、ほぼ同一内容で議会で制定された文書が「権利の章典」)。これによって議会政治と国教会制度を柱とするイギリスの立憲君主政治が確立した。この国王の交替が、血を流さずに実現したことから、このクーデターは「名誉革命」と呼ばれている。
アメリカ大陸へ
三十年戦争が始まった2年後のイギリスでは、ジェームズ1世が王権を執っていた。ジェームズ1世は、イングランド国教会の典礼で用いるための聖書の標準訳を求め、聖書翻訳を命じ、英語訳聖書『欽定訳聖書』を定めた人物である。そのような功績を残しているジェームズ1世は、「主教なくして国王なし」と称して国教会の主教制度を国家の柱とし、国教会以外の宗派であるカトリック、プロテスタント(イングランドのピューリタンとスコットランドの長老派(プレスビテリアン))のいずれも否定していた。
ジェームズ1世は、カルバン派の教義を学ぶとともに、フランスの悪魔学者(ジャン・ボダン)の著作にも通じて、悪魔の力や魔女の術策にも大変詳しい「悪魔学者」であり、自身で「悪魔学」という著作を描いているほどであった。彼は、この世にはおびただしい魔女がおり、その魔女と相謀って王殺しを企む者が何人もいると妄想するようになった。そして、「イギリスがプロテスタント国になって宗教改革前よりも悪魔の攻撃が激しくなり、カトリック教徒らは、悪魔の手下である魔女や妖術師とと手をくんでプロテスタントを攻撃しようとしている。国王こそが魔女を弾圧し一掃すべきだ」と考えるようになった。3 カルヴァン派のピューリタンは、イギリス国教会のあり方に批判的であったため(同じカルヴァン派でも長老派は、イギリス国王を教会の首長とすることは認めるが主教制に代わり長老制度をとるべきであると主張していた)、悪魔の手先と考えられ弾圧の対象となった。
ジェームズ1世からの激しい弾圧から逃れるため、また、その頃、イギリスでの経済不振と伝染病の流行が起こっていたことから、多くのピューリタンを含む人々(ピューリタンは半数以下)が、植民地を建設しようとメイフラワー号に乗って、新大陸アメリカに渡った。
考察
マルチン・ルターが、民衆と神の愛による真理に立って、カトリックの誤り(民を滅びの道に向かわせている免罪符による救い)を正したいと議論を求めて始まった宗教改革であったが、聖書が翻訳され、印刷術が発展したこともあって、その改革に便乗し、聖職者でない者たちが独自の考えで派閥を作るようになっていった。マルチン・ルターは、礼拝形式を心から礼拝を捧げるようにと見直し、「私は一つのモデルを提供する・・・」とモデルとしてまとめてはいたが、あえて体系化したり統率したりせず、民衆に寄り添って、改革を進めていた。その改革から「愛」が除かれ、堕落していくのは、いつの時代も「罪」の本質を知らず、悔い改めることもせず、罪を無視して放置していった結果である。「悔い改めよ、天の御国が近づいたから」と宣教され、神と隣人への愛を説かれたイエスの教えから離れないように、歩んでいこう。
–> 次の記事:争いや動乱とともに広がるプロテスタント~個人が選択する信仰へ(2)
- 世界史の窓「ユグノー戦争」 ↩︎
- 世界史の窓「王政復古(イギリス)」 ↩︎
- 池上俊一『王様でたどるイギリス史』2017 岩波ジュニア新書 p.96-98 ↩︎

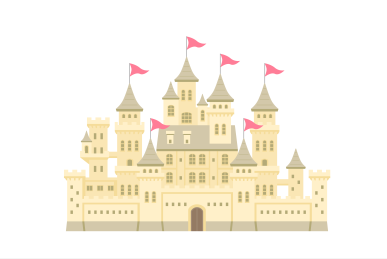


コメント