<– 前の記事:堕落した世に~神の計画による備え
前回は、マルチン・ルターが当時のローマ教会に異議を唱えるまで、どのように導かれて新生し、神に仕え、「95か条の論題」を掲げるに至ったかを見た。使徒たちの宣教によって信者が起こされ、迫害を経てローマの国教となった後、分裂を繰り返しつつ、キリスト教は世界に広まっていった。その過程で、ローマ教会の教皇の権威が強くなり、その下に枢機卿、大司教、司教、司祭、助祭といった階級ができていた。
- 枢機卿:教皇を補佐し、教皇選挙に参加する聖職者
- 大司教:教区の長、司祭の叙任、秘跡の執行、信徒の指導など、大司教区の管轄、司教や司祭の監督
- 司教:特定の教区の統括、司祭や助祭の監督
- 司祭:一般的に「神父」と呼ばれている。教区内での信徒の世話や宣教活動
- 助祭:司祭を補佐し、洗礼や結婚式などの儀式を執行
- 修道士:清貧・貞潔・従順の誓願を立て、修道院で共同生活を送りながら、祈りと奉仕の生活を送る男性信徒。修道司祭(修道会に所属し、修道院で生活しながら、司祭としての活動もする)になる者もいる
初代教皇は使徒ペテロとされているが、長い年月の中で教会の教えの中にも人間的な権力など聖書の教えではないものが入り込み、ピラミッド式に統率化され定着していた。マルチン・ルターの時代は、「罪の許し」を名目として、ローマ教会の名の下に免罪符が売り出され、民衆たちを悔い改めの道から遠ざけるような動きが盛んに行なわれるようになっていた。
この免罪符の概念は司祭であったマルチン・ルターの聖書理解、神認識とは相容れず、神を曲げてしまうものであり、民衆たちによくない実となって表れていたため、マルチン・ルターは、「95か条の論題」を一枚の紙に書き綴り、教会直属の上司のずっと上にあたるマインツ大司教(5億円の借金返済のために免罪符を発行した当の本人)宛に手紙をつけて送った。「このようなことについては、きちっとしていただくのがあなたの責任です」と。知らなかったとはいえ、ルターは、事の発端の張本人に向かって、「95か条の論題」を添えて手紙を送ったのであった。ここまでが前回の話であった。
95か条の論題
ここで、「95か条の論題」とはどのような内容であったかをざっと見ておこう。マルチン・ルターは、聖書を念入りに研究していたとはいえ、現代のような情報化社会ではない限られた情報下に生きた中世の司祭であり、中世カトリックの教えの影響を受けていることを踏まえて、見ていこう。
「95か条の論題」には、「贖宥の効力を明らかにするための討論〔95か条の論題〕」という題がついていて、マルチン・ルターは、真理への愛、そしてその真理を探求したいという熱情から、討論することを希望していた1。
【論題1】
「私たちの主であり、また教師であるイエス・キリストが『悔い改めのサクラメントを受けよ』※1と宣したとき、イエス・キリストは信じる者たちの生涯のすべてが悔い改めであることを願った。」
※1 「この時からイエスは宣教を開始し、『悔い改めなさい。天の御国が近づいたから』と言われた。」(マタイ 4:17)の原文は「悔い改めのサクラメントを受けよ」となっている引用である。2
悔い改めと赦し
カトリックでは、目に見えない神の恵みを、目に見える形(儀式)で表したものとして7つの秘跡(サクラメント)を定めていて、信者が神の恵みにあずかるための手段とされている。これは、解釈や実践が教派によってばらばらだったため、12世紀になってまとめて制定し継承されてきたものである。教会法(カノン法)は、キリスト教徒の信仰と生活の規範、教会の組織運営、活動に関する法体系である。使徒たちの教えや教会会議の決議、教皇の教令などから作られていったのだが、長い歴史の中でローマ法やゲルマン人の法などの影響を受けばらばらだったものを、12世紀にヨハンネス・グラティアヌスという法学者が、過去1000年間の教会法を網羅的に収録し、体系化した。この確立した教会法の中に7つの秘跡も定められた。
カトリックが定めている7つの秘跡というのは、洗礼、堅信、聖体、ゆるし、病者の塗油、叙階、婚姻である。
- 洗礼:聖霊の働きによって、受洗者の罪がすべて許され、神の子として新たに生まれる秘跡。(しるしとしての水。)
- 堅信:洗礼の恵みをより豊かに生きるために、洗礼を受けた人々に聖霊の賜物を与え、信仰を堅固たるものにする秘跡。堅信によって7つの賜物(敬畏・剛毅・孝愛・賢慮・知識・聡明・上智)が与えられる。
・敬畏:神の前で自分の小ささを知り、神への尊敬や畏れを持つ
・剛毅:神によって強められ、妥協することなく真理に従う
・孝愛:他人を慈しみ愛する心
・賢慮:物事を見通すすぐれた賢い考え
・知識:神に通じる深い知識
・聡明:物事の外面ではなく真理を見極める聡さ
・上智:神を知り、体験することで神からもたらされる知恵- 聖体:イエスの死と復活の記念を行うミサの中で、パンとぶどう酒がイエスのからだと血になるという信仰にもとづいて、それを霊的な糧として分かち合う。聖体の秘跡によって、すべての人々がキリストのうちに1つに結ばれる。
- ゆるし:神の愛に立ち返り回心する(告解)ことによって与えられる”神との和解”(罪のゆるし)の恵みの秘跡。→罪の償いへ
- 病者の塗油:臨終の床にある病人のゆるし/病の癒しの塗油
- 叙階:貞潔・清貧・従順の3つの誓願を立てて生涯を奉献する男子修道者にあたえられる秘跡。祈りと按手によって立てられ、使徒たちの後継者となる。
- 婚姻:互いに愛と忠実を尽くし、相手に仕え合いながら、神の創造のわざにあずかり、生まれてくる子どもを信仰のうちに育てる夫婦共同体としての使命をよりよく果たす。同意を交わし神への誓約をする。3
ルターが【論題1】で述べた「悔い改めのサクラメント(秘蹟)」というのは、ゆるしの秘跡のことである。ゆるしの秘跡は、「悔い改めの秘跡」「和解の秘跡」「告白の秘跡」「回心の秘跡」とも呼ばれるものであった。
聖書が教えているところの神の許しというものは、悔い改めたものにもたらされるものであり、頑として悔い改めない者(罪の中にあることを望む者)には許しがなくさばきが待ち受けている。罪がわからず、不動の神の愛という確かなものがなければ悔い改めることもできないような頑なな私たちのために、キリストはこの世に来られた。そして、十二使徒を選び、「悔い改めなさい。天の御国が近づいたから」と言われたキリストを信じ、罪を悔い改め神に立ち返るよう、宣教の使命を与えられた。福音を信じた者に与えられる神の贖い(よい知らせ、福音)を宣べ伝えられる使命であった(「十二人は出かけて行って、悔い改めさせるために宣教した。」(マルコ 6:12))。詳訳では「そこで彼らは出かけて行って、人は悔い改めなければならない〔すなわち、心を善いほうに変え、過去の罪を憎んで心底から行ないを改めなければならない〕ことを宣べ伝えた。」4とある。
ルターは、1番目の論題として、儀式で終わらない「生涯のすべてが悔い改め」であるという言い方で、外面的ではなく「心を善いほうに変え、過去の罪を憎んで心底から行ないを改める」ことが大切であることを伝えたのである。
【論題2】
「その言葉が(司祭が職務上行う告解と贖罪としての悔い改め、すなわち)サクラメントとしての悔い改めを指していると理解することはできない。」5
聖書を精査・研究したルターは、神の恩寵は儀式にはないことを知っていた。堕落した教えの中であっても、どこの教派教団にいたとしても、情報化社会で、誰でも聖書や聖書の教えを入手できる今、神を愛し聖書を神からの大切なものとして読むならば、そこにたどり着ける内容である。
【論題3】
「しかし、それはただ内的な悔い改めだけを意図しているとは言えないし、それどころか内的な悔い改めが〔内的なものに対して〕外的なものである肉をさまざまな方法で殺すという帰路に向かわないなら、虚しいものになってしまう。」6
ちょっとわかりにくい表現であるが、「キリストが言われた悔い改めは、単に内的な悔い改めだけをさしてはいない。悔い改めは、むしろ、外側で働いて肉を様々な方法で殺していかないなら、虚しく終わる。」と言っている。聖書をつらぬく教え「悔い改めよ」の真意を思い起こし、論題の意味を理解してもらおうと、ルターが配慮をもって細かに説明していることがわかる。
聖書には、罪の性質―外側の行動に罪の実が現れるまでには、段階がある―ということが記されている。
「だれでも情欲をいだいて女を見る者は、すでに心の中で姦淫を犯したのです。もし、右の目が、あなたをつまずかせるなら、えぐり出して、捨ててしまいなさい。からだの一部を失っても、からだ全体ゲヘナに投げ込まれるよりは、よいからです。もし、右の手があなたをつまずかせるなら、切って、捨ててしまいなさい。からだの一部を失っても、からだ全体ゲヘナに落ちるよりは、よいからです。」(マタイ 5:28-30)
「兄弟を憎む者はみな、人殺しです。いうまでもなく、だれでも人を殺す者のうちに、永遠のいのちがとどまっていることはないのです。」(Ⅰヨハネ 3:15)
ルターはすべての人間が持つ原罪を理解していて、罪というものは、肉の行動に移る前の小さな芽のうちに摘み取っておかないならば、最終的に罪の奴隷になり、虚しく終わっていくということを知っていた。原罪を持つ人間であるからこそ、思いの内に起こる小さな芽のうちに、さまざまな方法で殺して罪を膨らませない努力が必要である。それは、生涯にわたる罪との戦いである。
【論題4】
「〔今ある〕自己を憎むということ(それは真の内的な悔い改めではあるが)が続くかぎり、つまり天の国に入る時まで、罰(poena「罰、刑罰、ペナルティ」)は残る。」7
キリストを信じて恵みに入れてもらった現代のプロテスタントの流れを組む信仰者からすると、生きている限り「罰」が残るのか?と違和感を覚えるところである。ここで、マルチン・ルターが言っている「罰」の捉え方を知り、何を述べているのかを必要がある。
前回見たところでは、マルチン・ルターは、教育において厳格な両親の下で育った影響もあり、厳しいまでに正しさを求める神の義に恐怖を覚え、押しつぶされそうになるような繊細な心の持ち主であった。つまり罪への罰をとても恐れていた。その性質があったからこそ真剣に神を求め、献身し、新生するに至っていた。
その頃の中世の教会が命じているのは、神の前に自分が罪だと思うものを行ってしまったならば、それを一つ一つ取り上げて、そして思いつく限り残らず、懺悔を聞いてくれる他の神父の前で懺悔、告解をしなければならないということだった。修道士時代のマルチン・ルターは懺悔・告解を頻繁にしていて、神父のところへ行って懺悔をして、自分の部屋に戻ってくる―あまり広くない修道院の中を歩いて戻る途中でまた罪を思い出して、急いでとって返して、「もう一つございました」と言って懺悔告白をするぐらいで、他の人からは、「そんなに神経質にならなくてもいいじゃないか」と言われるぐらい真剣に自分の罪ということを考えた修道士だったそうである。8
聖書を見てみよう。「人はそれぞれ自分の欲に引かれ、おびき寄せられて、誘惑されるのです。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。」(ヤコブ 1:15)とあるが、神の恵みの中に入れられたものの、肉を持つ私たち人間は、生きている限り、肉の欲との戦いがある。欲をはらませることがないうように、ペテロは、「旅人であり寄留者であるあなたがたは、たましいに戦いをいどむ肉の欲を遠ざけなさい。」(Ⅰペテロ 2:11)と教えている。パウロは、朽ちない冠を受けるために「私は自分のからだを打ちたたいて従わせます。それは、私がほかの人に宣べ伝えておきながら、自分自身が失格者になるようなことのないためです。」(Ⅰコリント 9:27)と言っている。「思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種を蒔けば、その刈り取りもすることになります。自分の肉のために蒔く者は、肉から滅びを刈り取り、御霊のために蒔く者は、御霊から永遠のいのちを刈り取るのです。」(ガラテヤ 6:7,8)とあるように、神を侮り贖罪の心も持たず罪を犯し続けるならば、滅びという「罰」を刈り取ることになるが、罪を憎んで神を愛していくならば、御霊の導きのまま永遠のいのちという「報酬」をいただける。「罪から来る報酬は死です。しかし、神の下さる賜物は、私たちの主キリスト・イエスにある永遠のいのちです。」(ローマ 6:23)
ここに、「罪から来る報酬は死」とあるが、罪の刈り取りの中、それでも罪を増し加えていく(悔い改めを拒否し神に反逆していく)者たちを神はどのようにされるだろうか。イエスは言われている。「良い実を結ばない木は、みな切り倒されて、火に投げ込まれます。こういうわけで、あなたがたは、実によって彼らを見分けることができるのです。わたしに向かって、『主よ、主よ。』と言う者がみな天の御国にはいるのではなく、天におられるわたしの父のみこころを行なう者がはいるのです。その日には、大ぜいの者がわたしに言うでしょう。『主よ、主よ。私たちはあなたの名によって預言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇蹟をたくさん行なったではありませんか。』しかし、その時、わたしは彼らにこう宣告します。『わたしはあなたがたを全然知らない。不法をなす者ども。わたしから離れて行け。』」(マタイ 7:19-23)ここに、キリスト教信者と未信者の区別はない。むしろ、外面上は信者の者に特別言われているところである。
生きていて肉がある限り、肉の欲(神ではなく己を喜ばせようとする欲)は起こってくるが、欲に負け失敗を繰り返しても、罪の刈り取りの苦しみの中、ダビデのように罪を認め、責任転嫁せず、神を信じて結果を神にゆだねる信仰があるならば(罪は犯してしまうが、罪をも神に委ねて苦しみの中も神と共に歩んでいくならば)、赦しの神の愛が周囲にも流れていく。免罪符一つで罪が帳消しになるわけではない。しっかりと犯した罪を悔い改め、天の国に入る時まで悔い改めの心を持ち続けることの大切さをルターは言いたかったのではなかろうか。主への信仰を口で表明すれば、後は免罪符で罪が帳消しとなるので、何をしてもよいというのではないというのが、「天の国に入る時まで、罰は残る。」の意味するところではないだろうか。「キリストを信じたから自分にはもう罪はない」という信者がいるならば、肉の性質を無視してキリストを現代の免罪符のようにしてはいけないと忠告したい。
ダビデの悔い改め
ダビデはいくつかの罪(姦淫の結果のウリヤ殺人までも)を犯したことが聖書に描かれているが、神はダビデの信仰を喜ばれ、キリストに至る血筋に選ばれた。ここで、ダビデの悔い改めの一例を見てみよう。ダビデが王の座についた後、再び主の怒りが、イスラエルに向かって燃え上がったことがあった(Ⅱサムエル24:1)。イスラエルの民が何をしての怒りなのかは書かれていないのだが、今までいくつか考察されてきたところによると、神が油注がれた王に対する尊敬の念の欠如といった民の態度による罪(アブシャロムの反乱時やその後シェバというよこしまな者の言葉に耳を傾け、民はダビデについていこうとしなかった)、神の民が王国となったことを誇る心の罪などがあげられている。が、どれも想像の域のことであり、実際のところは不明である。しかし、民全体に及んでいるような主を怒らせるような何らかの罪があったようだ。王国として繰り返し起こるペリシテ人との戦いに勝利していく中で、神の存在が薄れてきて、自分たちを誇るようになっていたような継続した罪が積もり積もってのことだとしたら、何があったかがはっきり書かれていないこともうなずける。そのようなものは、徐々に社会全体に蔓延して、神から離れていることにも気づかないような罪である。
主の怒りが、イスラエルに向かって燃え上がっている中、ダビデは主の許しの中でサタンの誘いにのり、イスラエルの民の人口を数えた。(「主は『さあ、イスラエルとユダの人口を数えよ。』と言って、ダビデを動かして彼らに向かわせた。」(Ⅱサムエル24:1)この文の前の「さて、再び主の怒りが、イスラエルに向かって燃え上がった。」(Ⅱサムエル24:1)の「主の怒り」の「主」は太文字の主だが、ここにある「主」は太文字ではない。「ここに、サタンがイスラエルに逆らって立ち、ダビデを誘い込んで、イスラエルの人口を数えさせた。」(Ⅱ歴代誌 21:1))民の期待に応えるべく、兵力を増強し、王国の統率を自らしようとしたのだろうか、今までのダビデであったら、どんな時も、神に信頼し従っていて、兵力を数えるようなことはしなかっただろう。たとえ主の使いに「さあ、イスラエルとユダの人口を数えよ。」と言われても、「イスラエルの国は人数によりません。神である主が共におられる以上、数など何の意味がございましょうか。」というような神への熱い愛が見られた。
民数記26章では、カナンに入る前に、モーセとアロンに神が命じてイスラエルの諸部族毎の軍務につくことのできる者すべての人口を数えさせていて、人口調査自体が悪いことではない。人口調査をするダビデの心に問題があった。指示を受けた家来ヨアブが、「主が、御民を今より百倍も増してくださいますように。・・・なぜ、わが君はこんなことを要求なさるのですか。なぜ、イスラエルに対し罪過ある者となられるのですか。」(Ⅱサムエル24:3, Ⅱ歴代誌 21:3)と言っているのだが、側近にそのように思わせたような何かがダビデにあったようだ。ダビデは、ヨアブと将校たちを説き伏せて、半ば無理やり人口調査を実行した。調査は九か月と二十日もかかって終えたのだが(Ⅱサムエル24:8)、この命令で、王は神のみこころをそこない、神はイスラエルを打たれた(Ⅱ歴代誌 21:7)。ここで、ようやくダビデは良心のとがめを感じ、主に「私は、このようなことをして、大きな罪を犯しました。」と告白した。この後、ダビデは主のあわれみにすがり、主の裁きに委ねた。主はイスラエルに疫病を下されたので、イスラエルのうち七万の人が倒れた(Ⅱ歴代誌 21:14)。民が打たれていく様子を見て、ダビデは主に懇願したのであった。「民を数えよと命じたのは私ではありませんか。罪を犯したのは、はなはだしい悪を行なったのは、この私です。この羊の群れがいったい何をしたというのでしょう。わが神、主よ。どうか、あなたの御手を、私と私の一家に下してください。あなたの民は、疫病に渡さないでください。」(Ⅱ歴代誌 21:17)と。民を支配するのではなく、民を牧する良い牧者の心が見られる。この後、ダビデは、「主のために祭壇を築き、全焼のいけにえと和解のいけにえとをささげた。主が、この国の祈りに心を動かされたので、神罰はイスラエルに及ばないようになった。」(Ⅱサムエル24:25)
「民を数えよと命じたのは私ではありませんか。罪を犯したのは、はなはだしい悪を行なったのは、この私です。この羊の群れがいったい何をしたというのでしょう。」とダビデは言っているが、「主の怒りが、イスラエルに向かって燃え上がった」とイスラエル全体の罪が先立っていたのである。しかし、ダビデは、「民を統率するには、国の力を見せる必要があった」などという言い訳も、「このような民をまとめるには数を知る必要があった」などという責任転嫁も、「他では普通にやっていることではないか、このぐらいよいではないか」と逆ギレしたりはしなかった。ダビデは正しいお方である神(民を打たれていることは神の過ちではない)の御前に、民の前面に立って、懇願したのである。悪いのは、この私だと。
このことに、主は心を動かされ、全焼のいけにえを受け入れられ、神罰は止んだ。ダビデの民を思う心からの叫び、民の苦しみの中での祈りに、主は心を動かされ、王様を筆頭に神中心に落ち着きを取り戻した。神を愛し、人を愛していくと、罪の存在は耐えられなくなり(その過程で神の御手が及ぶこともあるが、結果は神の聖さに近づけられることへの喜びに変わるものである)、神の御前で悔い改め、神の赦しが下るのだが、そのような愛による神との関係性ができていると、罪を持ち続けることは耐えられなくなっていく。「キリスト・イエスにあっては、割礼を受ける受けないは大事なことではなく、愛によって働く信仰だけが大事なのです。」(ガラテヤ 5:6)
罪を赦す権威
【論題5】
「教皇は、自らが科した罰、あるいは教会法に従って科された罰以外には、他のどのような罰の赦しを宣言することも、あるいは赦すこともできない。」9
ここで、ルターは、当時のキリスト教世界の最高権力者の教皇について、語り出している。教皇という地位にあろうが、人間にすぎない者が神に対する罪を赦すことはできない。人に対する罪であれば、教皇は教会法に従って許しを宣言することはできるだろうと。
イエスは、地上で罪を赦す権威を持っておられた。「神おひとりのほか、だれが罪を赦すことができよう。」と律法学者が言っている中で、イエスは、「人の子が地上で罪を赦す権威を持っていることを、あなたがたに知らせるために。」と言って中風の人を癒された(マタイ 9:6, マルコ 2:10, ルカ 5:24)。また、ペテロに「あなたはペテロ〔男性名詞 
 大岩石〕です。わたしはこの岩〔女性名詞
大岩石〕です。わたしはこの岩〔女性名詞 
 ジブラルタル※のような巨岩〕の上にわたしの教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。わたしは、あなたに天の御国のかぎを上げます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。」(マタイ 16:18,19、〔〕内は詳訳聖書10)と言われた。カトリックでは、この個所を基にペテロを教会の岩とし、教皇はペテロの後継者だという理由で、権威付けされてきたようだが、ここでのつないだり解いたりする権威は、一個人ではなく、わたし(イエス)の教会に与えられた権威である(〔〕の説明による見解である)。教会ならばどの教会でもということではなく、イエスの教えに従い真理に打ち立てられた一枚岩の教会のことである。「聖霊を受けなさい。あなたがたがだれかの罪を赦すなら、その人の罪は赦され、あなたがたがだれかの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります。」(ヨハネ 20:22,23)聖霊とともに、真理の中を歩むならば、教会は真理という岩の上に立つ一枚岩となり、聖霊によって罪を赦すことも、罪を残すことも可能であるが、そうでないならば、不可能である。ルターは、告解という儀式によって与えられる許しについて、疑問を持って提言したようだ。
ジブラルタル※のような巨岩〕の上にわたしの教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。わたしは、あなたに天の御国のかぎを上げます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。」(マタイ 16:18,19、〔〕内は詳訳聖書10)と言われた。カトリックでは、この個所を基にペテロを教会の岩とし、教皇はペテロの後継者だという理由で、権威付けされてきたようだが、ここでのつないだり解いたりする権威は、一個人ではなく、わたし(イエス)の教会に与えられた権威である(〔〕の説明による見解である)。教会ならばどの教会でもということではなく、イエスの教えに従い真理に打ち立てられた一枚岩の教会のことである。「聖霊を受けなさい。あなたがたがだれかの罪を赦すなら、その人の罪は赦され、あなたがたがだれかの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります。」(ヨハネ 20:22,23)聖霊とともに、真理の中を歩むならば、教会は真理という岩の上に立つ一枚岩となり、聖霊によって罪を赦すことも、罪を残すことも可能であるが、そうでないならば、不可能である。ルターは、告解という儀式によって与えられる許しについて、疑問を持って提言したようだ。
※ ヨーロッパのイベリア半島南端にあたるイギリス領ジブラルタルにある、岬をなす一枚岩の石灰岩
【論題6】
【論題6】
「教皇は、神によって罪が許されたと宣言すること、あるいはそれを承認すること以外には、どのような罪も赦すことはできない。また、自らに委ねられている責務に関する訴訟事項を赦すこと以外には(それゆえ、このような事項が見過ごされるなら、罪はなお残ることになる)、他のどのような罪も赦すことはできない。」罪は、culpa「過ち」「責任」「罪」などを意味する言葉 11
当時の教会法に則って、教皇が人を裁く権威や任務について、ルターは教皇への尊敬の念と共に認めている。それは、【論題5】で見たように主イエスから教会に与えられた使命でもあるからだ。それを、神に委ねられている正しい訴訟をせずに見過ごされるならば、「罪はなお残ることになる」ということを指摘している。誰の罪か、正しい判断で間違いを正されなかった(訴訟による「刑罰で悔い改めたかもしれない)人の罪、なすべきことをなさずに見過ごした裁くべき側の罪の双方が残ることになるのである。
「もし、あなたが自分をユダヤ人ととなえ、律法を持つことに安んじ、神を誇り、みこころを知り、なすべきことが何であるかを律法に教えられてわきまえ、また、知識と真理の具体的な形として律法を持っているため、盲人の案内人、やみの中にいる者の光、愚かな者の導き手、幼子の教師だと自任しているのなら、どうして、人を教えながら、自分自身を教えないのですか。盗むなと説きながら、自分は盗むのですか。姦淫するなと言いながら、自分は姦淫するのですか。偶像を忌みきらいながら、自分は神殿の物をかすめるのですか。律法を誇りとしているあなたが、どうして律法に違反して、神を侮るのですか。これは、『神の名は、あなたがたのゆえに、異邦人の中でけがされている。』と書いてあるとおりです。」(ローマ 2:17-24)
「なすべき正しいことを知っていながら行なわないなら、それはその人の罪です。」(ヤコブ 4:17)
このような教皇への指摘をルターができたのは、教皇や大司教の地位にいる上司を、神にある者として信頼してのことだった。気づいていないのならば、気づいてほしい、ここで聖書の教えとかけ離れたことが行われているということを。このようなことは、信頼があったから言えることであった。ルターは、よもや、大司教張本人の借金のために、教皇と結託して免罪符が発行されたとは夢にも思っていなかったのであった。
【論題7】
「神は、人間がどのようなことにおいても神の代理人である司祭に、謙虚に従っていないなら、誰の罪も赦すことはない。」12
次に、司祭の使命が述べられている。ルターは司祭であったが、司祭とは、聖書をよく研究し、民が神に過ちを犯すことがないよう、その神の教えを教える役割を担った者であると認識していた。そういう意味で神の代理人であるという使命を謙虚に受け止めていた。指導される民(人間)が、司祭の教え(聖書の教え)に謙虚に従わず、免罪符という紙切れ一枚で罪は許されたから、後は何をしてもいいのだという態度で、司祭の忠告を退けるならば、罪は残るということを言いたかったようだ。目の前に、救いを必要としている民がいるのに、免罪符が阻んでいる、ルターには、その妨げを取り除かなければ果たせない使命を担っているという自覚があった。
【論題8】
「教会法が定める悔い改めは、生きている人間にのみ関わるものであり、死者については何も課していない。」13
免罪符の説教者は、死んだ両親の罪や煉獄での炎の苦しみ、民衆の罪を述べ聞かせ、「今、金貨1枚を箱に入れれば、これからの罪も含めてすべて帳消しになる」というような内容を、心に訴えかけるように説教していたので、ルターは、死者の罪を赦すことの誤りについても、述べた。
根本となる悔い改めと赦しによる救いについて、それに基づく教皇や司祭の職務について、また、死者の救いについて、95か条として細かく書き送ったのである。「悔い改めと赦しによる救い、教皇や司祭の職務、死者の救いについて、誤ったことが教えられている。何とかしてほしい」と数行で済みそうだが、真剣だからこそ、このように多くの枚数を割いて説明したのであった。このおそらく分厚くなった手紙を、受け取った側はきちんと見たであろうか。正しく歩んでいるならば、丁寧に見ただろうが、出した相手は指示した張本人たちである。聖書的かどうかというのはどうでもよく、対策に試案したことだろう。
【論題9】になると、教皇は神にある正しいお方だ、というルターの認識と、今起こっている問題とのはざまで、調整を試みている様子が伺える。
【論題9】
「〔教会法によれば〕教皇は自らの決定において死と必然についての条項を除外するので、聖霊は教皇を通して私たちに正しい対応をしている。」14
【論題10】【論題11】では、教会全体のカルト化ともいえる状態についての、教師たちへの非難勧告となっている。
【論題10】
「教会法による悔い改めは煉獄でも適用できる、と死を迎えようとしている者に言う司祭は、無学であり、害を及ぼす者である。」
【論題11】
「教会法が定める〔この世の〕罰を、煉獄における罰に変えているあの毒麦は、司祭たちが眠ってしまっているあいだに蒔かれたのだろう。」15
【論題24】では、偽りの教えがもたらしている影響が述べられている。
【論題24】
「以上のような理由から、多くの人が節操のない仕方で、荘厳であるだけの約束が与えられることで、罰から解放されているかのように騙されてしまっている。」16
【論題25】では、教皇の権限はそれに続く他の役職も個別に持つことになるので、教会法に則って過ちをただしてほしいと訴えている。
【論題25】
「教皇が煉獄に対してもっている権限と同じものを、その司教も、皇位の聖職者も、それぞれの司教区、聖堂区に対して個別的にもっている。」17
【論題27】【論題28】【論題32】【論題33】【論題35】では、カルト化ともいえる免罪符の蔓延への警告が書かれている。
【論題27】
「お金が箱の中に投げ入れられ、そのお金がチャリンと音を立てるや否や、魂が飛び立つ〔とともに煉獄を去る〕と教える人たちは、〔神の教えではなく〕人間的な教えを宣べ伝えている。」
【論題28】
「お金が箱の中に投げ入れられ、そのお金がチャリンと音を立てることで、利益と貪りは確かに増し加わるに違いないが、教会のとりなしはただ神の御心に基づいている。」
【論題32】
「贖宥の文書によって自らの救いが確実になると信じる人がいるなら、その人はそれを教える教師とともに永遠に断罪されるだろう。」
【論題33】
「人間と神を和解させる教皇の贖宥は計り知れないほど高価な恩恵である、と主張する人がいるなら、その人は厳しく警戒されるべきである。」
【論題35】
「魂を買い戻すことでき〔人を煉獄から連れ戻せ〕ると考え、告解の証明書をお金で買ったり、痛悔※は必要ないと考えたりする人は、非キリスト教的なことを教えている。」18
※ 「痛悔」は、罪を心から悔い改めることで、カトリック教会や正教会では、罪を司祭に告白し、神の許しを請う「ゆるしの秘跡」または「痛悔機密」の一部として重要な概念となっている。
【論題36】【論題37】では、本当の悔い改めについて、述べられている。
【論題36】
「真に懺悔したキリスト者であれば、贖宥の証明書なしでも、その人が当然得ることができるはずの罪と罪過からの十分な赦しをもつ。」
【論題37】
「〔このようにして〕真のキリスト者になった者であれば、生きている時も、死んでも、贖宥の証明書なしに、神から与えられるキリストとその教会の宝に与るあずかることができる。」19
【論題38】では、改めて教皇の権威を認め重要視するようにと語っている。
【論題38】
「しかし、教皇の赦しとそれへの関わりを軽視するようなことがあってはならない。〔これまで述べてきたように〕それは神の赦しの宣言なのである。」20
この後もこのようなことがとくとくと言葉を変えながら、書かれている。
【論題40】
「真実の懺悔は罰を求めるし、それを愛しもする。しかし、寛大すぎる贖宥は罰を緩和し、それを嫌悪するようになる。少なくとも、そのような機会を提供してしまう。」
【論題42】
「贖宥をお金で買うことは憐みの行いと何らかの意味で同じものだと認められているという考えは教皇の意見ではない、とキリスト者は教えられるべきである。」21
そして、【論題95】の最後は、次のように締めくくられている。
【論題95】
「キリスト者は、〔これまで見てきたような〕平安の保証よりも、むしろいくつもの困難をくぐり抜けて天の国に入ることを固く信じなければならない。」22
「95か条の論題」において、ルターは、民を迷いの道に引き連れていく悪しき免罪符(贖宥状)での罪の許しの宣言を、よほど何とかしたかったようだ。民に悪しき教えが蔓延して、教えに耳を貸そうとしない人が出てきていたからである。
ルターは、1517年にこの95か条の論題を提出し、このことが大きな波紋を呼びヨーロッパ全土を巻き込む宗教改革が勃発していった。聖書1520年にルターは、「キリスト教会の改善について」「教会のバビロン捕囚について」「キリスト者の自由について」という題の文書を出している。ルターは、教会の腐敗を批判し、独自の宗教改革運動を展開したことに対する処罰として、1521年に免罪符を発行したレオ10世(217代教皇)が治めるローマ・カトリック教会から破門され、現在でも、ルターの破門は解かれないままとなって、カトリックとプロテスタントという流れになっている。かつて、一つとして置かれた神の民が、北イスラエルと南ユダに分かれたように、一つであったキリスト教徒が分かれていった。そこには、修復不可能な人間の罪があり、分かれたところで、反目せずに互いのすぐれた部分を認め、神に仕えていくという神の愛に生きる道が残されている。キリストが再臨される時、神の教会はどのようになっているのだろうか。
–> 次の記事:宗教改革時代へ~罪との闘い
- 『宗教改革三大文書』深井智朗訳 講談社学術文庫 p11, p12 ↩︎
- 同 p13, p41 ↩︎
- https://pweb.cc.sophia.ac.jp/j-puthen/page031.html 参考 ↩︎
- 詳訳聖書-新約-, いのちのことば社発行 P98 ↩︎
- 『宗教改革三大文書』深井智朗訳 講談社学術文庫 p13 ↩︎
- 同 p13 ↩︎
- 同 p14, p41 ↩︎
- 徳善義和『マルチン・ルター 生涯と信仰』教文館 p40 ↩︎
- 『宗教改革三大文書』深井智朗訳 講談社学術文庫 p14 ↩︎
- 詳訳聖書-新約-, いのちのことば社発行 P43 ↩︎
- 『宗教改革三大文書』深井智朗訳 講談社学術文庫 p14, p41 ↩︎
- 同 p15 ↩︎
- 同 p15 ↩︎
- 同 p15 ↩︎
- 同 p15-16 ↩︎
- 同 p19 ↩︎
- 同 p19 ↩︎
- 同 p21-23 ↩︎
- 同 p23 ↩︎
- 同 p24 ↩︎
- 同 p24-25 ↩︎
- 同 p41 ↩︎

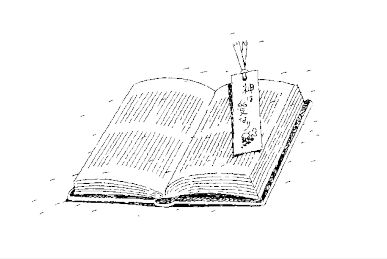


コメント