<– 前の記事:偽りとの闘い~著作に込めたルターの思い
対抗宗教政策
さて、ルターの宗教改革は、キリスト教世界に多くの影響をもたらした。ルターを破門したローマ・カトリック教会は、プロテスタント(新教)の運動が活発になり拡大していくとともに、強い危機感を持った。マルチン・ルターは新しい教会を作ろうとしていたわけではなく、カトリック教会の自己改革をしきりに呼びかけて公会議の開催をも要求していた。しかし、公会議を主張する側と公会議を危険視した教皇側の力関係もあり、公会議の開催は過度に慎重になっていた。そのような中、カトリック教会内部が停滞し、宗教改革運動が高まってきたことに危機感を持ち、緊急性を認識した教皇パウロ3世(220代教皇)は神聖ローマ皇帝カール5世からの協力の申し出もあって公会議の開催を決断した。
こうして、1545年にトリエント(イタリア北部)にて公会議が開かれた。この会議は、プロテスタントとの決定的な分裂を回避し、妥協点を見出し、融和を図る目的もあって召集されたのだが、プロテスタント側が出席を拒否したため、プロテスタントを糾弾する色彩が強まり、対抗宗教政策を打ち出すこととなった。そんなこんなで結局この公会議は、カトリック教会が自らの教義を再確認することでかえってプロテスタント側の主張との違いを際立たせることとなった。最終的には、会議の主な議題は、「カトリック教会の教義の再確認とそれに伴うプロテスタント側の主張の排斥」と「教会の自己改革」に絞られていったのであった。
1545年(ルターが死去する1年前)、教皇パウロ3世(220代教皇)によって始められたトリエント公会議は、1563年までの18年間、三会期にわたって開催された。一期目は、1545年から1547年まで続けられたが、シュマルカルデン戦争(1546年~1547年にカトリック教会を支持する皇帝側(カール5世)とシュマルカルデン同盟を結んだプロテスタント側で起こった宗教戦争)が激化したことにより開催地を一時ボローニャに移し、やがて伝染病(ペスト)の流行もあり中断した。二期目は、1551年に教皇ユリウス3世(221代教皇)によって始められたのだが、翌年の1552年にルター派であったザクセン選帝侯モーリッツが皇帝カール5世に勝利したことから会議の安全が危惧されて中断した。10年間の中断をはさみ(1559年には『禁書目録』が定められ、思想統制が強められた)、1562年に教皇ピウス4世(224代教皇)の代になって、第三会期が開始された。この会期で、カトリック教会の改革や秘跡や聖伝の扱いなどが討議され、1563年にようやく予定されたほとんどの議題を討議して公会議は終了した。
トリエント公会議の出席者の全体の3分の2はイタリア出身であった。なお、スペインからはサラマンカ学派(高い学問水準を保っていたサラマンカ大学のドミニコ会士の教授らによって創設されたドミニコ会学派)の神学者であるビトリア・ソト・カノらが代表団に選ばれ(ただしビトリアは病気のため辞退)、理論面においてカトリック勢力の建て直しに尽力した。
次に開かれた公会議は、300年以上後(1869年~1870年)の第1バチカン公会議である。トリエント公会議において、カトリック教会は、自らの教義を再確認し、トリエント公会議は、20世紀(1962年~1965年に開催)の第2バチカン公会議に至るまでカトリック教会の方向性に大きな影響を与え続けた重要な会議となったのである。1
教皇パウロ3世(220代教皇)は、トリエント公会議開催以前より、プロテスタントの弾圧や教会内部の粛清などを、ローマ教会とスペイン王宮中心に内部革新を展開させていたのだが、その一環としてローマに教皇権限の宗教裁判所を設置した。
宗教裁判所
トリエント公会議開催の3年前(1542年)に、教皇パウロ3世(220代教皇)は、ローマに宗教裁判所(異端審問所)を設けた。宗教裁判所は、スペインとポルトガルにも設けられていたのだが、それらは国王の権限での裁判であった。ローマの宗教裁判所はローマ教皇の権限のもとにあり、特定の教説や著作に対して異端性がないかどうかを審議するとともに、各国で行われる異端審問に問題がないよう監督することが目的としてつくられた。このローマの宗教裁判所は、検邪聖省(略して聖省という)というイタリア国内を管轄する教皇庁の省の一機関となった。
従来の異端審問では、教皇によって少数の異端審問官が任命されるシステムだったのだが、検邪聖省では、所属する10名の神学者や学識の誉れ高い枢機卿が審問官を務め、教皇が代表となって宗教裁判が行われた。検邪聖省長官の役職はドミニコ会が独占していた。その業務の多くは検閲であり、出版物を取り締まって禁書を指定する権限を有していて、1559年には「禁書目録」を定め、思想統制を強めていった。
この宗教裁判所には、弁護士は置かれず、被疑者となった者は疑いが晴れるまで有罪とされ、告発理由と告発者を知る権利や弁護を求める権利はなかった。裁判の目的は、被告に異端思想を抱いていることを自覚、改宗させ、教会と和解させることであった。被告が告解(自白)をしない場合には拷問が行われた。自白し、罪を認めれば異端聖絶文に署名し、罰を受ける。罰は断食、巡礼などの軽微なものから鞭打ち、投獄などの段階があった。罪状を認めなかった場合は世俗的権力に引き渡され火あぶりになることもあった。
1616年に始まった地動説を巡るガリレオ裁判は、この延長線上にある。1633年の審議で、ガリレオの有罪は確定し、自宅軟禁の処分を受けた(すでに地動説を人に説いたり、教えたりすることは禁止されていた)。その後の、自然科学の発達により、地動説の正しさが明らかになっていったことを無視し続けるわけにもいかなかったのか、1979年11月10日(有罪確定から343年後、ガリレオの死から337年後)、教皇ヨハネ・パウロ2世(264代教皇)は、アインシュタイン生誕100年の祝典のなかで、「ガリレオの偉大さはすべての人の知るところ」と題する講演を行い、ガリレオ裁判の見直しに着手した。そして、1983年に裁判が誤りであったことを認めて表明し、翌年1984年に調査委員会も同様の結論に達し、約350年ぶりにガリレオ・ガリレイ(1564-1642) に無罪を言い渡した。1992年、ローマ教皇庁は公式に誤りを認めた。といっても、ガリレオの正しさは、すでに科学によって証明されていたことで、ガリレオやその家族たちは既に世を去っている。誤りを認めたことで名誉を回復したのは、教皇庁だった。ちなみにルターの破門やアハト刑は、解かれていない。
ともあれ、ローマ・カトリック教会は、この教皇権限での宗教裁判所をつくることで、プロテスタントだけでなくカトリック教会内の改革派に対しても厳しい審査の目を向け、カトリック社会の治安と教理の統制を図っていった。2
イエズス会の新設
また、教皇パウロ3世(220代教皇)は、イエズス会を新たに設置している。イエズス会は、1534年(新教との対立が進んだ頃、シュマルカルデン同盟ができて3年後)にバスク出身のイグナチオ・デ・ロヨラを中心として、パリ大学で学んだ同士7人(バスク出身のフランシスコ・ザビエル、フランス出身のピエール・ファーブル、スペイン人のアルフォンソ・サルメロン、ディエゴ・ライネス、ニコラス・ボバディリャ、ポルトガル人のシモン・ロドリゲス)によって創設され、1540年にローマ教皇パウロ3世により承認され修道会となった。
イグナチオ・デ・ロヨラら7人の学友たちが、フランス・モンマルトルの礼拝堂で、「エルサレムへの巡礼」や「清貧と貞節」等の誓いを立てたのが、イエズス会の始まりである。イエズス会は、ローマ教皇への絶対服従、神と教皇の戦士として伝道に努めることを使命として結成され、「神の軍隊」、イエズス会員は「教皇の精鋭部隊」とも呼ばれ、軍隊的な規律で知られている。このような軍隊的な会風は、創立者の1人で・初代総長のイグナティウス・デ・ロヨラが、修道生活に入る以前に騎士であり、長く軍隊で過ごしたことと深い関係がある。
若き時のロヨラは、軍務について各地を転戦していたのだが、ある日、指揮中に飛んできた砲弾が足に当たって負傷し、父の城で療養生活を送ることになった。療養生活の間、暇をもてあましたロヨラは騎士道物語を読もうとしたところ、そこにはなかったので仕方がなくイエス・キリストの生涯の物語や聖人伝を読みはじめたそうである。聖人伝を読んでいくうちに、彼の中に聖人たちのように自己犠牲的な生き方をしたいという望みが生まれてきたのであった。彼は特にアッシジのフランチェスコの生き方に影響され、聖地に赴いて非キリスト教徒を改宗させたいという夢を持った。聖人にあこがれるあまり、彼の本名は「イニゴ・ロペス・デ・レカルデ」であったが、自分の名前をイニゴから(アンティオキアのイグナティオスにならって)イグナチオに改めた(バスク地方ロヨラの貴族の出身だから「ロヨラ」)。健康を回復したロヨラは1522年3月25日にスペインのカタルーニャにある修道院を訪れ、そこで彼は世俗的な生き方との決別を誓い、一切の武具を聖母像の前に捧げ、カタルーニャのマンレザにある洞窟の中にこもって黙想の時を過ごした。そこでロヨラは啓示を受けたとされている。ここにいたってロヨラは世俗の出世を捨て、ひたすらわが身を聖母に捧げることを誓った。もとが軍人だったため、以後の彼の言葉の中には、軍事的な用語やイメージがよく用いられている。3
さて、そのような経緯でできたイエズス会は、対抗宗教改革の一環として、カトリック勢力の回復と拡大を目的とし、積極的に海外布教を行っていった。時は、ポルトガルとスペインが新航路を開拓し、ローマ教皇の承認を得て海外に領土と布教の独占権を拡大していった大航海時代である。1541年(イエズス会が教皇に承認された翌年)、ポルトガル国王の要請を受けて、フランシスコ・ザビエルはインドのゴアに渡航した。1542年にゴアに到着したザビエルは、インド各地で布教活動を行い、ゴアをアジア布教の拠点とした。そして、1549年にフランシスコ・ザビエルが日本に渡航し、キリスト教の布教を開始し、キリスト教が日本にもたらされたのである。
スペイン
先ほどからスペインがよく出てくるので、スペインについて、見てみよう。1469年、イベリア半島の中央にあった「カスティーリャ王国」の女王イサベル1世とイベリア半島の東部や地中海の島々や南イタリアを治めていた「アラゴン連合王国」の王フェルナンド2世の結婚によって、同君連合が実現した。こうして、1479年、キリスト教国のアラゴン王国とカスティリャ王国が統合しスペイン王国となった。両国は1482年からイスラム勢力の領土を侵攻し始め、1492年にはイベリア半島南部ナスル朝(ムスリム王朝)の首都グラナダを陥落させ、ここに国土回復運動(レコンキスタ)が完了した。この功績により、フェルナンド2世とイサベル1世は、1496年にローマ教皇よりカトリック両王の称号を授与された。スペインは、カトリック教会と共に歩み、カトリック教会に根差した国であることが理解できる。
旧新それぞれの改革
こうして、カトリック教会は、改革でこれ以上の内部腐敗を食い止め、教理を立て直し、古くから受け継いだ伝統的教えを守り、海外宣教に力を入れ、新教との違いを明らかにしていった。
トリエント公会議で決まったこと:
- 381年に制定され、三位一体の教理が確立されたニカイア信条が再確認された。
- ルターが聖書から省いた第二正典は正典であるということを正式に認めた。(全73巻)
- 「聖書のみ」というルターの主張を退ける形で、聖書と聖伝が教えの拠り所であること、ウルガタ版がカトリック教会の唯一の公式聖書であるということを決議した。
こうして、ルターの教えは改めて退けられた。
上記は、カトリック側の価値観での決定であったが、ルターが聖書から第二正典を省いた理由は、次の理由からである。
・ ルターは、ヘブライ語聖書(タナハ)のみを(神からの霊感による)聖典とした。
ルターは、イエスが生きていた時代にユダヤ人が正典として認めていたヘブライ語の聖書(タナハ)に立ち返るべきだと考えた。第二聖典(7巻:トビト記、ユディト記、バルク書、シラ書、Ⅰマカバイ記、Ⅱマカバイ記、知恵の書)は、主にヘレニズム時代にギリシア語で書かれたり、ヘブライ語からギリシア語に翻訳されたりしたものであり、ユダヤ教の聖典であるヘブライ語のタナハには含まれていず、捕囚後に書かれたものであった。また、主イエスがこの世に生きていた時代の聖書は、タナハであった。この「聖書のみ」の原則のもと、ルターはヘブライ語聖書にない文書の権威を認めなかったのである。ルターは、この7巻を排除したのではなく、区別したのである。
・「信仰義認説(信仰のみによって救われる)」という教義との矛盾
第二聖典の中には、ルターが提唱した「信仰義認説(信仰のみによって救われる)」と矛盾する内容が含まれていた。例えば、第二聖典の「マカバイ記」には戦死した死者のために、死者の復活に思いを巡らして、死者が罪から解かれるように贖いのいけにえを献げたということが記されていて(Ⅱマカバイ記 12:45)、カトリック教会は、これを煉獄の教義を裏付けるものと見なしている。ルターは、信仰義認を重視したため、善行の重要性を示すようにタナハと同様の権威があるように引用されてしまっていた第二聖典の教えを、自身が見出した神学と相いれないものと判断したのであった。ちなみに、Ⅱマカバイ記の記述は、人間がなした行為であって、神側の評価は書かれていない。捕囚の後、神が沈黙されている時代の信仰の記述である。
・ヨハン・エックとの論争での経験
1519年のライプツィヒ討論で、ルターがカトリックの神学者ヨハン・エックと論争した際、エックは煉獄に関する教義を持ち出し、その根拠として第二聖典の記述を引用した。この論争の後、ルターは第二聖典を正典として認めることをやめている。第二聖典を持ち出し論破する行為を目のあたりにし、神のみこころと人間の記述との区別がわからなくなるような引用をされないよう、ルターは、第二聖典について、教義を確立するための根拠とはならないと公言するようになった。 (ルターの生き方や性質から考慮するに、屈辱を受けたという恨みからではないことがわかる)
ルターは、第二聖典を古来からの聖典と区別して扱ったのである。ルターは、ドイツ語訳聖書を出版した際、第二聖典を完全に削除するのではなく、旧約聖書と新約聖書の間に「外典(アポクリファ)」として区別して含めている。ルターは、第二聖典を外典として「読むには有用で良いものだが、教義を定めるための権威はない」と位置づけたのである。その後の初期のプロテスタント教会では、聖書にも外典が含まれていたのだが、印刷コスト削減などの理由もあって、次第に削除されていったようである。
カトリックは、「聖書のみ」というルターとは異なり、聖伝も教えの拠り所とし、ウルガタ版(ラテン語聖書)がカトリック教会の唯一の公式聖書であると決議した。ユダヤ人は、聖書(タナハ)とともに口伝律法のミシュナも聖典として重んじているように、カトリックもまた、聖伝という伝統を重んじたわけである。この違いは、よい悪いではなく、価値観によるものであり、何を信じるかの違いである。
このように価値観による信条が異なる2つの宗派は、もはや同じものとしては存続することはできず(一緒になろうとすると主張の仕合となり、争いが起こっていくことになる)、それぞれの道を歩み出したわけである。
新教では
カトリックとプロテスタントでは、価値観による信条が異なるため、煉獄についての教えの違いの他に(プロテスタントでは煉獄については教えていない)、違いはいろいろある。
カトリックや正教会では、聖職者を正式には「司祭」、尊称として「神父」(Father)と呼ぶが、プロテスタントでは「牧師」と呼ぶ。そのことにも、教理による認識の違いが現われている。カトリックでは聖職者は、神と信者の仲介役として、秘跡(サクラメント)を司る神から特別に叙階された存在とみなされる「司祭」(祭儀、ミサを司る役職)である。本来のプロテスタントでは、信徒を指導し、教会の運営を担う信者の代表者という立場であり、信仰を導く(羊を牧する)羊飼い(牧師)である。権威を主張したり、支配しようとするのは牧師の務めにはないものであり、注意すべき事柄である。
カトリックは自分たちの教理によって教会の改革に努めたように、カトリックを出たルターも、福音にそぐわず違和感を感じる部分を改革していった。初めは民衆に向けて説教し、キリストへの信仰を深めるように努めていたルターだったが、民衆の中に、更に深く信仰の心が入っていったことを見届けた上で、じっくりと慣習の改革に取りかかった。
第一に手掛けたのは、礼拝だった。改革に手を付けるのだが、大変慎重に(大切に)行っていった。それまでの礼拝は、ラテン語であった。その中で、ルターは説教をドイツ語で行っていた。その頃の中世の教会は、礼拝の中にさまざまなものが入り込んで、複雑な、しかし何となく荘厳な気持ちにさせる、というような礼拝が形成されていた。ルターは、そういった中で、神のことばの礼拝として欠かせない基本的なものを、教会の礼拝の伝統に遡って明らかにし、それに基づく礼拝の改革を行った。そのように整理してから、ヴィッテンベルグの民衆のために、ドイツ語の礼拝を提供した。その後もいろいろな改革の努力が続けられ、1526年に「ドイツミサと礼拝の順序」と呼ばれる礼拝の手引きが完成した。ルターの礼拝は、罪人である私たちに向かって、神が触れてくださる(奉仕してくださる)という考え方であり、礼拝のどの部分を取っても、十字架のキリストが示される形をとった。礼拝のひとこまひとこまに「アーメン」(然り)「アーメン」(感謝)と応答していくようにできている。イエス・キリストの十字架の救いを宣べ伝える神のことばを中心に据えて、罪の認識と罪の赦しが終始はっきりする形で礼拝の改革がなされた。ルターは、この形が絶対だとしたのではなく、「私は一つのモデルを提供する。他の人たちで、もっとよいものを考えだしてくれる人がいるかもしれない。私の提供しているこのモデルがどこででも通用、実用化されなければならないというようなことはないのだ」と言っている。ルターは、人間の限界を知っている謙虚さを持っていた。
この礼拝改革に伴って、ルターはドイツ語の会衆賛美歌を導入した。中世の礼拝で使われているのは、ラテン語の典礼歌で、音楽家が何重唱かの美しい歌声で、何を言っているのかわからないような、複雑な曲を作り出して教会の音楽としていた。それを、キリスト教の十字架の福音に戻って整え直したのであった。4
神の恵みの中にあるルターは、禁欲的な修道院制度の廃止を主張した。ルター自身は大変禁欲的な人であったのだが、聖職者も結婚すべきであり、修道院も廃止すべきであると主張していた。結婚を否定することは、聖書的な根拠がない考えであり、修道院の義務的な活動よりも「働く貧民の世話をすること」が重要だと、ルターは考えていたのであった。
その他、ルターは、教会財産についても、改革を試みた。当時の教会は、沢山の教会財産、教会領土のようなものを持っていて、そういうものに目をつけた諸侯たちもいて、「宗教改革をする」という名目を立て、自分の領内の教会財産を手に入れようとする者たちも出てきていた。ルターは、そういったことを避けるためにも、聖職者の自由になるような扱いをしないような改革、貧しい者たちへの基金や学校教育や災害準備基金といったことを考えて規定を作っていたのだが、様々な事情により、実現には至らなかった。5
ルターの結婚
カトリック教会では聖職者は信仰に専念するため、独身であることが義務付けられている。ルターの時代は、修道士や修道女も結婚しないで、信仰に生涯を費やすという考えが浸透している時代である。また、修道院を脱走したり、脱走をほう助したならば、死罪に当たるという極端な事例もあったような時代であった6。当時の修道院は、自発的に修道女となろうとして入る女性は少なく、ほとんど、家庭の事情や婚期を逸した貴族の娘などが強制的に送り込まれていた。1523年(ルター39歳)、ルターの著作を読んだ9人の修道女たち(ザクセン州のニムシェンという町にある小さい修道院)が、ルターの信仰に動かされ、ルターを頼って、信仰に生きたいと思って相談した。1523年のイースターの頃、ルターの助けにより、9人の修道女たちは、修道院を脱走し、ヴィッテンベルクにやって来た。元修道女であった女性たちは、普通の町の女性になり、いろいろな家に行儀見習いなどで預けられながら、次々と縁を持って、身を寄せるところを得ていった。その中で、一人、カタリーナ・フォン・ボラという女性が残り、ルターは、この女性と1525年6月、結婚した。(マルチン・ルター P186)ルター41歳、カタリーナ26歳であった。ルターは、カタリーナとの結婚によって、三男三女(ヨハネス、エリーザベト〈生後8か月で死去〉、マグダレーナ〈13歳で死去〉、マルティン、パウル、マルガレーテ)をもうけた。若い時のルターは健康そのものであったが、ヴァルトブルク城の生活で、健康のバランスが保てなくなり、40代半ばぐらいになると、循環器系の病気をいくつも抱えるようになり、鬱傾向も時々示すようになっていたのだが、この結婚は、神の愛に生きるルターにとって、益となった。晩年のルターが卓上で語った言葉の記録「卓上語録」というものが残っていて、「愛がいよいよ深く育っていくような結婚」だったという。「たとえ、誰かが私にフランスやヴェネツィアを引換えにくれると言っても、私はカタリーナを手渡しはしない」というような言葉も残っているそうで、信仰による愛の中で充実した家庭生活をいとなんでいたことが伺える。7
多くの違いを持ち、分かれていったカトリックとプロテスタント、それぞれが、神であるキリストを見上げ、神の栄光を現わしていくならば、それはそれで問題はないだろう。人間は、不完全で、いろいろな立場や環境の中、価値観や好みも違い、間違いも犯すが、真理は不動で、消えることもなく、探せば見出せるものである。
イエスの名を使っていながらも、イエスの弟子の仲間になろうとしなかった者に対して、イエスは次のように言われている。「ヨハネがイエスに言った。『先生。先生の名を唱えて悪霊を追い出している者を見ましたが、私たちの仲間ではないので、やめさせました。』しかし、イエスは言われた。『やめさせることはありません。わたしの名を唱えて、力あるわざを行ないながら、すぐあとで、わたしを悪く言える者はないのです。わたしたちに反対しない者は、わたしたちの味方です。』」(マルコ 9:38-40)ヨハネは、「私たちの仲間ではないので(「その人はわたしたちについてこなかったので」(口語訳)、「わたしたちに従わないので」(新共同訳)、「私たちといっしょにならないから」(詳訳))、やめさせた」と報告したが、イエスは、「わたしたちに反対しない者は、わたしたちの味方」=「イエスに反対しない者は、イエスの味方」と言われた。一緒に行動することはなくとも、違うことを信じていたとしても、とりあえず、イエスの味方であり、あとは、神がその人を扱われる。
小さい者たちのひとりにでもつまずきを与えるような誤った教えを教え、つまずかせ、主の取り扱いの中、自分自身を吟味することもないならば、「大きい石臼を首にゆわえつけられて、海に投げ込まれたほうがまし」というようなゲヘナでのさばきが待ち受けているのである。人は、感情のままに行動してしまうような弱さを持ち、全知全能でもないので、主に委ねておかないと誤った判断で間違いを犯しやすい。「あなたがたは、自分自身のうちに塩けを保ちなさい。そして、互いに和合して暮らしなさい。』」(マルコ 9:50)というイエスの命令にとどまりつつ。違いに目を留めず、和合を心がけ、広く長く深く高い神の愛にとどまっていこう。
–> 次の記事:宗教改革の影響~広がって行く過程で
- https://ja.wikipedia.org/wiki/トリエント公会議 ↩︎
- https://www.y-history.net/appendix/wh0903-062.html ↩︎
- https://ja.wikipedia.org/wiki/イグナチオ・デ・ロヨラ ↩︎
- 徳善義和『マルチン・ルター 生涯と信仰』教文館 p157-p160 ↩︎
- 同 p165 ↩︎
- 同 p187 ↩︎
- 同 p216 ↩︎

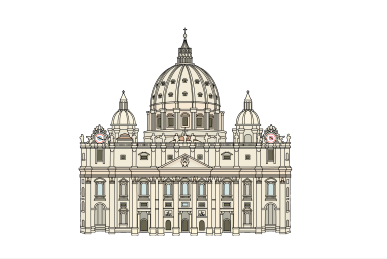

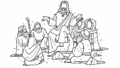
コメント