<– 前の記事:『宣教の前説-王の王であるメシアは人の子として来られた-』
聖書個所:ルカの福音書4章1節~14節(新改訳)
『悪魔の誘惑-示された威光-』
荒野での試み
ここに、バプテスマのヨハネから、バプテスマを受けられた後のイエスの様子が描かれている。ご聖霊が鳩のようにくだり、聖霊に満たされたイエス(ルカ 3:22)は、御霊の導きで、荒野に行かれた。「さて、聖霊に満ちたイエスは、ヨルダンから帰られた。そして御霊に導かれて荒野におり、四十日間、悪魔の試みに会われた。その間何も食べず、その時が終わると、空腹を覚えられた。」(ルカ 4:1,2)
人間に罪が入り、人が神から断絶された原因は、アダムとエバが狡猾な蛇の誘惑のことばに、耳を傾けたことであった。受肉されたイエスが十字架に向けてのこの後の働きに入る前に、神はイエスをサタンと対峙させ、告発者サタンの誘惑はイエスには全く通用しないということを示された。かつてサタンは清廉潔白に生きていたヨブをいろいろな理由をつけて神に告発しようとし、神の許しの中で災いを起こし試した。イエスは、宣教の働きに入る前に、御霊の導きで荒野に行って、この時はまだ「下がれ、サタン」とは言われず、四十日間悪魔にご自分を試みさせ、サタンにご自身の威光を表されたのである。この世の日常のことから離れ、四十日四十夜(マタイ 4:2)の断食で聖別した時を過ごされ、神との交わりを深められた。食べないことの限界は、個人差はあるものの、通常は水がなければ数日、食べ物だけなら3週間程度であると言われている。誰もが気軽にするものではない。長く断食したからといって、修行ではないのだからいばるものでもなく、このような断食は成す使命があってするものである。主イエスは、御霊の導きで、四十日が過ぎるまで空腹を覚えられなかったようだ。
四十という数は、4(普遍的な広がりを表わす数)×10(十全、完全)であり、聖書では、意味のある数である。ノアの洪水の時の雨は、四十日四十夜降り続いた(創世記 7:4)。ヤコブをミイラにするには、四十日かけられた。ミイラにするための腐敗防止の処置のためには、四十日要したのである(創世記 50:3)。また、モーセは十戒をもらったとき、シナイの山で、四十日四十夜パンも水もとらず主とともにいた(出エジプト 34:28)。ヨシュアやカレブらイスラエル人がカナンを偵察したのは、四十日であった(民数 13:25)。この偵察の日数を一日を一年とし、イスラエルの民は、不信仰という自らの咎を負い、四十年間荒野をさまようことになった(民数 14:34)。ゴリヤテが、サウルらイスラエルの陣営の前で、戦いを挑み、おどしていたのは、四十日であった(Ⅰサムエル 17:16)。エリヤはイゼベルからのがれ、四十日四十夜、歩いてホレブの山へやってきた(Ⅰ列王 19:8)。エゼキエルは、ユダの咎が四十年であると示され、四十日間横たわることを命じられた(エゼキエル 4:6)。ヨナの宣教によって、ニネベに与えられた猶予期間は、四十日であった(ヨナ 3:4)。よみがえられた主イエスは、四十日間、弟子たちに現われた(使徒 1:3)。このようにみると、四十日というのは、神が人類のために区切りをつけて何かなさるときの意味ある数に見えてくる。
さて、四十日四十夜がたって、限界までの空腹を覚えられているイエスのもとに、悪魔が現われた。旧約の預言をもちろん知っている悪魔は、イエスが何らかの形で人類を救うということを知っていたのだから、イエスが神に従い続け、人類の救いの道をまっとうされるのをなんとかして、阻みたかった。
悪魔( 
 )「悪魔、中傷者」の語源は、「間を行き交う者」であり、それが他人の告げ口や非難を言いふらすため行き交う人を指すようになっていった。それが、さらに「中傷・誹謗する者」という意味に転じ、悪魔を指すようになった。悪魔は、マタイの福音書では、「試みる者」(マタイ 4:3)、「サタン」(マタイ 4:10)と言われている。「試みる者」
)「悪魔、中傷者」の語源は、「間を行き交う者」であり、それが他人の告げ口や非難を言いふらすため行き交う人を指すようになっていった。それが、さらに「中傷・誹謗する者」という意味に転じ、悪魔を指すようになった。悪魔は、マタイの福音書では、「試みる者」(マタイ 4:3)、「サタン」(マタイ 4:10)と言われている。「試みる者」
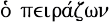 は、
は、
 (試みる)に定冠詞
(試みる)に定冠詞 
 がついた語である。「サタン」
がついた語である。「サタン」
 は、ヘブル語で、「反対する者」「攻撃する者」の意味である。悪魔や悪霊たちは、罪を犯し、自分の領域を守らず自分のおるべき所を捨てた御使いたちとして、聖書に描かれている(イザヤ 14:12-14, Ⅱペテロ 2:4, ユダ 6)。悪魔は、絶えず神にある者を訴える機会を作ろうとし、また機会を捕らえようと狙っている。ヨブを試みにあわせたように(ヨブ1章)、また、大祭司としての務めが回復された捕囚帰還後、大祭司ヨシュアの汚れを神の御前に、とがめ訴えようとしていたように(ゼカリヤ 3:1)、神に属する者たちを引きずり落とそうと狙っている。しかし、主にある信仰者は恐れる必要はない。起こることはすべて神の御手の中の出来事である。物事を自分で処理しようとせずに、神の愛を信じて恐れずに、罪をも神にゆだね、神により頼んで、御前に立ち続けていけばよいのである。神が守っているから清廉潔白でいられるのだと訴えられたヨブは、神の御前で自分の弱さを知り、聖められ、さらなる祝福を得た(この試みでヨブは子供たちや使用人たちを失いはしたが、死は永遠の世界へのこの世の通過点であり、信仰者にとって死は終わりではない)。よごれた服を着て御使いの前に立っていた大祭司ヨシュアは、よごれた服を脱がされ、主からの礼服とターバンを着せられ、主の務めを仰せつかった。そして、一つの若枝を来させると語られ、その国の不義を一日のうちに取り除くとも言われたのであった(ゼカリヤ 3:4-10)。
は、ヘブル語で、「反対する者」「攻撃する者」の意味である。悪魔や悪霊たちは、罪を犯し、自分の領域を守らず自分のおるべき所を捨てた御使いたちとして、聖書に描かれている(イザヤ 14:12-14, Ⅱペテロ 2:4, ユダ 6)。悪魔は、絶えず神にある者を訴える機会を作ろうとし、また機会を捕らえようと狙っている。ヨブを試みにあわせたように(ヨブ1章)、また、大祭司としての務めが回復された捕囚帰還後、大祭司ヨシュアの汚れを神の御前に、とがめ訴えようとしていたように(ゼカリヤ 3:1)、神に属する者たちを引きずり落とそうと狙っている。しかし、主にある信仰者は恐れる必要はない。起こることはすべて神の御手の中の出来事である。物事を自分で処理しようとせずに、神の愛を信じて恐れずに、罪をも神にゆだね、神により頼んで、御前に立ち続けていけばよいのである。神が守っているから清廉潔白でいられるのだと訴えられたヨブは、神の御前で自分の弱さを知り、聖められ、さらなる祝福を得た(この試みでヨブは子供たちや使用人たちを失いはしたが、死は永遠の世界へのこの世の通過点であり、信仰者にとって死は終わりではない)。よごれた服を着て御使いの前に立っていた大祭司ヨシュアは、よごれた服を脱がされ、主からの礼服とターバンを着せられ、主の務めを仰せつかった。そして、一つの若枝を来させると語られ、その国の不義を一日のうちに取り除くとも言われたのであった(ゼカリヤ 3:4-10)。
誘惑のことば
そのような性質を持つ悪魔がイエスに言った。3つの誘惑のことばを投げつけられたことが記されている。
「あなたが神の子なら、この石に、パンになれと言いつけなさい。」(ルカ 4:3)
「また、悪魔はイエスを連れて行き、またたくまに世界の国々を全部見せて、こう言った。『この、国々のいっさいの権力と栄光とをあなたに差し上げましょう。それは私に任されているので、私がこれと思う人に差し上げるのです。ですから、もしあなたが私を拝むなら、すべてをあなたのものとしましょう。』」(ルカ 4:5-7)
「また、悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の頂に立たせて、こう言った。『あなたが神の子なら、ここから飛び降りなさい。「神は、御使いたちに命じてあなたを守らせる。」とも、「あなたの足が石に打ち当たることのないように、彼らの手で、あなたをささえさせる。」とも書いてあるからです。』」(ルカ 4:9-11)
これらの言葉に、主イエスは、どれも申命記のみことばを使って答えられた。申命記は、モーセに授けられた律法のことばで、当時のイスラエル人なら、よく親しみなじんでいるみことばであり、主イエスは、特別にむずかしい聖句を使われたわけではなく、誰でも答えられるような言葉を使われたのである。難問ではないのだが、欲があると、違ったところからみことばを引っ張り出しまでもして、欲に従い敗北の道に進みそうな誘惑のことばである。
かつて、イスラエルの民は、この律法の契約に従えず、「四十日間も山に入ったきりのモーセはどうなったかわからない、死んでいるかもしれないから」という負のことばに負け、鋳物の子牛を作り、また、「神は、カナンの地でわれわれを殺すに違いない。巨人のような民には勝てない」という負のことばに負け、神に反逆し、荒野を四十年間放浪した。いずれも不信仰に陥った結果であった。この敗北続きの神の民を神のもとに勝ち取るため、主イエスはこの世に来られた。3度にわたる誘惑に、主イエスは、どのように返されたか。私たちも見習うべき悪魔の誘惑を撃退する手本になる個所である。
悪魔の誘惑を撃退するには、まず、そのことばが、どこからくるのか見分ける必要がある。この聖書の箇所には、「悪魔は言った」と書いてあるから、悪魔が言っているとわかるのであって、私たちへの誘惑のことばは、「私は悪魔である」と言って語ってくるわけではない。むしろ、光のみ使いのようなそぶりをして語る。時には、「万軍の主が言われる」とイエスであるような前置きまでして、語られたという例をも知っている。どのような言い回しをしたとしても、みことばまでを用いて語ったとしても、偽装の神サタンの語ることばには、本物の神の性質が見られないのである。霊の見分けが大切である。
第一の誘惑「自ら奇蹟を」
初めの誘惑、「あなたが神の子なら、この石に、パンになれと言いつけなさい。」(ルカ 4:3)霊の耳に聞こえてくることば、ぽへらーと「なんか、パンを出す奇跡が聖書にもあったよね、『言いつけなさい』と言われるからそうしよう」とうかつに従ったなら、悪魔の思うつぼである。主イエスは、後に、「だれでも、この山に向かって、『動いて、海にはいれ。』と言って、心の中で疑わず、ただ、自分の言ったとおりになると信じるなら、そのとおりになります。だからあなたがたに言うのです。祈って求めるものは何でも、すでに受けたと信じなさい。そうすれば、そのとおりになります。」(マルコ 11:23,24)と言っておられるが、このとき、石に命じられることはなさらなかった。
「あなたが神の子なら、」は、あなたは神の子ではないかもしれないが、もし神の子であればというニュアンスではなく(神というお方を知りたいという信仰による期待の問いではなく)、「あなたは、わたしの愛する子、わたしはあなたを喜ぶ」(ルカ 3:22)という天からの証明があった主イエスに、あなたは神の子であるのだから、当然のこと、できるでしょう?という意味の条件文である。調子よく祭り上げ、自尊心をくすぐり、高ぶりを引き出そうとすることばである。大事なのは、ことばの表面ではなく、ことばにひそむ思いを見分けることである。迫り来る敵を前にした困難の時、杖で紅海を分けよとモーセに語られたように(出エジプト 14:16)、荒野で水がなく死にそうな状態で神がモーセに杖を打たせて、岩から水を出させたように(出エジプト 17:6)、同じことば「この石に、パンになれと言いつけなさい。」を、多くの人が飢えて困っている状況で、信仰によってなせ、というように語られたのなら、そうすべきである。しかし、今の場合は、そうではなかった。単なる、自分が神の子であるという証明を、今ここで自ら現せという挑発である。空腹という弱さを感じているところを、パンという欲に引いていき、ついには、自分の腹を満たすために、自ら奇跡をなすという、神に罪を犯させるようにしむけているのである。
「飲み水さえない」との民の不信仰による不平不満に限界にきたモーセは、「岩に命じよ」との主の命を越えて、「逆らう者たちよ。さあ、聞け。この岩から私たちがあなたがたのために水を出さなければならないのか。」と言って岩を2度打った(民数 20:3-13)。この時、神に「わたしを信ぜず、わたしをイスラエルの人々の前に聖なる者としなかった」と告げられ、モーセとアロンはカナンに入ることができなかった。「地上のだれにもまさって非常に謙遜」(民数 12:3)であったモーセすら、神に導かれながらも悟ろうとしない民の不平不満に限界が来て、「私たちが・・・出さなければならないのか」と自分が出たのである。人間には限界がある。モーセは岩を2度打って、神に従わなかったからカナンに入れなかったわけではない(律法的に見るとそうなるが)。カナン入植時にも、「神は、カナンの地でわれわれを殺すに違いない。巨人のような民には勝てない」とエジプトに帰ろうと言っている民である。この民を引っ張ってカナンに入ることは後継者に負わせ、これ以上モーセには重荷を負わせなかった神の愛とモーセの使命によるものである。
その挑発のことばに、主イエスはどう答えられたか。「『人はパンだけで生きるのではない。』と書いてある。」(ルカ 4:4)聖書のみことばをもって返された。みことばを返すには、みことばの意味を覚えていないとできない。「あなたに罪を犯さないため、私は、あなたのことばを心にたくわえました。」(詩篇 119:11)みことばを日々蓄えることは、大切なことである。が、やみくもに暗記しているみことばを言えばよいというものではなく、意味が大切である。主イエスは、「この石に、パンになれと言いつけなさい。」という誘惑のことばに、申命記のみことばをもって返された。「それで主は、あなたを苦しめ、飢えさせて、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。それは、人はパンだけで生きるのではない、人は主の口から出るすべてのもので生きる、ということを、あなたにわからせるためであった。」(申命記 8:3)必要ならば、神は、自らマナを与えてくださる方である。エリヤのもとへカラスにパンと肉を運ばせたように(Ⅰ列王 17:3,4)、神が与えてくださるものであり、自分が作り出すものではないのである。神は、おまえが自分で出してみろと言われるようなお方ではない。物やお金に仕えさせようとする誘惑がきた時は、まずその誘惑に気付き、主の口から出るものがすべてであって、満ち足りる信仰こそが神に喜ばれる道であるということを思い出そう(「満ち足りる心を伴う敬虔こそ、大きな利益を受ける道です」(Ⅰテモテ 6:6))。狡猾な悪魔的な挑発にのって、罪を犯さないためには、主というお方をよく知らなければならない。
第二の誘惑「栄光の権力」
2度目の誘惑は、人が住んでいる世界中の国々を幻のうちに見せて、「もしあなたが私を拝むなら、すべての権力と栄光をあなたのものとしましょう。」と言うことばであった。マタイは、ルカの2番と3番を入れ替え、3度目の誘惑に上げている(マタイ 4:8,9)。マルコは、誘惑にあったことだけを記していて内容は記していない(マルコ 1:12)。
人類に罪が入ってから、悪魔は、この世においては、「この世の支配者」「空中の権威を持つ支配者」と呼ばれ、ある程度の権威を有しているようだ。しかし、それは全知全能万軍の主である神の御手の中のことであって、神の絶対的な主権の中でのことだ。悪魔は、全くの嘘をつくばかりではなく、時には、本当のことを含めて、みことばをも使ったりするから、クリスチャンをも惑わすことができるのである。悪魔は、真理を知らないわけではなく、私たちよりも真理を熟知している霊的存在であり、私たちよりも能力を持っているから、巧みに欺くことができるのである。この霊的存在の悪魔に自分の力で立ち向かおうとしても無理である。全能の神により頼み、聖霊に満たされ、知恵と力をいただいていかなければ、到底無理である。揺らいだ時こそ信仰を働かせることが大切である。
初めは、食欲という肉の欲をつついてきたサタン。今度は、名誉欲に訴え出る。サタンを拝むだけで、この世の栄光と権力が手にはいるというのである。サタンを拝み、栄光と権力を手にしたとしても、それは、一時だけであるが・・・。歴史上でみても、権力を有した独裁者の末路は、悲惨である。人は、栄光の時だけを祭り上げて取り上げやすいが・・・。主イエスは、このような条件をのまなくとも、すでに、王の王、主の主であられる神であった。語ったのが、サタンであるとわかっていたなら、「私を拝め」ということばに、クリスチャンであればだれもひっかかりはしないだろう。しかし、神のようなそぶりで語られたならどうだろうか。私は大丈夫と言う人は油断が生まれないように気を付けたほうが良い。神よりも権力への欲が強ければ、神に従えば、高い地位につけてくださるのだと、飛びつくかもしれない。先程のパンにしてもそうである。神よりも食欲、名誉欲などのあらゆる欲望がまされば、人間は、理屈をつけて、その欲に従ってしまう。それを防ぐのは、「心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。」(申命記 6:5)という愛に基づく信仰だけである。少し愛して長く愛してというゆるやかな愛ではなく、心、精神、力と、霊、魂、肉体すべてにおいて全力を注いで、愛する熱い愛である。そのような神への愛があれば、誘惑が来たときに、神のことが思い浮かび、肉の欲が勝つことはないのである。マルチ商法の組織のトップに就こうとしていた人に注意すると、「主のことばを伝えるために、トップの力を持たないと」と言って、走って行ってしまった人がいた。欲に従ってトップの力を持った時、人はどうなるか、歴史を見るとわかるだろう。主イエスは、この誘惑に、この「心を尽くし・・・」の後のみことば、「ほかの神々、あなたがたの回りにいる国々の民の神に従ってはならない。」(申命記 6:13)をもって、返された。
第三の誘惑「神を試す」
3度目の誘惑(マタイでは、2度目の誘惑)は、エルサレム神殿の頂から飛び降りろというものであった。「『神は、御使いたちに命じてあなたを守らせる。』とも、『あなたの足が石に打ち当たることのないように、彼らの手で、あなたをささえさせる。』とも書いてあるからです。」(ルカ 4:10,11)と、聖書のみことばを使っての誘惑であった。この聖書の原文はどうなっているか。「まことに主は、あなたのために、御使いたちに命じて、すべての道で、あなたを守るようにされる。彼らは、その手で、あなたをささえ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにする。」(詩篇 91:11,12)とある。ここだけ見たなら、聖書を差し出され、「ほら、ここに書いてあるでしょう」と言われでもしたら、「すべての道で」が省かれてはいるけれど、すべての道ということは、この道も含まれているのだから、「確かに書いてあるよね、気がすすまないけど、みことばだからやってみるか。」となりかねない。しかし、この「すべての道で」が省かれたことにより、神の広さ、偉大さから目が離れ、限定的なことに目が向くことになる。実に巧妙に神の性質をすり替えている。
みことばは、神の性質である愛で読まなければ、変質してしまう。たとえ、まったく同じことばを使おうが、意図する思いが悪いなら、変質してしまい、みことばとはかけ離れたものとなってしまう。サタンは、自分に都合よく、神のみことばを当てはめて、愛でも聖でも義でもないところに引いていく。誤ったみことばを信じ引いていかれた人々は、神が言っていると思い込むところから、聖書を知らない人たちよりも、取り扱いがやっかいになる。
「いと高き方の隠れ場に住む者は、全能者の陰に宿る。」(詩篇 91:1)で始まるこの詩篇91篇。危険やわざわいからの神さまの守りを歌っている。
「主は狩人のわなから、恐ろしい疫病から、あなたを救い出されるからである。」(詩篇 91:3)
「あなたは夜の恐怖も恐れず、昼に飛び来る矢も恐れない。また、暗やみに歩き回る疫病も、真昼に荒らす滅びをも。」(詩篇 91:5,6)
「それはあなたが私の避け所である主を、いと高き方を、あなたの住まいとしたからである。わざわいは、あなたにふりかからず、えやみも、あなたの天幕に近づかない。」(詩篇 91:9,10)
「彼がわたしを愛しているから、わたしは彼を助け出そう。」(詩篇 91:14)
自分から好きこのんで危険の中に飛び込んでも、勝手気ままに高い所から飛び降りても、守ってくださるべきだというみことばではない。神への愛によって、命が危険にさらされたりしたとき、必要ならば守ってくださるのである。必ず守ってくださるというわけではない。死によって神が栄光をお受けになることもある。死をもってふるわれる信仰者は、「父よ、わたしの霊をみ手にゆだねます」(ルカ 24:46)と言われたイエスにならう道を歩んでいった信仰者たちである。そういう信仰者たちは、「命を失っても、神に従おう」と思っているのだから、「守ってくださるべきだ」とは考えない。主イエスは、みことばをもって、神の性質をゆがませようとする誘惑に、やはりみことばをもって答えられた。「『あなたの神である主を試みてはならない。』と言われている。」(ルカ 4:12)と返された。「あなたがたがマサで試みたように、あなたがたの神、主を試みてはならない。」(申命記 6:16)の引用であった。ここでいう試みは、なげやりな試みとか、あざけりまじりの試みのような信仰の土台に立たない試みである。ギデオンが、神のことばのしるしとして、羊の毛の露をしるしとして求めたような試みに、主が応じられたのは、ギデオンの心にみじんの悪もなかったから、純粋に知りたいという信仰からであったから、ギデオンの弱さに応えられたのである(士師 6:36-40)。
私事であるが、下の子が3年生くらいのとき、入り口に置いてあった台車で、住んでいた公団の自動ドアを割ってしまったことがあった。公団事務所に謝りに行き、弁償額の知らせを待っていた。以前、割ったことがある他の子供が、7万円ほどの弁償をしたことを聞き、また、大きな試練により弱さを覚えているときであった。出費がかさんでいたことから、「主よ、もう気力がありません。私を愛してくださっているなら、ただにしてください。」と弱さの中で祈りながら、事務所に行った。すると、「今回は、業者が置いていった台車ということもあるし、特別に、弁償はいりませんと、上の許可がおりました。」と言われた。この話を公団の自治会の人にすると、とても驚いていた。神を愛し、純粋に神を求める心からの求めには、愛を試す(ここでは、むしろ、愛を知りたい)という思いにも、神は答えてくださることもある(絶対ではない)。ことばだけを取り上げるなら、神の愛を試すなんて・・・となるが、心は純粋に神を求めてのことであった。
マタイとルカの順序の違いは、対象とする読者(マタイはユダヤ人、ルカはギリシャ人を意識している)ゆえに、最後に一番印象に残らせたいもので締めくくったのだろうか。(マタイは栄光と権力、ルカは奇蹟への試み)
必ずやってくる誘惑
3度の誘惑、主イエスは聖書のみことばをもって返されているのだが、聖書を熟知していなくても、神さまの性質を正確に知り、神を愛する愛に立つなら、「神さまは、このような方である。」と、惑わされることを避けることができるのである。私たちは、十字架の神の愛にふれられて、救いを受けているのだから、神の愛を知っているはずなのであるが、肉の弱さがあり、忘れやすいものである。主イエスのこれらの誘惑は、聖霊を受けた直後であった。このような誘惑は、聖霊を受けて勇んで歩みだそうとする時にくることが多いようだ。誘惑を受けることは、神の許しの中で起こることであり、聖霊のことばに耳を傾け、聖霊により頼む訓練でもある。「あなたがたのあった試練はみな人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなたがたを耐えることのできないような試練に会わせるようなことはなさいません。むしろ、耐えることのできるように、試練とともに、脱出の道も備えてくださいます。」(Ⅰコリント 10:13)試練は、私たちを倒すためではなく、高めるためにある。
「誘惑の手を尽くしたあとで、悪魔はしばらくの間イエスから離れた。」(ルカ 4:13)悪魔はイエスの誘惑に手を尽くしたが、主イエスは、全くその手にのらなかった。みことばを使っても落とせなかった悪魔は、しばらくの間、主イエスから離れた。この後、サタンは、また違う手を使ってくるのである。イエス自身を、ゆるがせることができなかったため、ユダという身近な側近の者を利用して・・・。
「イエスは御霊の力を帯びてガリラヤに帰られた。すると、その評判が回り一帯に、くまなく広まった。」(ルカ 4:14)荒野での誘惑を抜けられた主イエスは、御霊の力を帯びて地元のガリラヤに帰られた。するとイエスの評判が回り一帯にくまなく広がったとある。どのような評判だったのだろうか。御霊の力を帯びているイエスの評判のようだが、言葉や態度や雰囲気で、明らかに他の人や以前とは違うものがあったのだろう。悪魔が差し出そうとした(悪魔の言葉に従ったとしても本当に差し出したかどうかはわからないが)世界中の権力はいきなり得られないが、確実に、名声は広まっていく、こつこつ神に従って歩んでいくなら、ちょうどよい時に神ご自身が高めてくださるのが、神のやり方である。「あなたがたは、神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神が、ちょうど良い時に、あなたがたを高くしてくださるためです。」(Ⅰペテロ 5:6)
「心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。」(申命記 6:5)心、精神、力を尽くす3拍子の愛、私たちは、これほど、主イエスを愛しているだろうか。どこかに自分という余力を残していないだろうか。自分というものを残しているとき、そこを巧みにつついてくる霊的存在がいることを忘れてはならない。むずかしいことをたくさん覚えなくても、神への愛と人への愛、早い話、この2つが律法の集約である。新約のキリストの自由の律法でもある神と人への愛の2つだけでも聖書は十分なのであり、悪魔の誘惑に立ち向かうためにも、十分なのである。ところが、人間、このたった2つがなかなかできない。1つであってもできない。御霊の力により頼むことで、そのことが可能となる道を主イエスは開かれた。
–> 次の記事:『イエスの教え-会堂で-』

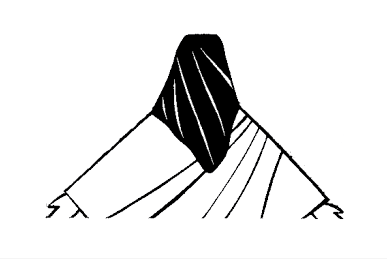



コメント