聖書個所:ユダの手紙 1節~25節(新改訳)
『恵みと放縦-背教-』
ヤコブの兄弟ユダ
「イエス・キリストのしもべであり、ヤコブの兄弟であるユダから、父なる神にあって愛され、イエス・キリストのために守られている、召された方々へ。どうか、あわれみと平安と愛が、あなたがたの上に、ますます豊かにされますように。」(ユダ 1,2)で始まるこの短い手紙の差出人は、自分を「ヤコブの兄弟であるユダ」と名乗っている。ユダという人物は、聖書には数名出てくるが、「ヤコブの兄弟」と名乗っただけで、通用した人物は、エルサレム教会の中心的指導者であり、ヤコブの手紙の著者の「ヤコブ」の兄弟であるユダである。つまり、ユダの手紙の著者は、イエスが地上におられたときの肉の兄弟であるユダとされている。そのユダが、自分を紹介するために用いたのが、「イエスの兄弟ユダ」ではなく、「イエスとヤコブの兄弟であるユダ」でもなく「イエス・キリストのしもべであり、ヤコブの兄弟であるユダ」であった。ヤコブもユダを含む兄弟たちも、復活したイエスに会うまで、イエスを信じることができなかった。イエスが生きている間はイエスを信じなかった兄弟たちであったが、復活の主イエスが実際にヤコブに現れて、その後、兄弟たちは母マリヤと共に祈る人に変えられていった(イエスの「兄弟」参照)。
ヤコブやユダたちにとって、イエスの兄弟であったことは、一番身近にいながら、神に遣わされた者を信じることができなかった人間の罪深さを思い知るだけで、自慢になるような要素ではなかった。イエスの身内の者たちは、イエスが十二使徒を任命し本格的に宣教を開始しようとした時、気が狂ったと思って、力づくで連れ戻そうとイエスを訪ねていた。「彼の身内の者たち〈肉親の者たち〉は、力ずくで彼を取り押さえようとして出かけて来た。『彼は気が狂っている〈逆上している、錯乱している〉』と言っていたからである。」(マルコ3:21 詳訳聖書-新約-, いのちのことば社発行 P89, P90)。その後、群衆を教え、宣教を進めている時にも話をしようと出向いてきている(マタイ 12:46-50)。そこには、母や兄弟たちが、みこころを行なっていなかったことが語られている。そして、ヨハネ 7:5では、イエスが人々を集めて伝えていることは著名になりたいと思ってやっていることだと思って、兄弟たちが「公の場に出たかったら、自分を世に現しなさい。」と忠告をしたことが書かれていて、「兄弟たちもイエスを信じていなかったのである。」とはっきりと書かれている。兄弟たちは、復活の姿を見るまでは、肉親としての情愛は持っていたが、「預言者はだれでも、自分の郷里では歓迎されません。」(ルカ 4:24)の実践をしていたような者であった。
身近な肉親であった自分たちより、弟子であったペテロやヨハネたちの方がよほどイエスというお方を信じ、従っていたことは、こうして聖書に書かれているように、キリスト教会内では、周知の事実であった。兄弟たち(母も)に「イエスの兄弟(母)」と誇るような心はみじんもなかったのである。
恵みを放縦に変える偽物
「愛する人々。私はあなたがたに、私たちがともに受けている救いについて手紙を書こうとして、あらゆる努力をしていましたが、聖徒にひとたび伝えられた信仰のために戦うよう、あなたがたに勧める手紙を書く必要が生じました。というのは、ある人々が、ひそかに忍び込んで来たからです。彼らは、このようなさばきに会うと昔から前もってしるされている人々で、不敬虔な者であり、私たちの神の恵みを放縦に変えて、私たちの唯一の支配者であり主であるイエス・キリストを否定する人たちです。」(ユダ 3,4)時は一世紀(67年頃)ネロの迫害下である。ユダヤ戦争が起こり、ペテロやパウロが殉教を遂げる頃である。ユダは諸教会に、「私たちがともに受けている救いについて手紙を書こうとして、あらゆる努力をし」福音を伝える努力をしていた時に、福音を歪ませ、罪の自覚と悔い改めから遠のかせるような教えで、教会内を荒らし回る偽の兄弟たちが急激に出現しているという報告がユダのもとに届いた。この偽の兄弟たちは、「神の恵みを放縦に変えて、私たちの唯一の支配者であり主であるイエス・キリストを否定する人たち」であった。キリストの救いから離れさせ、この世の楽しみに目を向けさせて背教に導く者たちの存在に、警告の急を感じたユダは、「聖徒にひとたび伝えられた信仰のために戦うよう、あなたがたに勧める手紙を書く必要」を感じ、この手紙を諸教会(小アジヤの教会)に書き送ったのであった。「私たちの唯一の支配者であり主であるイエス・キリストを否定する」異なる教え(異端)の侵入を防ぐには、まず、イエス・キリストという真理に立った兄弟同志が互いに、与えられた「あわれみと平安と愛」(ユダ 2)の内にとどまり続け、ますますはぐくんで豊かに持つことである。
「忍び込んで」ということばからもわかるように、ここで言われている問題は、教会内部のことを言っている。ユダに限らず、教会の指導者たちは、絶えず、内部に起こってくる偽りという敵と戦っていた。私たちの信仰の戦いの中で最も困難な戦いは、外との戦いではなく内との戦いである。全く異なるものならば、だまされはしないが、よくできて美しく見え欲をくすぐるような贋作を識別するのは非常に困難なことである。サタンは私たちの弱さをよく知っていて、どうすれば、クリスチャンをだませるかも熟知している。内部崩壊が大きいダメージをもたらすことも知っている。「もし国が内部で分裂したら、その国は立ち行きません。また、家が内輪もめをしたら、家は立ち行きません。サタンも、もし内輪の争いが起こって分裂していれば、立ち行くことができないで滅びます。」(マルコ 3:24)だからこそ「あわれみと平安と愛」が大切なのである。「律法の全体は、『あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。』という一語をもって全うされるのです。もし互いにかみ合ったり、食い合ったりしているなら、お互いの間で滅ぼされてしまいます。」(ガラテヤ 5:14,15)とパウロも書いているように、偽物が忍び込んできたときに、信者同士が「愛は結びの帯として完全なものです。」(コロサイ 3:14)とある「愛」という帯で固く結ばれていたならば、崩れないのである。一瞬偽物を信じる者が出ても、偽物のメッキはいつか剥がれるもの、真理は剥がれるものがなく不動であり、わからずに偽物に耳を貸した者たちが偽物と知った時に「愛」に立ち返ることができる。放蕩息子が父のところに帰ったように…。キリストにある兄弟の絆は、一人一人に与えられた信仰と自由意思によって、形成されるものである。
偽物は、表面をカムフラージュして本物のように見せかけて入ってくる。それも愛による信仰がためされる時で、神の御手の中である。このような背教をもたらす者たちは、「さばきに会うと昔から前もってしるされている人々で、不敬虔な者であり、私たちの神の恵みを放縦に変えて、私たちの唯一の支配者であり主であるイエス・キリストを否定する人たち」と書かれている。「不敬虔な者」は、神を神として恐れ敬わない者のこと、「放縦」は 
 「好色」とも訳される語であり、肉の欲望のままに生きることを言っている。
「好色」とも訳される語であり、肉の欲望のままに生きることを言っている。
それでは、どのような経過をたどって「私たちの神の恵み」が「放縦」に変質してしまうのだろうか。本来、「神の恵み」は、罪の生き方に対して、救いをもたらすものである(恵みによって罪を知り、罪から離れて神に従いたくなる)。「放縦」というのは、自分の欲望を捨てることもせず(罪から離れる気もない)、「神の恵み」の道を脇に追いやり(恵みをいいように自己解釈し)、欲望のままに生きることである。クリスチャンへの落とし穴は、神は恵みに満ち、何の代償も要求せずに罪を赦してくださる方であるから少しぐらいみことばを無視しても大丈夫だ、キリストの血があるから大丈夫だ、また赦してもらえばよいという発想である。そのような発想は、神や自分への甘さと神への侮りを原因とするもので、エスカレートしていく。聖絶のものをかすめとり、神の怒りを招いたアカンや、イエスの弟子でありながらイエスを売ったイスカリオテ・ユダにも見られた思いである。
初代教会の頃に異端として台頭してきたものに、グノーシス主義があった。グノーシス主義というのは知識を意味するグノーシスというギリシャ語に由来していて、カメレオンのように知的な環境の色に染まる思想体系を持つ集団につけられた名であった。キリスト以前からギリシャやユダヤ、オリエント起源の思想を吸収し、キリスト教も取り入れて発達させていき、その後、知的な異教徒が受け入れやすいようにグノーシス主義によって修正されたキリスト教として現れ、真に危険な異端となった1。
初代教会の頃のグノーシス主義は、次のように考えていた。「善であるのは精神だけで、物質は本質的に悪である。したがって肉体は本質的に悪である。だから人間は肉体において何をしてもしかたがない。どうせ肉体は悪なるものなのだから。神の恵みは大きくてすべての罪を覆うのだから、人はどれだけ罪を犯してもよい。イエスに頼む者は何をしても赦されるだろう。罪が多ければ多いだけその分、神の恵みも大きくなる。だから罪を犯すことを心配する必要はない。イエスが面倒を見てくれるだろう。」こうして神の恵みは曲解され、公然と罪を行なう口実とされた。そのゆえに彼らは「イエスを否定する者たち」と言われている2。
このような異なる教えは、形を変えて今でも、教会の中にはいりこんでくる。人間の罪の性質は変わらないため、名を変え形を変え、やってくる。よくない部分を指摘すると、彼らは言う。「人はもともと罪深いのだから、いくら罪を犯しても、大丈夫なのだよ。『罪の増すところには恵みも増し加わる』(ローマ 5:20参考)とパウロも言っているし」と、みことばまで持ち出して正当化する。彼らは口先ではキリストを信じていると言いながら、その生活態度においてはキリストに支配されることを拒否し、口先だけで「イエスは主」と言うが、キリストの精神をもって主を仰いで仕えようとはしない。そのような態度は、神を自分の欲のために使っているにすぎないという第三者からのあざけりの要素を提供することになる。
サタンは、人間の弱さを知り尽くしていて、二千年前からの手口を今日も使っている。真理からそらそうとする放縦に変わった恵みの福音を信じた人々は、自分たちの教理を正当化するために、上述したように真理から少しばかりずれたみことばを持ち出す。「私たちは、律法の下にではなく、恵みの下にあるのだから罪を犯そう、ということになるのでしょうか。絶対にそんなことはありません。」(ローマ 6:15)と言っているパウロの真意をくみとりもせずに、迷いの道に導いていくのである。
背教を前に思い出させたいこと
ユダは、「あなたがたは、すべてのことをすっかり知っているにしても」と、キリストの福音をすでにすべて知っているはずの信者に向けて、切り出した。「あなたがたは、すべてのことをすっかり知っているにしても、私はあなたがたに思い出させたいことがあるのです。」(ユダ 5a)思い出させたいこととして、旧約のさばきの実例を3つあげている。これらの例と、偽の兄弟たちの行動に共通点があるからである。
- 「それは主が、民をエジプトの地から救い出し、次に、信じない人々を滅ぼされたということです。」(ユダ 5b)
エジプトの奴隷身分から、神の奇蹟により、救い出されたにもかかわらず、荒野の困難の中、不信仰に陥り、神に対する信頼を失って、ついに神の怒りによって滅ぼされた事件である。 - 「また、主は、自分の領域を守らず、自分のおるべき所を捨てた御使いたちを、大いなる日のさばきのために、永遠の束縛をもって、暗やみの下に閉じ込められました。」(ユダ 6)
天の光の中で一定の領域を与えられて不自由のない自由な生活を送り、神のそばで使えるというすばらしい役割を持っていても、自らの傲慢のゆえに神に反した御使いたちのことである。本来の栄光の務めを放縦に変えたのである。その結果が、「大いなる日のさばきのために、永遠の束縛をもって、暗やみの下に閉じ込められ」たのならば、神の似姿に造られた(御使いよりまさる存在の3)人間が、恵みによって与えられた「神の子」という天的身分を傲慢にも濫用した場合に、さばかれずに済むことはない。 - 「また、ソドム、ゴモラおよび周囲の町々も彼らと同じように、好色にふけり、不自然な肉欲を追い求めたので、永遠の火の刑罰を受けて、みせしめにされています。」(ユダ 7)
道徳的に腐敗した人間へのさばきである。「みせしめ」とあるように、後の時代に生きる者への予表である。
偽の兄弟たちの特徴
このような歴史上の警鐘があるにもかかわらず、偽の兄弟たちは、堕落と背教に人々を導いているのである。彼らの特徴が、4つあげられている。「それなのに、この人たちもまた同じように、夢見る者であり、肉体を汚し、権威ある者を軽んじ、栄えある者をそしっています。」(ユダ 8)
- 「夢見る者」
サタンも、「天に上り、神の星々のはるか上に王座を上げ、北の果てにある会合の山にすわり、密雲の頂に上り、いと高き方のようになる」(イザヤ 14:13,14)という夢を描いた。ここでは、見せかけの幻によって、自分の教えを正当化している人のことを言っている。 - 「肉体を汚し」
夢見た結果の行いである。パウロは、「不義をもって真理をはばんでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して、神の怒りが天から啓示されている」(ローマ 1:18)ことについて触れている。「神の、目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこのかた、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はない」(ローマ 1:20)と厳しいと思うようなことが語られている。「不義をもって真理をはばんでいる人々」というのは、真理(神が私たちに計画されているよいこと)を見ようともしないで、また、周囲の人々にも見させないように働き、欲のままに不義に誘うような人々である。「彼らは、神を知っていながら、その神を神としてあがめず、」(ローマ 1:21)「自分では知者であると言いながら、愚かな者となり、」(ローマ 1:22)「不滅の神の御栄えを、滅ぶべき人間や、鳥、獣、はうもののかたちに似た物と代えてしまい」(ローマ 1:23)とあり、その結果、肉体を汚すようになることが書かれている。「それゆえ、神は、彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡され、そのために彼らは、互いにそのからだをはずかしめるようになりました。」(ローマ 1:24)そのようなことになった理由も書かれている。「それは、彼らが神の真理を偽りと取り代え、造り主の代わりに造られた物を拝み、これに仕えたからです。」(ローマ 1:25) - 「権威ある者を軽んじ」
自分の罪の暗さゆえに、神の聖さに従っている(神の権威につながっている)者を侮蔑し軽んじていく。それは、主を否定する態度に直結する。また、この世の権威について、軽んじる態度も同じである。この世の権威は、人が立てたように見える権威であったとしても、何らかの神の計画の中で置かれたものである。自分にはわからない神の未来に向けての計画が存在する。「人はみな、上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて、神によって立てられたものです。したがって、権威に逆らっている人は、神の定めにそむいているのです。そむいた人は自分の身にさばきを招きます。」(ローマ 13:1,2) - 「栄えある者をそしる」
神の御手の中、神の許しの範囲で栄えさせている者をそしることは、主をけがす態度に直結している。神にある人は、たとえ自分に暴言を吐かれようが、その相手をそしることはしない。ダビデが、残存していたサウルの家の一族のシムイに石を投げつけながら、のろいのことばを吐かれた時、「彼がのろうのは、主が彼に、『ダビデをのろえ。』と言われたからだ。だれが彼に、『おまえはどうしてこういうことをするのだ。』と言えようか。」と神に委ね放置したのだが(Ⅱサムエル 16:5-13)、感情にままに動かないことは神と共にある者の態度である。「御使いのかしらミカエルは、モーセのからだについて、悪魔と論じ、言い争ったとき、あえて相手をののしり、さばくようなことはせず、『主があなたを戒めてくださるように。』と言いました。」(ユダ 9)悪魔が相手でも、ののしらない態度である。感情を自分で抑えて、心の奥底と行動に食い違いがあるような偽善を言ってはいない。神に委ねての心からの行為である。そしりやののしりは、聖められていない本能のままの肉の働きであり、人を汚すものでしかない。イエスは言われた。
「悪い考え、殺人、姦淫、不品行、盗み、偽証、ののしりは心から出て来るからです。これらは、人を汚すものです。」(マタイ 15:19,20)
「内側から、すなわち、人の心から出て来るものは、悪い考え、不品行、盗み、殺人、姦淫、貪欲、よこしま、欺き、好色、ねたみ、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪はみな、内側から出て、人を汚すのです。」(マルコ 7:21-23)
罪の結果は滅びであり、それが悪であるということは「本能によって知るような事がら」であり、知らなかったという言い訳は通用しない。「しかし、この人たちは、自分には理解もできないことをそしり、わきまえのない動物のように、本能によって知るような事がらの中で滅びるのです。」(ユダ 10)
偽の兄弟たちの忌まわしさ
忌まわしいこととして、次にユダは、続けて旧約の例を3つあげている。「忌まわしいことです。彼らは、カインの道を行き、利益のためにバラムの迷いに陥り、コラのようにそむいて滅びました。」(ユダ 11)と。
- 「カインの道」
神への不従順の心と、欲望から出る利己心から兄弟をないがしろにしたカインの道である(創世記4章)。 - 「バラムの迷い」
利益のための物欲に支配され、民をそそのかして、偶像と姦淫の道に引き込み、迷いの道に陥らせたバラムのような誘惑者の道である(民数 31:16、黙示録 2:14)。 - 「コラのようにそむく」
自ら会衆の上に立ちたいという支配欲のため、仲間と共謀してモーセに逆らい、分を越え不当な要求をしたコラのような高慢の道である(民数 16章)。
「罪」の原語は 
 「的外れ」である。何から的を外すのか。神が私たちの幸せのために意図され定められた、本来あるべき目的や道から外れた状態である。上述の3つは、自己中心的な欲からの行為であった。これらは、内部崩壊により大きなダメージを与えた。
「的外れ」である。何から的を外すのか。神が私たちの幸せのために意図され定められた、本来あるべき目的や道から外れた状態である。上述の3つは、自己中心的な欲からの行為であった。これらは、内部崩壊により大きなダメージを与えた。
「彼らは、あなたがたの愛餐のしみです。恐れげもなくともに宴を張りますが、自分だけを養っている者であり、風に吹き飛ばされる、水のない雲、実を結ばない、枯れに枯れて、根こそぎにされた秋の木、自分の恥のあわをわき立たせる海の荒波、さまよう星です。まっ暗なやみが、彼らのために永遠に用意されています。」(ユダ 12,13)彼らは、雪よりも白いイエスの交わりにしみをつける「愛餐のしみ」(詳訳では、「愛餐の中の暗礁〈として危険な分子〉」(詳訳聖書-新約-, いのちのことば社発行 P686)であると言われている。これらの行為は、それだけ許してはならない、主の交わりを破壊する行為であるからだ。
そのような恐れげもなくともに宴を張っている彼らについて、ユダは「自分だけを養っている者」と言っている。詳訳を見るとこう書かれている。「その愛餐の場で彼らは思い切ってぜいたくな〈〔あなたがたのまん中で〕みんないっしょになって騒ぎ飲む〉酒盛りを、ためらいもせず、自分たちの腹のために〔だけ〕開くのです。」(詳訳聖書-新約-, いのちのことば社発行 P686)キリスト者の交わりは、互いの徳を高めるためのものである。自分だけを牧し(養い)※、自分が満腹したらよいという利己心を示していて、そばにいる羊たちがお腹をすかせていようが、喉が渇いていようが、死にかけていようが顧みない。そのことをここでは4つの比喩で語られている。
※「養う」
 は「(羊の群を)牧する,牧者の務めを果たす,(羊に)食物を与えて世話をする,養う,飼う,治める」の意味である。
は「(羊の群を)牧する,牧者の務めを果たす,(羊に)食物を与えて世話をする,養う,飼う,治める」の意味である。
- 「風に吹き飛ばされる、水のない雲」
恵みの雨を降らせるような期待だけさせておきながら、さっぱり雨を降らせない水がない雲。風が吹くと、吹き飛ばされてどこかに行ってしまう、全くあてにならず、そこにあったのは、欺きと無益である。 - 「実を結ばない、枯れに枯れて、根こそぎにされた秋の木」
収穫の秋だというのに、主につながっていないために全く実(ガラテヤ5:22,23に書かれている御霊の実)を結ばない様子である。「枯れに枯れて」というのは、直訳すると「二度死んで」であるそうだ。主の恵みを一度味わって後、堕落することである。「根こそぎ」とは、徹底的なさばきを示す。 - 「自分の恥のあわをわき立たせる海の荒波」
荒波のように絶えず動揺している様子。「悪者どもは、荒れ狂う海のようだ。静まることができず、水が海草と泥を吐き出すからである。『悪者どもには平安がない。』と私の神は仰せられる。」(イザヤ 57:20,21)「恥のあわ」いくら隠していても心の汚れは隠しきれず、あわのように現れては消えていく。なくなることはなく、わいて出てきて表に見え隠れしながら浮かばせている。 - 「さまよう星」
本来、秩序正しく、軌道に乗って動いているのが星である。置かれた正しい道を捨て、真理から迷い出た無軌道な生き方である。そのような星は、わずかに光を発するが、正規の軌道を逸しているため、ついには、宇宙の暗闇の中に吸い込まれていく。軌道を逸脱した星は、様々な運命をたどる可能性があるそうだ。大きく分けると、他の天体に飲み込まれる、別の天体と衝突する、あるいは「浮遊惑星」になる、といった可能性があるそうだ。
いずれにしても「まっ暗なやみが、彼らのために永遠に用意されています」と永遠のさばきが待ち受けているのである。
14節では、エノクの預言についてふれ、このさばきは創世記時代から既に定められていたことだと告げている。「アダムから七代目のエノクも、彼らについて預言してこう言っています。『見よ。主は千万の聖徒を引き連れて来られる。すべての者にさばきを行ない、不敬虔な者たちの、神を恐れずに犯した行為のいっさいと、また神を恐れない罪人どもが主に言い逆らった無礼のいっさいとについて、彼らを罪に定めるためである。』」(ユダ 14,15)
このエノクの預言と言うのは、聖書外典「エノク書」1:9の引用であると考えられている。エノク書は紀元前1 – 2世紀頃成立したと推定されていて、エノクの預言を記したという黙示書物であり、終わりの日のさばきが描かれている。書かれた当初は広く読まれたらしく、教父達の評価も高いものであったというが、聖典には含まれなかった書物である。その1:9には、こう書かれている。
旧約聖書外典 下 関根正雄編 講談社文芸文庫 p207, p208
「みよ、神は千万の聖者を従えて来る。すべての人をさばき不信者をことごとくほろぼすために。また、神をないがしろにして犯した不信の行為のゆえに 不審な罪人が神にさからって語った雑言のゆえに あらゆる人を罪に定めるために来る。」
ここで、主の来臨は、「彼らを罪に定めるため」とある。
偽の兄弟たちの見分け方
この短い手紙の中に、ユダはいろいろと偽の兄弟たちの特徴を描いてきたが、人間は、元来、罪人である。少し当てはまるからといって、まだ聖められていない部分であるかもしれず、大切なことは罪を犯した後の悔い改めとその結果としての実である。そこを混同してはならない。ユダは、その見分けるため5つの特徴をあげている。「彼らはぶつぶつ言う者、不平を鳴らす者で、自分の欲望のままに歩んでいます。その口は大きなことを言い、利益のためにへつらって人をほめるのです。」(ユダ 16)
- 「ぶつぶつ言う者」
荒野でつぶやき続け、滅ぼされた民のような、不信仰の表れである。神につながる者は、次のみことばを大事にする。「満ち足りる心を伴う敬虔こそ、大きな利益を受ける道です。私たちは何一つこの世に持って来なかったし、また何一つ持って出ることもできません。衣食があれば、それで満足すべきです。金持ちになりたがる人たちは、誘惑とわなと、また人を滅びと破滅に投げ入れる、愚かで、有害な多くの欲とに陥ります。」(Ⅰテモテ 6:6-9) - 「不平を鳴らす者」
「不平を鳴らす」
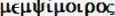 「自分の運命(境遇)についてこぼす,始終不平を言う,不平満々」不平不満を言葉や態度で表すことである。主がなさることを喜べない人である。
「自分の運命(境遇)についてこぼす,始終不平を言う,不平満々」不平不満を言葉や態度で表すことである。主がなさることを喜べない人である。 - 「自分の欲望のままに歩んで」
飽くことを知らず、自分のわきあがる欲望のままになって生活している状態である。 - 「その口は大きなことを言い」
彼らは大言壮語を吐く者、詳訳では、「語るところは高慢〈尊大〉であり」4とある。 - 「利益のためにへつらって人をほめる」
詳訳では、「利を得るためにはだれかれにほめ言葉を言いたてます〈へつらいの賛辞を人々に呈します〉。」5とある。自分にとって益となるためには、人にへつらうことをもする様子である。こういう人たちは、自分の利益、得することしか頭になく、他人をほめていても、自分の益にならないと、そのほめた口で違う実を見せていく。
この5つが顕著に現れていて、悔い改めることもないならば、注意が必要である。しかし、彼らが出現してくることは、前もって使徒たちも言っていたことである。「愛する人々よ。私たちの主イエス・キリストの使徒たちが、前もって語ったことばを思い起こしてください。彼らはあなたがたにこう言いました。『終わりの時には、自分の不敬虔な欲望のままにふるまう、あざける者どもが現われる。』」(ユダ 17,18)そして、ユダは、「この人たちは、御霊を持たず、分裂を起こし、生まれつきのままの人間です。」(ユダ 19)と述べた。
私たちのなすべきこと
このような困難な惑わしの時代に、堅く信仰に立ち続けるには、どうしたらよいのか。かたっぱしから偽者をあばいて、つるしあげていくことではない。もちろん、ユダも偽の兄弟たちをつるしあげるためにこのような厳しい手紙を書いたわけではない。ユダは、この手紙を、羊を守るために書いている。主を愛するゆえにである。主イエスは、主を信じる者たちを、「つまずかないように守ることができ、傷のない者として、大きな喜びをもって栄光の御前に立たせることのできる方」(ユダ 24)である。聖書は言っている。「あなたがたは、自分の持っている最も聖い信仰の上に自分自身を築き上げ、聖霊によって祈り、神の愛のうちに自分自身を保ち、永遠のいのちに至らせる、私たちの主イエス・キリストのあわれみを待ち望みなさい。疑いを抱く人々をあわれみ、火の中からつかみ出して救い、またある人々を、恐れを感じながらあわれみ、肉によって汚されたその下着さえも忌みきらいなさい。」(ユダ 20-23)命令である。ここに、異なる教えがはびこる中で、私たちのなすべきことが7つあげられている。
- 「自分の持っている最も聖い信仰の上に自分自身を築き上げ」
まず先決することは、確固たるイエスという土台の上に、火に焼かれてもなくならない材料で、自分自身を築き上げることである。金、銀、宝石で建てるか、木、草、わらで建てるかということである(Ⅰコリント 3:12)。このことなくしては、何をしても、どのような奉仕をしても、すべてが無駄になる。 - 「聖霊によって祈り」
次に、聖霊による祈りである。自分勝手な祈りではない。これを怠ると、信仰にいのちがなくなってくる。 - 「神の愛のうちに自分自身を保ち」
人のもっている愛というものは偏っていて、神の愛のうちに浸り続けていないなら、枯渇してしまう。他人に流せる光もなくなってしまう。神の愛のうちにとどまり続け、自分自身を保つことが大事である。 - 「永遠のいのちに至らせる、私たちの主イエス・キリストのあわれみを待ち望みなさい。」
自分の罪深さを知っており、神のあわれみを待ち続けることが大切である。苦しみに耐えきれず待つことの限界を自分で決めて動きまわると、惑わしの罠が待ち受けている。耐えきれない時は、神による確信が来るまで祈り続けることが必要である。 - 「疑いを抱く人々をあわれみ」
惑わしの波にのまれて迷っている人に対し、とるべき姿勢は、あわれみをもって接することである。厳しく戒めたり、まして、ののしって追い払ったりすることではない。 - 「火の中からつかみ出して救い」
迷いの中に陥っている人は、滅びの火の中からつかみ出さなくてはならない。ぼやぼやいいかげんに事にあたるなら、大やけどをしてしまう。真剣勝負である。これは真理を知る者の使命である。そのことは、ヤコブ 5:19,20でヤコブも述べていることである。 - 「またある人々を、恐れを感じながらあわれみ、肉によって汚されたその下着さえも忌みきらいなさい。」
罪に陥っている人と接する時は、神への恐れをもって、罪にのまれないように気をつける必要がある。ある人々とは、「一度光を受けて天からの賜物の味を知り、聖霊にあずかる者となり、神のすばらしいみことばと、後にやがて来る世の力とを味わったうえで、しかも堕落してしまうならば、そういう人々をもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。彼らは、自分で神の子をもう一度十字架にかけて、恥辱を与える人たちだからです。」(ヘブル 6:4-6)のような人々である。人に対してはあわれみを持ち、罪そのものは憎めということである。律法に語られている「らい病」(「らい病」と訳されていた ツァラアト は、現代のらい病、ハンセン病とは異なるある種の皮膚病のこと)で汚れた衣服は、汚れたものであり、火で焼かれなければならない、触れてはならないものであった(レビ 13:47-59)。律法の「らい病」は罪を教える型であった。
ツァラアト は、現代のらい病、ハンセン病とは異なるある種の皮膚病のこと)で汚れた衣服は、汚れたものであり、火で焼かれなければならない、触れてはならないものであった(レビ 13:47-59)。律法の「らい病」は罪を教える型であった。
こうしてユダが述べていることは、2000年経った現教会にも必要な教えである。「父なる神にあって愛され、イエス・キリストのために守られている、召された方々へ。どうか、あわれみと平安と愛が、あなたがたの上に、ますます豊かにされますように。」(ユダ 1,2)

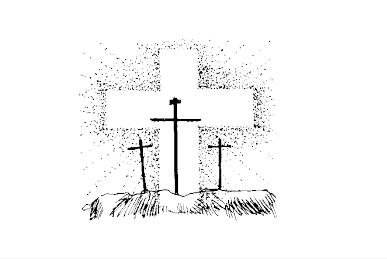


コメント