<– 前の記事:『イエスの教え-会堂で-』
聖書個所:ルカの福音書4章31節~44節(新改訳)
『宣教を開始されたイエス-カペナウムにて-』
前回は、会堂で教え始められたイエスを、故郷ナザレの人々は受け入れず、イエス(神)のことば「まことに、あなたがたに告げます。預言者はだれでも、自分の郷里では歓迎されません。わたしが言うのは真実のことです。…」(ルカ 4:24-)と言われたことに腹を立て、丘の崖の上から投げ落とそうとしたというところまでを見た。そのような激怒し殺意を露わにしている人々を前に、イエスは冷静に彼らの真ん中を通り抜けて立ち去られたのであった。
宣教開始のしるし
荒野(伝承によればヨルダン川西岸地区のエリコの町から11 km西郊外(エルサレムへの方角)にある「誘惑の山」と言われている山)での悪魔の試みの後、イエスがここガリラヤ地方に来られたのは、ヨハネがヘロデに捕らえられたと聞いたことがきっかけであった。(「ヨハネが捕えられたと聞いてイエスは、ガリラヤへ立ちのかれた。」(マタイ 4:12)「ヨハネが捕えられて後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を宣べて言われた。」(マルコ 1:14))ヨハネが捕まったと聞いてガリラヤの田舎に立ち退かれたというのは、ヘロデ王がいるところから遠くに逃げようと身の安全を図ってのことではない。メシアの道備えを担っていたヨハネの働きの終わりは、メシアが本格的な働きに入ることのしるしを意味していた。「これ(イエスがゼブルンとナフタリとの境にあるガリラヤへ立ちのかれたこと)は、預言者イザヤを通して言われた事が、成就するためであった。すなわち、『ゼブルンの地とナフタリの地、湖に向かう道、ヨルダンの向こう岸、異邦人のガリラヤ。暗やみの中にすわっていた民は偉大な光を見、死の地と死の陰にすわっていた人々に、光が上った。』この時から、イエスは宣教を開始して、言われた。『悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。』」(マタイ 4:14-17)ヨハネがこの世を去ることは、メシアとしての宣教開始の合図であった。
こうして、ナザレに来られ、会堂で教えを始められたイエスであったが、ナザレの人々は、罪を指し示すイエスのことばを拒み、イエスを殺そうとしたのであった。
カペナウムで宣教開始
ナザレを立ち去られたイエスは、カペナウムの町に行かれた。「それからイエスは、ガリラヤの町カペナウムに下られた。そして、安息日ごとに、人々を教えられた。」(ルカ 4:31)カペナウムの町は、ナザレから45Kmほど北東にある町である。「下られた」とあるが、ナザレは標高400mほどの丘陵地帯にあり、ガリラヤ湖畔にあるカペナウムは海抜マイナス180mほどにある(標高差は約580m)町である。徒歩10時間以上かかる距離にあり、ともにガリラヤ地方の町である。宣教を開始するためにガリラヤに来られたイエスは宣教の場を、生まれ故郷ナザレではなくカペナウムに移された。ナザレの人々が、神の悔い改めの機会を拒み、神のことばを預かって語った者(イエス)を拒んだからであった。カペナウムに入られたイエスは、ナザレでなされたように、安息日ごとに、会堂で人々を教えられた。ナザレでの出来事を意に介さず、メシアとしての働きをなされる主の姿がある。
「人々は、その教えに驚いた。そのことばに権威があったからである。」(ルカ 4:32)ナザレでもカペナウムでも同じように語り、人々を教えるイエス。「生まれた時から私たちのそばで同じように育ち、成長を見てきた」というナザレの人々のような先入観がないカペナウムの人々は、素直にその教えに驚き、イエスのことばの権威に触れた。こうして、イエスは、本格的な宣教を始められた。
悪霊の追い出し
「また、会堂に、汚れた悪霊につかれた人がいて、大声でわめいた。『ああ、ナザレ人のイエス。いったい私たちに何をしようというのです。あなたは私たちを滅ぼしに来たのでしょう。私はあなたがどなたか知っています。神の聖者です。』」(ルカ 4:33-34)会堂にいた「汚れた悪霊につかれた人」、この人が会堂にいたのは、神を求めて(神を礼拝するため)であった。彼がいつも大声でわめいている人であり、「汚れた悪霊につかれた人」と周囲に認知されていたなら、会堂には入れなかっただろう。イエスの権威に触れ、突然大声でわめき出したのである。わめき出したのは、彼の意志ではなく、悪霊のしわざであった。彼の人生に何があったのかはわからないのだが、汚れた悪霊がその人についていた。明らかにその人ではない、別の位格(ペルソナ)が現われていた。人と悪霊は区別(判別)できるものであり、区別(判別)して当たらなければならない。それを一緒くたに扱うことは、つまずきをもたらす。わめきながら放たれた言葉「あなたは私たちを滅ぼしに来た、あなたは神の聖者です」という言葉は本当のことであった。悪霊(神に敵対する霊)につかれた人は、時に神について本当のことを語る。が、いくら本当のことを語っていても、その行いの目的は神の働きを妨げるものである。
使徒の働き16章に出てくる占いの霊につかれた若い女奴隷もそうであった。彼女は、パウロとルカたちのあとに幾日もついてまわり、「この人たちは、いと高き神のしもべたちで、救いの道をあなたがたに宣べ伝えている人たちです。」(使徒 16:17)と叫び続けていた。このことに、困り果てたパウロが、キリストの御名によって悪霊を追い出したのであった。
「イエスが、(新改訳では「彼を叱って」、口語訳では「これをしかって」)『黙れ。この人から出て行け』とお叱りになると、悪霊はその男を人々の中に投げ倒し、何の傷も負わせずに出て行った。」(ルカ 4:35〈新共同訳〉)イエスが叱り命じると、悪霊は、人々に害を与えることなしにその人から出ていった(退散した)。イエスは悪霊を叱って追い出された。叱る根底には、愛による怒りがあった。「怒っても、罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。」(エペソ 4:26,27)とあるが、怒りを感情のままたれ流していけば罪につながっていくが、愛による怒りは、必要がある怒りである。(「怒っても」の怒りは 
 (挑発する、怒りをかき立てる、怒りを起こされる、怒る、憤る)であるが、挑発し怒りを起こさせ、罪に誘う存在がいることを忘れてはならない)
(挑発する、怒りをかき立てる、怒りを起こされる、怒る、憤る)であるが、挑発し怒りを起こさせ、罪に誘う存在がいることを忘れてはならない)
悪霊の追い出しは、信じる者に伴うと言われ、与えられたしるしである。「それから、イエスは彼らにこう言われた。『全世界に出て行き、すべての造られた者に、福音を宣べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は、救われます。しかし、信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のようなしるしが伴います。すなわち、わたしの名によって悪霊を追い出し、新しいことばを語り、蛇をもつかみ、たとい毒を飲んでも決して害を受けず、また、病人に手を置けば病人はいやされます。』」(マルコ 16:15-18)霊的存在である神が存在するのだから、悪霊も存在し、悪霊につかれる人々も存在する。病原菌が存在し、それに対する免疫がないならば、病気になる。悪霊が存在し、それに対する防御法を知らなければ、悪霊につかれることがある。人は、手に負えない物事を恐れ、排除しようとする傾向があり、「悪霊」もなかったことにしたいのだが、聖書にはっきりと書かれている存在である。恐れは、愛からは出てこないものである。(「愛には恐れがありません。全き愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。恐れる者の愛は、全きものとなっていないのです。」(Ⅰヨハネ 4:18))信仰によって行う神にある行為の根底にあるのは、愛である。イエスは、会堂にいた「汚れた悪霊につかれた人」をあわれみと愛に満ちた心で、「彼」という人ではなく「悪霊」に向かって叱り命じられた。これを愛もない状態で人に向かってやみくもに、勘違いした権威によって命じるなら、去っていくのは、「悪霊」ではなく、命じられた「人」となる。
1990年代にペンテコステ派を通じて、悪霊の追い出しの教えがブームのように訪れたことがあった。「イエスの御名によって、悪霊よ、出ていけ」と命じれば、悪霊は出ていく、というイエスの御名による力の伝道の実践の教えであった。聖書では、イエスや使徒は、宣教の場面で悪霊を追い出す必要に多々直面し、実践していた事柄であるので、「悪霊の追い出し」も別に誤った行為ではないのだが、実践する人側に問題が見受けられ、侮蔑や非難、分裂、カルト化を招くこととなった。権威を得たようなふるまいをする者や、判別なく呪文のように唱える人たちが出てきたのは、聖書を読み取っての指導者の教育の問題であった。「悪霊につかれた人」や「病気を抱えている人」の苦しみをあわれみ、「愛」に基づいて、力ある働きを実行していたなら、つまずきは避けられただろう。間違いではない神の真理を語っていても、それをどのように使うかによって、悪(サタン)の手先にもなりうるのである。「愛」である神に基づかない教えは、それが真理であっても、良くない実によって、真理をも否定されてしまいかねないことになるから困りものである(否定しようとしても真理はゆるがず、時代を経ても残るのであるが)。
イエスは、安息日ごとに教えられていた会堂で、悪霊を追い出されたのだが、汚れた悪霊がついていた人の悪霊のわざも神の栄光につながっていったのである。悪霊はその男を会衆の真ん中に投げ倒して〈詳訳聖書1〉出ていった。イエスの権威を会衆の真ん中で示すことになったのであった。
言葉一つで悪霊が出ていくというこれまでに見たこともない権威を目の当たりにし、「人々はみな驚いて、互いに話し合った。『今のおことばはどうだ。権威と力とでお命じになったので、汚れた霊でも出て行ったのだ。』」(ルカ 4:36)イエス(神)の権威は、支配するための権威ではない。人々を救い、各々をしあわせに導く「わざわいではなくて、平安を与え、将来と希望を与えるための」(神の)計画(エレミヤ 29:11)に従う道を教え導くための愛に基づく権威である。悪霊の追い出しは、その一環にすぎない。他に対しマウントを取るためのものではないのだが、目に見える現れは、高ぶりに陥りやすいもので、周囲につまずきを起こすことになるので、注意が必要である。
私が知っている悪霊の追い出しを乱発していた指導者の例を2つ上げる。
・母親に明らかに霊的な現象が見られると言って、ある夫婦が、ある悪霊の追い出しの専門家を名乗っている指導者を頼った。その指導者は、相談者の話に耳を貸さず(愛の欠落)、手っ取り早く追い出しにかかり、何の変化もないのに、「悪霊は出ていきました」と締めくくり(判別できていない)、えっ?ととまどう夫婦の言葉にも耳を貸さずに、その場を閉めくくり、帰した。その後のその人の状態は、その行為によって悪化したのだが、その指導者は関知することはなかった。
・とある地方の聖会にて、集会が終わって外にいると、「娘が悪霊につかれていて…」と疲れ果てたような母親が娘を連れてやって来た。「日本の君(悪霊の頭)」と戦って勝利したと言って悪霊の追い出しを語っていた指導者は、来ていた人々に囲まれ、頼まれるままに手を置いて祈っていた。母親の要望を聞いたあるスタッフが、母娘の必要のほうが必要性が高いと思われたので、指導者の元に連れていった。すると、その指導者は暗く疲れたような顔つきとなり、少し手を置いて少し祈ったのだが、何の変化も熱情も表さないまま、あれっ?という感じで、対応を終えてしまい、指導者は時間がないと言って他の信奉者のところへ行ってしまった。あの母娘もあとが大変だったのではなかろうか。
何のために、追い出しを試みているのか、真剣に求める信者を気落ちさせるためなのだろうか。愛は捏造できないものである。口で愛を語っていても、実際にその場にいると、メッキならば剥がれていくのが愛である。メッキではない愛はイエスから流れる。イエスは、決して見放すことはない。
評判になったイエス
「こうしてイエスのうわさは、回りの地方の至る所に広まった。」(ルカ 4:37)イエスの力ある働きは、うわさとなって、周囲の地方の至る所に広まっていった。悪を制し、権威ある聖い教えが喜びと共に広がっていく、神の国の訪れである。
「イエスは立ち上がって会堂を出て、シモンの家にはいられた。すると、シモンのしゅうとめが、ひどい熱で苦しんでいた。人々は彼女のためにイエスにお願いした。」(ルカ 4:38)シモンが使徒として召命された記事は、カペナウムの宣教開始(マタイ 4:13-, マルコ 1:21-, ルカ 4:31-)の前に書かれているものと(マルコ 1:16-)、後に書かれているものがある(マタイ 4:18-, ルカ 5:1-)。その順番はともかく、シモンやその兄弟アンデレやゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネは、ガリラヤ湖で漁師として魚を取っていた時に、イエスから声をかけられ、すべてを捨ててイエスに従ったという使徒としての召命の記事が3つの福音書に書かれている。
それとは別、ヨハネの福音書の1:35-には、シモンが初めてイエスに会った記事がある。まだバプテスマのヨハネがヘロデに捕らえられていない頃の話である。まず、ヨハネの弟子であったシモンの兄弟アンデレが、もう一人の弟子とともに、ヨハネの言葉を聞いて、イエスについて行ったのが発端であった(ヨハネ 1:35-37)。ついて来るアンデレたちにイエスが言葉をかけた。「あなたがたは何を求めているのですか。」と。「ラビ(訳して言えば、先生)。今どこにお泊まりですか。」(ヨハネ 1:38)と答えるアンデレたちに、イエスは、ご自身の泊まっている所を教え、十時ごろ(ユダヤ方式の時刻で16時ごろ)からその日を過ごした(ヨハネ 1:39)。イエスのところを出たアンデレはまず兄弟シモンのところへ行って、「私たちはメシヤ(訳して言えば、キリスト)に会った。」(ヨハネ 1:41)と告げた。アンデレもシモンもメシア(メシヤ)を心から待ち望んでいたのだろうことが伺えるくだりである。それからアンデレは、シモンをイエスのもとに連れていき、イエスはシモンに目を留めて、ケパ(訳すとペテロ)という名前を授けられたのであった(ヨハネ 1:42)。
そういう関係性が出来ていて、会堂での働きを終えられたイエスは、シモンの家にはいられたのであった。すると、シモンのしゅうとめが、ひどい熱で苦しんでいたのである。「ひどい熱で苦しんでいる」医者であるルカの描写である。人々は彼女のためにお願いした。人々に頼まれなくても、イエスはお癒しになっただろうが、「人々は彼女のためにイエスにお願いした。」という一文が入っている。この一文に、人々の彼女への愛が見えるようだ。愛によって形成されていく神の子たち。
力ある宣教
「イエスがその枕もとに来て、熱をしかりつけられると、熱がひき、彼女はすぐに立ち上がって彼らをもてなし始めた。」(ルカ 4:39)先ほどの会堂にいた汚れた霊と同じように、熱をしかりつけられたイエス。医者であるルカが記している。この熱は、普通の病気の熱ではなかったような描写である。会堂での働きの後、シモンのしゅうとめがイエスをもてなそうとしていた、このタイミングでの高熱である。悪霊によるものだとイエスは見抜いておられた。イエスが熱をしかると、汚れた霊のごとくに熱は去り、何事もなかったかのように、彼女はすぐに立ち上がって、人々をもてなし始めたと。「熱をしかると熱がひいた」という医学では考えられない方法をイエスはなされたのである。しかも、高熱による消耗も見られず、すぐに活動しているのである。
「日が暮れると、いろいろな病気で弱っている者をかかえた人たちがみな、その病人をみもとに連れて来た。イエスは、ひとりひとりに手を置いて、いやされた。」(ルカ 4:40)ひどい熱が、イエスの権威で、言葉一つで後遺症もなく癒されたといううわさは、瞬く間に広がって行き、癒しを必要としている病人を連れた人々が大勢、イエスのもとにやって来た。この日は安息日(会堂で教えられた)であったため、日暮れまで待ち、安息日が明けた日暮れにすぐにやってきた人々。イエスは、ひとりひとりに手を置いて、いやされた。みもとに来た人を拒まず、「時間がない、また明日ね」とは言わないイエスの愛である。
「また、悪霊どもも、『あなたこそ神の子です。』と大声で叫びながら、多くの人から出て行った。イエスは、悪霊どもをしかって、ものを言うのをお許しにならなかった。彼らはイエスがキリストであることを知っていたからである。」(ルカ 4:41)悪霊が話す真実は、真実を悪いことに用いようとするためであり、真実を悪いことに思わせ、歪ませてしまう効果をもたらす。「あなたこそ神の子です。」と大声で叫びながら出ていく狙いは何か。イエスは、「うんうん、わたしが神の子であることは事実だ」と見過ごさずに、すべてを見抜いておられ、悪霊どもをしかりつけ、ものを言うことを許されなかった。前回の教会シリーズのメッセージ2で、「ライプツィヒ討論会」でルターを誘導し、異端としての言質をとったヨハン・エックにも見られたが、事実を悪用するのが、悪の常套手段だ。
「彼ら(悪霊ども)はイエスがキリストであることを知っていたから、イエスは、悪霊どもをしかって、ものを言うのをお許しにならなかった。」というのは、イエスがキリストであることを知っていて、この事実を広めれば、世の混乱をもたらし、ローマの圧力も加わり、イエスの宣教ができなくなるとでも考えていたのではなかろうか。
宣教の目的
「朝になって、イエスは寂しい所に出て行かれた。群衆は、イエスを捜し回って、みもとに来ると、イエスが自分たちから離れて行かないよう引き止めておこうとした。」(ルカ 4:42)人々への病の癒しや悪霊を追い出しに、肉体において疲れ切っていただろう。朝になって、神のみもとで静まり、安息を取ろうとしてのことだろう、イエスは、寂しい所に出て行かれた。ところが、群衆は押し寄せ、イエスを捜し回り、イエスを見つけると、自分たちから離れて行かないよう引き止めておこうとしたのであった。朝になっても、人々は絶え間なく押し寄せていたようだ。
「しかしイエスは、彼らにこう言われた。『ほかの町々にも、どうしても神の国の福音を宣べ伝えなければなりません。わたしは、そのために遣わされたのですから。』」(ルカ 4:43)イエスには、カペナウムだけのラビで納まるわけにはいかない使命がある。限られた日々の中で、多くのユダヤの町々に神の国の福音を宣教しなければならない。こういう状況下で、病人の癒しのためではなく、自分たちから離れて行かないように引き留めようとする群衆に、言ったイエスの言葉である。
イエスは、「悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。」と宣教を始められたが、罪を気付きもしない人々に対し、直接的に罪を告げてはいない。婉曲な言い回しで、自身の罪を気付かせようとされている。悔い改めは、人に指摘されてできるものではない。外面的に悔い改めの方向にコントロールされても、真の心からの悔い改めには至らない。ナザレの人々の態度(神の言葉を預かった者の言葉に驚きながらも、「この人はヨセフの子(ただの大工のせがれ)ではないか」とあざけった行為)に対しては、旧約の例を出しつつ、預言者を退けることの罪に気付くようにと働き、今回のカペナウムの群衆には、他の町々に必要があることを告げて、自己中心的な思いに気付きを与えようとされている。神の光に照らされて、自身の闇を知り、悔い改めるよう、イエスは神の国を説かれた。
「そしてユダヤの諸会堂で、福音を告げ知らせておられた。」(ルカ 4:44)カペナウムで反響を受け始まったイエスの宣教は、ユダヤ中に行きわたらせるよう、イエスは、この後、諸会堂を巡られ、福音を告げ知らせていった。
悔い改めは、神と人との関係の中で起こる。罪を知るのも、人からではなく、神との関係の中のことである。いかに神から離れ、自分勝手な道を歩んでいるのかを知るところに、罪の自覚がある。罪の語源は 
 (的外れ。善いものとして造られた人間の本来進むべき神の方向から外れている状態)である。愛する神の愛を信じて、歩んでいこう。
(的外れ。善いものとして造られた人間の本来進むべき神の方向から外れている状態)である。愛する神の愛を信じて、歩んでいこう。
–> 次の記事:『イエスのもとに来る人々-主の選び-』
- 詳訳聖書-新約-, いのちのことば社発行 P149 ↩︎
- 「宗教改革時代へ~罪との闘い」 ↩︎

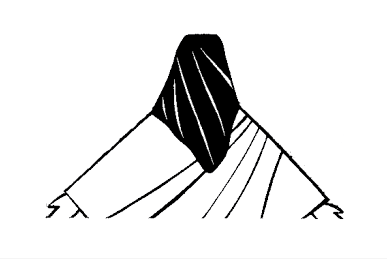



コメント