<– 前の記事:『悪魔の誘惑-示された威光-』
聖書個所:ルカの福音書4章15節~30節(新改訳)
『イエスの教え-会堂で-』
会堂で教え始められるイエス
ヨハネからバプテスマを受けられた後、荒野で悪魔の試みにあわれ、悪魔を退けられたイエスはガリラヤに帰られ、周囲の地方一帯にイエスの評判が広まった、前回は、そこまでを見た。
その後「イエスは、彼らの会堂で教え、みなの人にあがめられた。」(ルカ 4:15)「彼らの会堂」は、口語訳、新共同訳では「諸会堂」となっている。「そしてイエスご自身は、諸会堂で〈連続の〉教えをし、すべての人によって承認〈尊敬〈賞賛〉を受けられた。」(詳訳聖書-新約-, いのちのことば社発行 P148)ガリラヤに帰られ、評判となったイエスは、その超越した知恵により、必然的に諸会堂で教えるラビ(先生、師)となった。
シナゴーグでの礼拝
ユダヤ人の諸会堂で当時行われていた日々の礼拝順序や正確な内容が、どのようなものであったかの詳細は不明であるのだが、神殿時代に毎朝夕に捧げられていた子羊の生贄(コルバン・タミード)は、この時代では諸会堂での礼拝に変わっていた。バビロン捕囚によって神殿が崩壊した後は、トーラー(モーセ五書)の学習とその実践を至上価値としたラビ・ユダヤ教が発展し、ラビたちは神殿供犠をシナゴーグ(会堂)での祈祷を中核とする礼拝へと転化させていた(すなわち、ユダヤ教という宗教となった時点でいけにえより、律法が中心となっていた)。こうして祭壇に奉納する燔祭(全焼のいけにえ)に代わり、人間の心と体を神に捧げる祈祷が罪を贖い、神との関係を維持する媒介となっていった。ユダヤ教の礼拝において祈祷は個人が自由に唱えるものではなく、聖書の章句を組み合わせた定型文を唱えることで唯一の神ヤハウェへの信仰と献身を表明する行為となっている。
【ユダヤ教の基盤ミシュナとタルムード】
ラビたちは、トーラーの成文律法の他に、モーセからラビに伝えられたとされる口伝律法を形成していた。紀元200年頃にその口伝律法を体系的に整理したものが「ミシュナ」であり、その後、ミシュナの各節についての学者たちの議論と解釈を記録した「ゲマラ」という注釈を加えてタルムードが編纂された。ミシュナもタルムードも、現在も使われていて、ヘブライ語(旧約)聖書に継ぐユダヤ教の重要な聖典となっている。「ゲマラ」の作成はパレスチナ(エルサレム)とバビロニアの2つの地域で行われ、4世紀末にエルサレム・タルムード、6世紀までにバビロニア・タルムードが成立している。ミシュナは、6つの区分(①ゼライーム「法」11編構成、②モエード「祭事」12編構成、③ナシーム「女性」7編構成、④ネズィキーン「損害」10編構成、⑤コダシーム「聖事」11編構成、⑥トホロート「清め」12編構成)に分かれていて、それぞれの編がさらにいくつかの章に分かれた構成になっていて、律法の規定や解釈を具体的に示しており、ユダヤ教徒の日常生活や宗教儀礼における行動規範となっている。
祈りと祝福・什一税・農業に関する法を扱っている①ゼライームに、ベラホートという9章からなる祈りの言葉の規則について書かれている個所があり、その4章1節で、「朝の祈りは正午までに(ささげるべきである)。ラビ・ユダはいう、第四時※までに。・・・」(※午前十時頃)(ミシュナ ベラホート, エルサレム文庫 石川耕一郎訳 p28)と、1日朝昼夕と3回祈祷を唱えることが定められ、このように行動規範として細かく定められている。
【ユダヤ教の日々の礼拝】
礼拝は、①早朝に行われるシャハリト(夜明け)、②午後に行われるミンハ((穀物からなる)供物、贈物)、③夕方以降に行われるマアリヴ(夕刻)があり、行われる時間帯によって行われる内容が異なっていた。礼拝は、詩篇を含む抜粋した聖書の章句およびシェマ(聞け、イスラエルよ)の朗唱、アミダー(祈祷)の朗唱、また、月曜と木曜には各週のトーラー指定個所の朗読がなされる。
シェマは、「聞け、イスラエルよ」で始まる申命記6:4-9、11:13-21、民数記 15:37-41の3つの聖句からなり、ヤハウェへの信仰を記憶し、律法を固く守ることを刻み付けることを復唱させていた。こうして「家にすわっているときも、道を歩くときも、寝るときも、起きるときも、これを唱えなさい。」(申命記 6:7)の実践を教えていた。シェマは、最も重要な祈祷とされ、ヤハウェへの信仰告白であると同時にその信仰の根幹をなしているものとされ、すべてのユダヤ人は1日に2回(朝夕)唱えることが定められている。
アミダー(Amidah)は「立つ」という意味のヘブル語を由来とする言葉で、18の定型からなる祈祷文であり、起立して朗唱するため、「立祷」を意味する「アミダー」と呼ばれる。アミダーは、1日3回朝昼夕の礼拝で朗唱される。
トーラーの朗読(クリアット・トーラー)もまた、礼拝の重要な要素である。月曜と木曜のシャハリト(ユダヤ教の朝の祈りのことで、日々の生活において非常に重要な儀式とされている)に、その週の指定朗読個所の最初の章句の朗読が定められている。朗読者による抑揚のついた朗読の前後に、祭司、レビ人、信徒イスラエルの出自を持つ3名が指名され、タリト※1を着用しトーラーの巻物※2が置かれた説教台上で祝祷を朗唱する。※1 https://ja.wikipedia.org/wiki/タッリート に写真あり
【参考文献】ユダヤ文化事典 日本ユダヤ学会編 編集代表:市川裕 p174
※2 https://ja.wikipedia.org/wiki/トーラー に写真あり
以上は、日々の礼拝についてであったが、安息日(金曜の日没から土曜の日没まで)はヤハウェへの賛美によって聖別する日であり、神の言葉であるトーラーを学ぶ日でもあり安息日の礼拝が行われた。
【ユダヤ教の安息日礼拝】
【参考文献】ユダヤ文化事典 日本ユダヤ学会編 編集代表:市川裕p79, p179
金曜の日没にシナゴーグで安息日を迎える礼拝が行われ、安息日を迎える一連の歌が歌われる。土曜の早朝にもシナゴーグで礼拝が行われ、祈祷のほかにその週の安息日に定められたトーラーの朗読個所および預言書の朗読個所を朗読する。礼拝では、その週のトーラー朗読個所に基づく説教を行い、神の言葉について耳を傾け、思索する。トーラーの朗唱は、パレスチナ(エルサレム)基準では3年周期、バビロニア基準では1年周期で全体が朗唱されるように取り決められている。
【ユダヤ教の聖書】
【参考文献】ユダヤ文化事典 日本ユダヤ学会編 編集代表:市川裕p78
ユダヤ教の聖典のヘブライ語聖書は、トーラー(モーセ五書)、ネヴィイム(預言者〈「前の預言者」と呼ばれる歴史書と「後の預言者」と呼ばれる預言者の書〉、クトゥヴィム(諸書)の3部から成り、それぞれの頭文字TNKから合成した語Tanak(タナハ)とも呼ばれている。主イエスが来られた時代は、既にトーラーとネヴィイムの権威は確定していた(クトゥヴィムが正典になったのは、不明な点が多いのだが、もっと後の時代であった)。イエスの時代は、モーセ五書と歴史書、預言者の書を聖典としていた時代、ミシュナができる前の口伝律法の時代ではあるが、ミシュナにまとめられた内容を行っていた時代であった。
会堂で宣教を開始されたイエス
「それから、イエスはご自分の育ったナザレに行き、いつものとおり安息日に会堂にはいり、朗読しようとして立たれた。」(ルカ 4:16)イエスの時代の会堂礼拝の内容はどのようになされていたのかはわからないが、上述したミシュナで規定されたものに近い内容である。ラビとなられたイエスは、いつものとおり会堂に入られ、聖典を朗読しようとして立たれた。朗読と説教は居合わせた祭司、レビ人、ラビに優先的に提供されていたようである(新聖書註解 新約1 いのちのことば社発行 p338)。
「すると、預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いて、こう書いてある所を見つけられた。」(ルカ 4:17)その週の安息日に定められた正典の個所はイザヤ書だったようである。イザヤ書を渡されたイエスは、61章1,2節を開かれた。「わたしの上に主の御霊がおられる。主が、貧しい人々に福音を伝えるようにと、わたしに油を注がれたのだから。主はわたしを遣わされた。捕われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために。しいたげられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。」(ルカ 4:18,19)(「神である主の霊が、わたしの上にある。主はわたしに油をそそぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者をいやすために、わたしを遣わされた。捕われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年と、われわれの神の復讐の日を告げ、すべての悲しむ者を慰め、」(イザヤ 61:1,2))この個所を開き、イエスは公にご自身が来られた目的を告げられたのであった。イエスが、ヨハネのバプテスマを受けられた時、天が開け、聖霊がイエスに下り、天から「あなたは、わたしの愛する子、わたしはあなたを喜ぶ」という声があった(ルカ 3:21.22)。神の霊が下った人イエスが、「貧しい人々に福音を伝えるようにと」いう目的の下、神に遣わされてきたということを示す聖句であった。「捕われ人には赦免を」の赦免と訳された語は 
 (解放、釈放、ゆるし、赦免)であるが、イザヤ書にある「解放」のヘブル語
(解放、釈放、ゆるし、赦免)であるが、イザヤ書にある「解放」のヘブル語 
 (ペカハ・コーアハ)は、この個所のみに使われている珍しい言葉で「目を開く」という意味を持っていることばである。
(ペカハ・コーアハ)は、この個所のみに使われている珍しい言葉で「目を開く」という意味を持っていることばである。
イスラエルでは、レビ記25章の律法に基づいて、安息という概念に基づきヨベルの年という捕らわれからの解放が設けられていた。安息の年7年を7回繰り返した翌年の50年目に、角笛が吹き鳴らされ、国中のすべての住民に解放が宣言され、土地の安息、負債の免除、奴隷の解放などが行われた。自由と解放がもたらされる神の恵みの年であった。こういった解放の概念が根付いているイスラエルの社会に、イエスは、罪に捕われ抜け出せないでいる捕らわれの人々に赦免を、真理が見えていない盲人には目の開かれることを告げ、しいたげられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために来られたのである。
「イエスは書を巻き、係の者に渡してすわられた。会堂にいるみなの目がイエスに注がれた。」(ルカ 4:20)聖句を朗唱したイエスは、イザヤの巻を戻し、会堂にいるみなは続く説教を待っていた。聖句は立って、説教はすわってなされたようである。
「イエスは人々にこう言って話し始められた。『きょう、聖書のこのみことばが、あなたがたが聞いたとおり実現しました。』」(ルカ 4:21)このようにイザヤ書61章1,2節に書かれている預言の解放の福音のことばが実現したことをガリラヤの会堂にいた皆に伝えられたのであった。イエスの説教を聞いたみなは、「イエスをほめ、その口から出て来る恵みのことばに驚いた。」(ルカ 4:22a)とある。どんな内容をどのくらい語られたのか、書かれていないが、神の霊が宿った説教である。聞いてみたいと思っても現在では実際に聞けないような恵まれた内容が語られているのだが、当時の人々は知る由もない。イエスの恵まれるメッセージを聞いているのだが、それでも、聞く側は、恵まれながらも、その人の求め、位置、態度によって、様々な応答をするものである。神の恵みは低いところに流れる性質を持つ。(「神は、高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになる。」(ヤコブ 4:6)「神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。」(Ⅰペテロ 5:5))
イエスのメッセージへの会衆の応答
イエスの故郷ガリラヤの人々は、恵みのことばに驚いていたのだがこう言った。「この人は、ヨセフの子ではないか。」(ルカ 4:22b)これがただの素朴な疑問だったら、この後のイエスとのやり取りは違ったものになったことだろう。ただの疑問の言葉でないことは、次のイエスの言葉からわかる。信仰を阻む言葉である。「彼らは言った」(ルカ 4:22b)とあるように、一人の特定の人が言ったのではない。イエスをほめた「みな」(ルカ 4:22b)である。心から神を礼拝する心を持って聞いていたなら、イエスの語る言葉を聞けることが、どれだけ恵まれた事かを悟ったであろう。この言葉に、イエスは次のように返された。「きっとあなたがたは、『医者よ。自分を直せ。』というたとえを引いて、カペナウムで行なわれたと聞いていることを、あなたの郷里のここでもしてくれ、と言うでしょう。」(ルカ 4:23)「医者よ。自分を直せ。」は、ラテン語で、Medice, cura te ipsum.(メディケ・クーラー・テー・イプスム、医者よ、自分自身を治せ)という紀元前6世紀の古典文献にも見られるような知られていたことわざである。イエスは、この時、すでにカペナウム(ガリラヤ地方の町でナザレの北西のガリラヤ湖畔にある町)で何らかの奇蹟を行っていて、そのうわさが広まっていたようだ(イエスは、これより前にカナの婚礼の際に水をブドウ酒に変える奇蹟を最初のしるしとして行われ、その後、母や兄弟たちや弟子たちといっしょに、カペナウムに少し滞在されたことがあった(ヨハネ 2:1-12))。婉曲的に「この人は、ヨセフの子ではないか。」という言葉にある高ぶりに気付くようにと語られたようである。大工のせがれヨセフの息子であるあなたに、神の霊が注がれているというならば、郷里のここでもカペナウムで行ったような奇蹟のみわざをやってみろ、と言わんばかりの心をイエスは見抜いておられた。「あなたの郷里のここでもしてくれ」は、まるで、「あなたが神の子なら・・・」(ルカ 4:3)と荒野で誘惑したサタンの言葉のようである。罪の奴隷になっていると、サタンに似た言動をしてしまう。そこから解放されるには、そのことに気付いて、へりくだった心をもって、「悔い改めなさい。天の御国が近づいたから」と言われるイエスのもとに来て(マタイ 4:17)、悔い改めて神に立ち返ることである。「きっと…言うでしょう」という言い方をされているが、予知されての言葉で、実際にそのように言おうとしていたのだろう。
イエスは、また、こう言われた。「まことに、あなたがたに告げます。預言者はだれでも、自分の郷里では歓迎されません。わたしが言うのは真実のことです。エリヤの時代に、三年六か月の間天が閉じて、全国に大ききんが起こったとき、イスラエルにもやもめは多くいたが、エリヤはだれのところにも遣わされず、シドンのサレプタにいたやもめ女にだけ遣わされたのです。また、預言者エリシャのときに、イスラエルには、らい病人がたくさんいたが、そのうちのだれもきよめられないで、シリヤ人ナアマンだけがきよめられました。」(ルカ 4:24-27)神が遣わされた者のことばを聞いて恵みを感じながらも、受け取ろうとせず、郷里でも奇蹟をしてみろという心根を、エリヤやエリシャなどの預言者たちを受け入れず、罪を重ねて滅びの道に向かったイスラエルの民の罪に重ねて告げられたのである。イエスは、ご自身を預言者の位置において言われたのだが、預言者どころか神であられるイエスが神のことばを預かっているという真実を告げられただけである。自身を神または神の預言者とするイエスと、イエスを信じず「この人は、ヨセフの子ではないか。」という者とどちらが高慢か、イエスに悪いところがあって立派に見せようと神の名を使った発言をしたのならば、神を冒涜する高ぶりと言えるだろうが、イエスは神でありイエスに全く悪(罪)はなかった。
北イスラエルでアハブが王であった時―アハブはイゼベルをめとり、バアルの祭壇ややアシェラ像を造った王である、バビロン捕囚より約300年ほど前の話である―、エリヤが預言者として立てられ、アハブに「私の仕えているイスラエルの神、主は生きておられる。私のことばによらなければ、ここ二、三年の間は露も雨も降らないであろう。」(Ⅰ列王 17:1)と告げたことによって、大ききんが起こった。アハブ王から身を隠すよう、神からの指示で、エリヤは川のほとりに身を隠した。「ここを去って東へ向かい、ヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに身を隠せ。そして、その川の水を飲まなければならない。わたしは烏に、そこであなたを養うように命じた。」(Ⅰ列王 17:3,4)川の水が枯れた時、主なる神は、「さあ、シドンのツァレファテに行き、そこに住め。見よ。わたしは、そこのひとりのやもめに命じて、あなたを養うようにしている。」(Ⅰ列王 17:9)と言われ、エリヤは、ツァレファテのやもめのところに身を寄せ、尽きないかめの粉とつぼの油の奇蹟をもって神に養われた。ある日、やもめ女の息子が非常に重い病気にかかり死んでしまった。その時、エリヤは主に祈り、祈りが聞かれて、息子は息を吹き返したことがあった。イエスの言葉を見るに、この時、アハブ王の手からエリヤをかくまうことのできる神の目にかなった人物は、イスラエルにはいなかったようである。「それから、かなりたって、三年目に、次のような主のことばがエリヤにあった。『アハブに会いに行け。わたしはこの地に雨を降らせよう。』」(Ⅰ列王 18:1)ルカの記述によると三年六か月後に、エリヤはアハブに会いに出かけ、イスラエルを聖めた。カルメル山に全イスラエルと、イゼベルの食卓につく四百五十人のバアルの預言者と、四百人のアシェラの預言者とを集め対決をしたのである(Ⅰ列王 18:19)。主の火が下ってエリヤが勝利し、民はみな、これを見て、「主こそ神です。主こそ神です。」と言ってひれ伏し、バアルの預言者たちは捉えられ殺された(Ⅰ列王 18:39,40)。
また、エリヤの時代の後のエリシャの時代に、アラムに「らい病」(「らい病」と訳されていた  ツァラアト は、現代のらい病、ハンセン病とは異なるある種の皮膚病のこと)にかかっていたナアマンという王の将軍がいた。アラムが略奪した際に、イスラエルの地から捕らえて連れてきたひとりの若い娘が、ナアマンの妻に仕えていた(Ⅱ列王 5:1,2)。その娘が、女主人に「もし、ご主人さまがサマリヤにいる預言者のところに行かれたら、きっと、あの方がご主人さまのらい病を直してくださるでしょうに。」と告げた(Ⅱ列王 5:3)。そう聞いたナアマンはエリシャのもとを訪れ、エリシャが言った言葉に従って、ヨルダン川に行って7たび身を洗った結果、彼のからだは元どおりになって、幼子のからだのようになり、きよくなったのであった(Ⅱ列王 5:14)。その前の章で、エリシャは、子供がなかったシュネムの女に子供を授け、何年か経って急死した子供を生き返らせる奇蹟を起こしているし(Ⅱ列王 4:8-37)、その他にもいくつかの奇蹟が記されている(Ⅱ列王 4:1-7, 38-44)。「らい病人」であったからということでナアマンを癒されたのではない。「また、預言者エリシャのときに、イスラエルには、らい病人がたくさんいたが、そのうちのだれもきよめられないで、シリヤ人ナアマンだけがきよめられました。」イスラエルの人々は神を求めて誰も訪ねてこなかったが、アラム人のナアマンだけが、捕虜の娘の言葉を信じてイスラエルの神を藁にもすがるような思いであったかもしれないが、信じて頼ってはるばる異国から訪ねてきたのである。そしてヨルダン川で7たび洗えと言われたことを、そんなことで治るのかと信じられずに初めは帰ろうとしたのだが、ナアマンのしもべたちの忠言に耳を傾けて、言われたとおりにやってみたのであった。神の預言者の言葉を半信半疑であったとしても、信じた信仰が、イエスはここで取り上げられたのである。からし種ほどの信仰があったなら、疑いがあっても、イエスのメッセージを聞いた時、「この人はヨセフの子ではないか。」のようなあざけりの言葉は出ず、本当かもしれないという信仰の言葉や行動に現れてくるだろう。イエスのメッセージを聞いた後の会衆の行動は次に書かれている。
ツァラアト は、現代のらい病、ハンセン病とは異なるある種の皮膚病のこと)にかかっていたナアマンという王の将軍がいた。アラムが略奪した際に、イスラエルの地から捕らえて連れてきたひとりの若い娘が、ナアマンの妻に仕えていた(Ⅱ列王 5:1,2)。その娘が、女主人に「もし、ご主人さまがサマリヤにいる預言者のところに行かれたら、きっと、あの方がご主人さまのらい病を直してくださるでしょうに。」と告げた(Ⅱ列王 5:3)。そう聞いたナアマンはエリシャのもとを訪れ、エリシャが言った言葉に従って、ヨルダン川に行って7たび身を洗った結果、彼のからだは元どおりになって、幼子のからだのようになり、きよくなったのであった(Ⅱ列王 5:14)。その前の章で、エリシャは、子供がなかったシュネムの女に子供を授け、何年か経って急死した子供を生き返らせる奇蹟を起こしているし(Ⅱ列王 4:8-37)、その他にもいくつかの奇蹟が記されている(Ⅱ列王 4:1-7, 38-44)。「らい病人」であったからということでナアマンを癒されたのではない。「また、預言者エリシャのときに、イスラエルには、らい病人がたくさんいたが、そのうちのだれもきよめられないで、シリヤ人ナアマンだけがきよめられました。」イスラエルの人々は神を求めて誰も訪ねてこなかったが、アラム人のナアマンだけが、捕虜の娘の言葉を信じてイスラエルの神を藁にもすがるような思いであったかもしれないが、信じて頼ってはるばる異国から訪ねてきたのである。そしてヨルダン川で7たび洗えと言われたことを、そんなことで治るのかと信じられずに初めは帰ろうとしたのだが、ナアマンのしもべたちの忠言に耳を傾けて、言われたとおりにやってみたのであった。神の預言者の言葉を半信半疑であったとしても、信じた信仰が、イエスはここで取り上げられたのである。からし種ほどの信仰があったなら、疑いがあっても、イエスのメッセージを聞いた時、「この人はヨセフの子ではないか。」のようなあざけりの言葉は出ず、本当かもしれないという信仰の言葉や行動に現れてくるだろう。イエスのメッセージを聞いた後の会衆の行動は次に書かれている。
「これらのことを聞くと、会堂にいた人たちはみな、ひどく怒り、立ち上がってイエスを町の外に追い出し、町が立っていた丘のがけのふちまで連れて行き、そこから投げ落とそうとした。」(ルカ 4:28,29)人間は都合が悪いことの図星をつかれると、怒り出すものである。会堂にいた人たちはみな(全員)、殺意をもって怒りだし(原語では、「あらん限り、1つも欠けがない激怒でいっぱいにし」という意味の言葉)、がけのふちからイエスを投げ落とそうとした。何がそんなに全会衆を怒らせたのか、普通にニュートラルな心で聞いていれば、そんなに怒るようなことをイエスは言ってはいない。「預言者は、自分の郷里では歓迎されません」イエスを神のことばを語る人(実際にイエスの語る教えは、みなの人にあがめられた内容であった)だと認め、また歓迎していたなら、ここに怒る要素はない。また、バビロン捕囚に至った罪を知り、悔い改めていたなら、「昔は神に背き、よくないことをしていたよね。」と、捕囚前の話を聞いて怒るような内容ではなかっただろう。イエスのことを、神のことばのような内容を語ってはいるが、たかが大工の息子ではないかと小バカにしていたなら、なまいきだ、焼を入れてやろうとなるだろう。エリヤやエリシャの時代のことが語られた時、癒しや奇蹟がなされない自分たちの心を振り返り、「この人は、ヨセフの子ではないか。」と言った高慢な思いに気付けるような信じ方をしていたなら、ここに怒り出す要素はないのである。彼らは、捕囚に至った罪を理解し悟ることもなく、律法に従って会堂に通い礼拝を欠かさない自分たちの信仰は立派だと自負していたのである。
「しかしイエスは、彼らの真中を通り抜けて、行ってしまわれた。」(ルカ 4:30)殺意を持ってひどく怒っている人々に対し、「しかし」とイエスは冷静であった。「思慮分別のない愚かな者に効く薬などなく、いくら教え諭しても治ることはない」という意味のことわざ1があるが、イエスは、いくら教えても、治ることはない類の不信仰さ(完全なる神を見ようとせず、欠けたところがある自分の知恵や思慮に固執している愚かさ)を相手にすることなく、堂々と真ん中を通って去って行かれたのであった。神が去った会堂、追い出したのは、会堂にいた人たちみなである。彼らが、神を追い出したその重大さに気付き、立ち返る日が来ればよいのだが・・・。イエスは、心の高い者と同じ位置に立つことなく、高ぶりを捨てようとしない者を相手にすることもなく去って行かれたのであった。神であるイエスを去らせたことを彼らは知らない。見えていない部分を見させようと「目を覚ませ」と忠告して努力しても、治すことはできない。自分を高くする異なる神に仕える人々、心低くし、神の下にやってこなければ、決して治ることはない。
神を信じて従っているつもりであっても、自分の行為を自負したり、自分中心に考えてたりしていると、いつの間にか自分とは異なる人々を見下すようになっていく。そのまま進むと「私は天に上ろう。神の星々のはるか上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山にすわろう。密雲の頂に上り、いと高き方のようになろう。」と心の中で言った(イザヤ 14:13,14)サタンの似姿に近づいていくことになる。いつの間にか、神ではなく自分が主語になっていないだろうか。肉を持つ私たちである、そのことに気づけるような心で、気づいた時に神のもとに差し出し、悔い改め聖められて安息を得られる信仰をいつも持ち続けよう。
–> 次の記事:『宣教を開始されたイエス-カペナウムにて-』
- 「馬鹿に付ける薬はない」 ↩︎

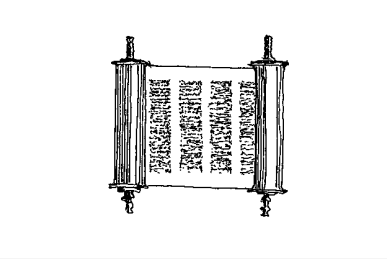



コメント