<– 前の記事:『宣教を開始されたイエス-カペナウムにて-』
聖書個所:ルカの福音書5章1節~16節(新改訳)
『イエスのもとに来る人々-主の選び-』
求めに応じられる主の姿
カペナウムで宣教を始められた主イエス、ユダヤの諸会堂に出向き、人々に悔い改めを説き、権威あることばで人々を教え、人々をあわれみ、悪霊を追い出し、病をいやし、神の愛を表わされた。その霊を治める権威と力あるわざに触れ、人々は癒しを求めてイエスのもとにやってきた。
「群衆がイエスに押し迫るようにして神のことばを聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸べに立っておられたが、岸べに小舟が二そうあるのをご覧になった。漁師たちは、その舟から降りて網を洗っていた。」(ルカ 5:1-2)イエスが語る神のことばと力あるみわざを求めて、多くの人々が、イエスのもとにやって来るようになっていた。イエスはもはや時の人のようになっていて、移動しても人々が群がってくるようになっていた。ゲネサレは、ガリラヤ湖の北西部(カペナウムからは南西に5Km弱)のところに広がる平原を指し、「ゲネサレ湖」という名称は、捕囚帰還後に「ゲネサレの海」と呼ばれるようになり、琵琶湖の四分の一ほどの大きさ(約166Km2)のガリラヤ湖の別名である。この地方は、1年のうち10か月以上いろんな果物を収穫することができ、水も豊かな肥沃な地帯であった。主イエスは、群衆に神のことばを語りつつ、ガリラヤ湖に来て岸辺に立っておられ、そこに小舟(長さ7-10mほど)が二そうあることに目をとめられた。その小舟は漁師の舟で、漁を終えた漁師たちが舟を降りて漁を終えた後の網を洗っていた。小舟の一そうはシモンの持ち舟であり、イエスはそのシモンの舟に乗られ、陸から離れて漕ぎ出すように、頼まれた。それは群衆に教えるためであった。詳訳聖書では、このように書かれている。「さて、人々が神のことばを聞こうとしてイエスのもとに押しかけて来た時、イエスはゲネサレの湖畔〔ガリラヤの海べ〕に立っておられた。」(詳訳聖書-新約-, いのちのことば社発行 p150)カペナウムで、人々は奇蹟を見て自分たちから離れないようイエスを引き留めようとしていたのだが、ゲネサレの湖畔に押し寄せるようにやってきた人々は、神のことばを聞こうと飢え渇いている人々であった。イエスは、そのような群衆を放置したり、振り切ったりすることはせず、全群衆が教えを聞けるよう動かれたのである。イエスは真剣に求めてくる人には、応えてくださるお方である。
使徒の召命
「イエスは、そのうちの一つの、シモンの持ち舟にのり、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスはすわって、舟から群衆を教えられた。」(ルカ 5:3)神のことばを求めて押し迫るようにやってきた群衆すべてが、教えを聞くことができるように、イエスは湖の上から岸に向かって語るスタイルを取られたのであった。この後のペテロの召命については、4福音書すべてに書かれているのだが、書かれている個所や出来事はそれぞれ微妙に違っている。
マタイの福音書(4:18-22)では、荒野での悪魔の試みを終え、バプテスマのヨハネが捕らえられたと聞いてガリラヤに立ちのかれた後にナザレを去ったイエスは、同じガリラヤ地方の町カペナウムに住まわれたと書かれている。そして、このことはイザヤ書の預言の成就であると触れ、宣教を開始されたことを述べた後に、ガリラヤ湖のほとりを歩いていた時、ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレに「わたしについて来なさい。あなたがたを、人間をとる漁師にしてあげよう。」(マタイ 4:19)と声をかけられ、またそこから行った先で、ゼベダイの子ヤコブとヨハネを呼ばれたと書かれている。
マルコの福音書(マルコ 1:16-20)では、荒野での悪魔の試みを終え、バプテスマのヨハネが捕らえられた後にガリラヤで神の福音を宣べ伝え、その流れで、ガリラヤ湖のほとりを通られた時に、シモンとその兄弟アンデレに「わたしについて来なさい。人間をとる漁師にしてあげよう。」(マルコ 1:17)と声をかけられ、またそこから行った先で、ゼベダイの子ヤコブとヨハネを呼ばれたと書かれていて、その後、イエスの一行はカペナウムにはいって教えられたと書かれている。
ヨハネの福音書(ヨハネ 1:35-51)では、一味変わっていて、バプテスマのヨハネがイエスに洗礼を授けた翌日、ふたりの弟子(アンデレと他一人)と一緒に立っていた時に、イエスが歩いて行かれるのを見かけ、「見よ、神の小羊。」と言ってイエスに注目させ、ふたりの弟子はヨハネの言葉を聞いて、イエスについて行った。そのアンデレがその後、自分の兄弟シモンをイエスのもとに連れていき、イエスはシモンに目を留められ、ケパ(訳すとペテロ、岩という意味)という名を授けたということが描かれている。イエスの洗礼の翌日(シモンと会われたのは翌々日)なので、カペナウムから宣教をはじめられるより前(シモンの召命よりずっと前)の話であり、この後、ルカ4章にあったシモンのしゅうとめの癒しの出来事につながっていく。この名をつけたところを見ると、イエスはシモンを見た時、シモンの中にある揺るがない正義や信念を見て取っていたと思われる。そしてイエスは、その翌日にガリラヤに行こうとされ※1、道中にピリポを見つけて声をかけられ、ピリポがナタナエルをイエスのもとに連れて来たということが書かれている。それから三日目にガリラヤのカナで婚礼があったと続いている。その後に母や兄弟、弟子たちとカペナウムに下っていき、長い日数ではないが滞在されたとある。ヨハネは、イエスの宣教開始をここからという言い方をしていず、先の三つの共観福音書を証しするようにイエスの語られた言葉を中心に淡々と丁寧に綴っている。
※1 イエスがガリラヤ地方に来られたのは、ヨハネがヘロデに捕らえられたと聞いたことがきっかけであった。「ヨハネが捕えられたと聞いてイエスは、ガリラヤへ立ちのかれた。」(マタイ 4:12)「ヨハネが捕えられて後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を宣べて言われた。」(マルコ 1:14)( 『宣教を開始されたイエス-カペナウムにて-』より)ヨハネが「見よ、神の小羊。」とイエスに橋渡しをするかのように言ったのは、神のみこころを行なった結果であり、その後、まもなくヨハネはヘロデに捕らえられたと思われる。
さて、ルカの福音書であるが、マタイやマルコの記述を詳しく説明するように書かれている(ヨハネの福音書は、先の三つの共観福音書を補うように、イエスの神性を伝える目的をもって、別の角度から書かれている)。四つの福音書は、主な対象とした人々や、伝えたい目的の違いがあり、同じ出来事をそれぞれの視点で書いた三つの共観福音書(聖書で三は完全数)は矛盾がない完全な証しとなっている。三つの共感福音書にヨハネの福音書が、神性を描いたことによって普遍的に広がりを見せる福音書となり(聖書で四は普遍的な四方八方への広がりを表す)、全人類への福音としてまとまった形となった。聖書は、神の霊感によって書かれた神聖な書物であり、よくできている。最も早く書かれたのはマルコによる福音書とされ、次いでマタイ、ルカ、最後にヨハネが書かれたという説が有力となっている。四つの福音書は細かい違いはあるが、それぞれを補って、矛盾なく理解できるようになっていることが見て取れる。
ルカ1章~4章では、荒野での悪魔の試みを終え、バプテスマのヨハネが捕らえられたと聞いて、宣教を開始しようとガリラヤに行かれたイエスが、生まれ故郷のナザレでは受け入れられず、45Kmほど北東に下ったガリラヤの町カペナウムに行って、それからユダヤの諸会堂で宣教を始められたことを見てきた。ペテロの召命の記事であるが、四福音書を総合すると、ヨハネの福音書に書かれているようなイエスとの出会いがあって後に、マタイやマルコ、ルカの福音書に書かれているように、湖で「わたしについて来なさい。人間をとる漁師にしてあげよう。」と召され、シモンたち使徒は、すべてを捨てて正式に従っていったようである。イエスが「ゲネサレ湖の岸べに立っておられた」とゲネサレ湖に来られたのは、すでに出会っていてケパ(岩)という名で呼ばれ、家に泊まってもおられたシモンがいると知ってのことで、公の宣教に入られてまもなくのこと、十二人の弟子を集められるためだったのだろう。
話を「舟から群衆を教えられた。」(ルカ 5:3)ところに戻す。神のことばを求めて押し迫るようにやってきた群衆に、ことばを届けるために、イエスは湖の上から岸に向かって語るスタイルを取られた。湖に立っていて、見ると、小舟が二そうあり、その一つは以前アンデレが連れて来て、ケパと名付けたシモンの持ち舟であった。そこで、イエスは、シモンに岸から少し漕ぎ出してくれるように頼み、イエスは岸から少し離れたところで、舟から群衆を教えられた。即席の教壇である。すわって教えるのは、当時の会堂説教において一般的なスタイルであった。話し終えられたイエスは、シモンに、「『深み〔沖(詳訳)〕に漕ぎ出して、網をおろして魚をとりなさい。』と言われた。」(ルカ 5:4)こう言われたシモンは、こう思ったかもしれない。「魚を取るプロである自分たちが、夜通し漁をしていたが、何も取れず、意気消沈して網を洗っていたのである。イエスはラビとして尊敬はしているが、漁に出たこともないだろうイエスが言ったとおりにしたところで、同じことだろう。」次のように、答えて言っている。「先生。私たちは、夜通し働きましたが、何一つとれませんでした。でもおことばどおり、網をおろしてみましょう。」(ルカ 5:5)
「そして、そのとおりにすると、たくさんの魚がはいり、網は破れそうになった。」(ルカ 5:6)イエスのことばに従うと、どこに魚たちがいたのか、夜通し努力してもとれなかった魚が、網が破れそうになるくらいたくさん、網にかかったのである。そこで、もう一つの舟の仲間の漁師たちにも助けを呼び掛けて、魚を引き上げたところ、二そうとも沈みそうになるくらいの量の魚が上げられたのであった。小舟といっても7-10m長さの舟である。「そこで別の舟にいた仲間の者たちに合図をして、助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやって来て、そして魚を両方の舟いっぱいに上げたところ、二そうとも沈みそうになった。」(ルカ 5:7)プロの漁師たちが二そうの舟で、夜通し働いても、一匹たりとも取れなかったのにである。
「これを見たシモン・ペテロは、イエスの足もとにひれ伏して、『主よ。私のような者から離れてください。私は、罪深い人間ですから。』と言った。それは、大漁のため、彼もいっしょにいたみなの者も、ひどく驚いたからである。」(ルカ 5:8,9)ちっとも取れなかったにもかかわらず、びっくりするくらいの量の魚が取れたことに、テンパったペテロ。ひどく驚いたのは、いっしょにいた仲間も同じであったが、ペテロは、感情をすぐに口や行動に表す性質があるようで、「イエスの足もとにひれ伏して、『主よ。私のような者から離れてください。私は、罪深い人間ですから。』と言った。」ペテロは、ただ驚いただけでなく、そこに神の御手を感じ取ったと同時に、自分の罪の性質の自覚も感じ取り、神への怖れをもって心低くひれ伏し、主の前に出たのであった。プロ中のプロやすぐれた人物を「神!」と呼ばれることがあるが、ペテロはそのように人間に向けて呼ぶ「神」以上のプロの技を超えた「真の神」を見、自分を「罪深い人間」と言ったのである。同じ出来事を見聞きしても、そこに何を見るかは人それぞれである。ペテロがテンパりながらもとっさに出た言動であることを見るに、イエスに会って神の言葉を聞いた時、いやそれよりも前から、心にあったことを確信したのだろう。少しもぶれずにまっすぐに向かうペテロの姿である。ルカの福音書では、「シモン・ペテロ」とフルネームで書かれているのは、ここだけである。ヨハネの福音書では、普通に複数回この呼び方が出てくるのだが、マタイの福音書では、「あなたは、生ける神の御子キリストです。」(マタイ 16:16)と信仰告白の個所に、マルコの福音書には出てこないフルネーム。ルカが、フルネームで記した個所が、ペテロが信仰告白をし召命を受けたこの個所であることは考え深い。
「シモンの仲間であったゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンにこう言われた。『こわがらなくてもよい。これから後、あなたは人間をとるようになるのです。』」(ルカ 5:10)ここに、ヤコブとヨハネの名が出てくる。マタイやマルコの記事では、シモンに「人間をとる漁師にしてあげよう。」と言われた後、行った先でヤコブとヨハネを呼ばれたと書かれていた場面である。ゼベダイの子ヤコブとヨハネは、シモンの漁師仲間で、その場にいて、ひどく驚いた人々の中にいたようだ。「こわがらなくてもよい。」とあるように、シモンがこわがっていたことがわかる。神に出会い、原罪を含め罪を抱えた自分と比べものにもならない圧倒的な神聖に触れた時、人間は神への怖れを抱く。神に出会ったと言って、自分が神であるかのようにふるまうとしたら、その人が出会った神は、真の神ではなく、別の存在である。人の姿を取って来られたイエスは、怖れながらも神の前に救いを求めてやってくる人に、「こわがらなくてもよい。」と手を差し伸べられる方である。「これから後、あなたは人間をとるようになるのです。」とイエスがシモンに言われたとあるが、マタイやマルコの記事によれば、「イエスは彼ら(アンデレとシモン)に言われた。」(マタイ 4:19, マルコ 1:17)とある。
「彼らは、舟を陸に着けると、何もかも捨てて、イエスに従った。」(ルカ 5:11)アンデレや、この後イエスに呼ばれたヤコブとヨハネを含め、彼らは、何もかも捨てて、イエスに従う道を選んだ。「何もかも捨てて」というのは、漁師を生業としていた者に、「これから後、あなたがたを(魚ではなく)人間をとる漁師にしてあげよう。」と呼ばれ、応答した結果、従う時に持っていけない「何もかも」である。漁師のプロとしての誇り(ヤコブやヨハネは、父ゼベダイも漁師であり、人を雇っていた)や、この後の生活の不安などを捨てたのである。マタイの福音書は、「彼らはすぐに網を捨てて従った。」(ペテロとアンデレ、マタイ 4:20)「彼らはすぐに舟も父も残してイエスに従った。」(ヤコブとヨハネ、マタイ 4:22)、マルコの福音書では、「すると、すぐに、彼らは網を捨て置いて従った。」(ペテロとアンデレ、マルコ 1:28)「すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちといっしょに舟に残して、イエスについて行った。」(ヤコブとヨハネ、マルコ 1:20)と書かれている。魚を取る網や漁師の父や雇人たちを捨て置いて(湖に残して)従ったのである。このことばを利用して金銭や財産を捨て(捧げ)させようとする異なる教えもあるが、何でも捨てればよいものではない(神が与えたもうた感謝すべき仕事、物、関係もある)し、世の何もかもを捨てることが優れた行為になるわけでもない。神のみこころなる言葉に従おう。
全身「らい病」※2の人を癒され…
※2 「らい病」と訳されていた  ツァラアト は、現代のらい病、ハンセン病とは異なるある種の皮膚病のこと
ツァラアト は、現代のらい病、ハンセン病とは異なるある種の皮膚病のこと
「さて、イエスがある町におられたとき、全身らい病の人がいた。イエスを見ると、ひれ伏してお願いした。『主よ。お心一つで、私はきよくしていただけます。』」(ルカ 5:12)イエスの宣教での一幕である。当時、「らい病」に侵された人は、他の人々と共に住むことが許されず、人に近付く時は「汚れている」と叫ぶよう求められていて、主の集会にも加わることができなかった。「全身らい病の人」というのは、そのような孤独な境遇に置かれた人であった。その人は、「自分は汚れているから、イエスに近づけない」とは考えず、イエスを見て「お心一つで、私をきよくしてくださる方」と信じて、御前にひれ伏した。同じ記事が、マタイとマルコにも記されているのだが、「ひとりのらい病人」(マタイ 8:2, マルコ 1:40)と表現していて、医者であったルカは「全身らい病の人」という表現で「らい病」が全身であったことを記している。全身「らい病」にかかりいつ治るか希望もないような状態で、イエスにすがったのである。イエスは、そのような状態をあわれみ、「お心一つで、きよくしていただける」という彼の信仰に応えられた。「イエスは手を伸ばして、彼にさわり、『わたしの心だ。きよくなれ。』と言われた。すると、すぐに、そのらい病が消えた。」(ルカ 5:13)「汚れている」とされた彼には、誰もさわろうとしなかっただろう。イエスは、言葉一つで癒すこともできるお方であるのだが、そのような彼の体に手を伸ばしてさわり、「お心一つで、きよくしていただける」と言った信仰に応じ、「わたしの心だ。きよくなれ。」という言葉をかけて、癒された。結果、たちまちのうちに「らい病」は消えたのである。
「イエスは、彼にこう命じられた。『だれにも話してはいけない。ただ祭司のところに行って、自分を見せなさい。そして人々へのあかしのため、モーセが命じたように、あなたのきよめの供え物をしなさい。』」(ルカ 5:14)人は、信仰がなくともこのような超常現象には飛びついてしまう。イエスは、奇蹟が独り歩きして見せ物のように、人々が押し寄せることを望まれなかった。イエスのもとにであっても、人が多くやって来ればよいというものではない。求める心、目的が肝心である。その人の心次第では、神のことばであっても、神のわざを見たとしても、伝わるものも伝わらない。イエスであっても、変えられない人の心がある。
モーセの律法において、皮膚にできた「らい病」の患部を調べて「汚れている」とか「きよい」と宣言するのは、祭司の役割であった(レビ 13章)。そして、律法においては「きよい(「らい病」の患部がいやされている)」と宣言された人は、祭司のもとで儀式(供え物)をすることが定められていた(レビ 14:1-32)。モーセの律法通りに行うよう指示したのは、人々へのあかしのためであった。癒されたことに違いはないのだが、祭司の証明書がなければ、人々は信じられず、彼をきよい者として扱わないかもしれなかった。イエスは、ただ癒されたのではなく、この後、彼が生活しやすいように、配慮を持って指示したのである。主の愛による配慮である。
「しかし、イエスのうわさは、ますます広まり、多くの人の群れが、話を聞きに、また、病気を直してもらいに集まって来た。」(ルカ 5:15)イエスは、「誰にも話してはいけない。」(ルカ 5:14)と言ったのだが、マルコは「ところが、彼は出て行って、この出来事をふれ回り、言い広め始めた。」(マルコ 1:45a)と記している。喜びのあまりになのか、イエスはああ言ったがイエスのしたよいわざは人に伝えるべきだと彼が考えたのかはわからない。彼が言い広めなくても、見ていた人や知った人が広めたかもしれないが、彼が積極的に広めた、「そのためイエスは表立って町の中にはいることができず、町はずれの寂しい所におられた。」(マルコ 1:45b)と記されている。その結果、本当の意味での宣教の妨げになり、イエスは寂しい所、ルカによれば荒野に祈るために退いておられた。「しかし、イエスご自身は、よく荒野に退いて祈っておられた。」(ルカ 5:16)それでも、追っかけの人々は、イエスを探し当ててやってきていた。「しかし、人々は、あらゆる所からイエスのもとにやって来た。」(マルコ 1:45c)中には、本当に必要としている人がいたかもしれないが、「あらゆる所から」押し寄せる人々、静まっての祈りもままならなかっただろう。
多くの人々が、話を聞きに、また病気の癒しを求めて、主のもとにやって来たのだが、まず主が目を留められたのは、たやすく動かされない「岩」のような性質を持ち、後に「主よ、私のような者から離れてください。私は、罪人ですから。」とひれ伏しみもとに来たペテロであった。追っかけてつかもうとする人々と、罪を持つ自分から離れるよう言いつつ、御前に出たペテロ。主は、ペテロの信仰と性質を愛され、この後、みそば近くに置かれたのである。こうして召されたペテロたちに、イエスは、ご自分が去られた後の教会形成を託されていった。
私たちは、どのように主に近づき、主のことばに従っているだろうか。主が目を留めてくださる者になっているだろうか。静まり、主の御声に従ってまいりましょう。
–> 次の記事:『イエスが来られた世-神の愛からの逸脱-』

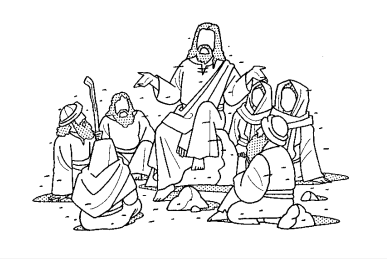


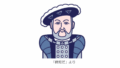
コメント