聖書個所:Ⅰコリント人への手紙 6章1節~11節(新改訳聖書)
『さばく力-争いの仲裁-』
罪の容認
いろいろなタイプの人々が集うと、好みや主張もいろいろで、治める力が問われてくる。それは、小さなグループでも、学校でも、職場でも、国でも、自分ファースト(弱い者を顧みない自己中心)でいろいろ主張し出したら、まとまりがなくなって、気が合った人だけ受け入れるような偏った共同体になったり、強い者が「右」といえば、他の人は間違っていると思っていても「右」ということで同調しておかないと所属できなくなる独裁的な共同体になったりする。後者は、マインドコントロールに陥りやすい状況である。
気が合った人だけ受け入れるのは、仲良しグループのことならば、それはそれでよいのだが、ある目的をもって存在している社会的グループであるならば、そういうわけにはいかない。教会がそのような仲良しグループでまとまっていたり、独裁的権力者によって統率されたなら、そこに、キリストの愛があると言えるだろうか。そのような教会があるとすれば、キリストのうちにある教会かどうか(頭はキリストかどうか、いつのまにかキリストを追いやり頭がすりかわっていないか)疑った方がよいだろう。
教会ができてきた初期の頃、交通の要所であったコリントの教会には、いろいろな人種が入り混じっていた。そういった多様な人々が集う中、教会内にも、党派、不道徳、訴訟、偶像にささげられた肉、主の晩餐の濫用、偽使徒、結婚の諸問題、集会における無秩序な行為、教会における婦人の位置、復活に関する異端・・・といったいろいろな問題が起こっていた。商業貿易の中心であったコリントは、邪悪かつ不道徳な町として有名であり、コリントという語が、堕落と同義語にさえなっているほどの不品行の町であったという。性的にも放縦に暮らしていたコリント人たちは、このような土壌、環境のもと、救われた後もこの習慣をきっぱり断ち切ることができない者が教会内部にも存在していた。
教会の中で、継母を妻にしたという不品行の罪がパウロの耳に届いた(Ⅰコリント 5:1)。父がすでになくなっていようが、両親がすでに離婚していようが、どんないいわけをしたとしても、父の妻と関係を持つことは、父を辱める行為であり、律法ではっきりと禁じられていることであり(レビ 18:7,8)、悔い改め、方向転換するべき罪であった。コリント教会のクリスチャンは、このような罪が教会内にはびこっていても、なお、誇り高ぶっていたのである。
教会の中では、個人の罪は、一個人の罪にとどまらない。周囲は、クリスチャンの罪として見る。キリストのからだの罪となり、「クリスチャンがあのようなことをしている。」と主の敵に大いに侮りの心を抱かせることになるのである。ダビデが、ウリヤの妻と不品行の罪を犯し、その罪を認めたとき、ナタンは言った。「主もまた、あなたの罪を見過ごしてくださった。あなたは死なない。しかし、あなたはこのことによって、主の敵に大いに侮りの心を起こさせたので、あなたに生まれる子は必ず死ぬ。」(Ⅱサムエル 12:13,14)キリスト者の罪の容認は、聖なる神の名を汚す行為となり、敵に侮りの心を与えることになるのである。キリストの宣教は「悔い改めなさい。神の御国が近づいたから。」で始まっているように、神の国の一員になるには、罪の中にいる自覚と罪から離れる意思が必要である。
キリスト者が集う教会の中で、罪が発覚したときの正常な反応は、痛みと悲しみである。パウロが、「そのような行ないをしている者をあなたがたの中から取り除こうとして悲しむこともなかったのです。」(Ⅰコリント 5:2)と言っている「悲しむ」の原語は、死者への追悼をあらわすことばであるそうだ。罪に対するいいかげんな態度は危険なものである。罪に慣れ親しんで、そのうちに、罪がわからなくなってしまう。そして、罪によって他の人を傷つけようが、悲しませようが、正当化してしまうようになる。罪に麻痺してしまうのである。罪悪感があるうちは、まだ、立ち返るチャンスがある。罪に対する唯一の安全保障は、罪を見てショックを受けることであると、バークレーは言っている1。これがなくなってしまうと、罪がわからなくなり、容認していくことになるのである。愕然として、みずから傷つき痛むべきものであり、キリストとともに乗り越えていくことである。キリストを十字架にかけた人類すべての罪、これにショックを受けることなしに、キリストを知ることもできないし、よって、救いもないのである。
パウロは、「私のほうでは、…そのような行ないをした者を主イエスの御名によってすでにさばきました。…私たちの主イエスの権能をもって、このような者をサタンに引き渡したのです。それは彼の肉が滅ぼされるためですが、それによって彼の霊が主の日に救われるためです。」(Ⅰコリント 5:3-5)パウロは、このように罪から離れられない者を、主の権威を用いて、教会の交わりから断ち、世に戻したのである。これは、パウロの愛から出ていた。きちんとさばくことによって、罪の重大さを悟り、新生するためであった。罪の予防と治療のためである。このようにさばいたパウロが、むしろ、罪を黙認し、見逃していたコリントの兄弟たちを「高慢」(Ⅰコリント 5:2,6)と呼んでいることに注目したい。神を知らない者にとっては(神を無視するなら)、「主イエスの御名によってすでにさばきました。」と言いきれるほうが、高慢に聞こえ、「他人の罪を扱うなんて、おまえは、何者なのか。」と反論されそうである。
主イエスが、屋根からつり降ろされた中風の男を「あなたの罪は赦された」と言っていやされた時、律法学者、パリサイ人たちといった指導者たちは、「神をけがすことを言うこの人は、いったい何者だ。神のほかに、だれが罪を赦すことができよう。」(ルカ 5:21)と言った。どっちが高慢であるか、いうまでもなく明白である。パウロがここで言っているさばきは、そもそも「さばいてはいけません。さばかれないためです。」と主イエスが言われた類の破壊的なさばきではなく、神の国を「治める」という神の国の建て上げのためのさばきである。「さばいてはいけません。」と言われた主イエスは、愛である神に仕えず文字に仕えている指導者たち(律法学者、パリサイ人、サドカイ人たち)に「まむしのすえたち、・・・」(マタイ 12:34, 23:33)と厳しい言葉を浴びせられている。
「あなたがたの高慢は、よくないことです。あなたがたは、ほんのわずかのパン種が、粉のかたまり全体をふくらませることを知らないのですか。」(Ⅰコリント 5:6)コリント教会は、黙認すべきではない罪は見逃して、戦うべきではない罪でもない問題については、教会以外の権威に訴えてでも争うというふうに、与えられた治めるという機能を用いずにいた。神よりも自分の感情によって処理していたのである。この高慢というパン種は粉のかたまり全体をふくらませてしまうものである。パン種というのは、前回パンを焼いたときから保存しておいた、発酵した練粉のことであるのだが、ユダヤ人は発酵を腐敗と同一視していた。「パン種」は腐敗させ堕落させる影響を言っている。ちょっとぐらいの罪=わずかなパン種が全体を腐らせると言っているのである。
罪の取り扱い
パウロは、以前、コリントの教会に不品行な者とつきあうなと書き送っていたところ(Ⅰコリント 5:9)、コリントの兄弟姉妹は、それを、教会外部に当てはめてしまったようだ。これを外部に実行するなら、神をまだ知らない人たちに恵みを知らせるどころか、上目線でさばくようなこと(断罪、高慢)になっただろう。コリントのような不品行のはびこる町では、教会は孤立化してしまうことになる。パウロが、真に意味するところは、「もし、兄弟と呼ばれる者で、しかも不品行な者、貪欲な者、偶像を礼拝する者、人をそしる者、酒に酔う者、略奪する者がいたなら、そのような者とはつきあってはいけない、いっしょに食事をしてもいけない、ということで」(Ⅰコリント 5:11)であった。この思いは、先に述べたように、罪を犯している兄弟を悔い改めに導くため、主を侮らせないためであった。
続けて、パウロは述べる。「外部の人たちをさばくことは、私のすべきことでしょうか。あなたがたがさばくべき者は、内部の人たちではありませんか。外部の人たちは、神がおさばきになります。その悪い人をあなたがたの中から除きなさい。」(Ⅰコリント 5:12,13)教会外部の人たちの罪は、神を知らないでしていることゆえ、その人たちにすべきことは、福音を伝えることであって、さばくことではない。神のみが人の心を知っておられる。神は、その人がなぜそのような罪に陥っているのかをご存知である。そういうわけで、神を信じていない者については、神にさばきをゆだねなければならない。
教会内部の人については、互いに訓戒し合うという責任がある。神を知っている者同士としてできる特権である。もちろん、兄弟愛に基づいて、柔和に、である。断罪する心しかないなら、争いをもたらして新たな問題が生じていくだろうが。神の国を建て上げるためのさばきは、愛の心を伴うものである。神が明らかに罪であると断言しているにもかかわらず、悔い改めない兄弟のそのような罪を見過ごすことこそ、高慢なことである。罪を指摘されていい気分になる者はいない。神が明らかに罪であると断言しているにもかかわらず、悔い改めない兄弟の罪を見過ごすことは、神よりも自分の立場を重要視しているということになる。そうであるからこそ、パウロは、内部の人たちをさばきなさいと言っているのである。物事をあいまいにしておきたい日本人にとっては、苦手とするところである。しかし、愛があるなら、死をもたらす罪(「罪から来る報酬は死です。」(ローマ 6:23))を見過ごしにしていいものではないのである。罪の指摘と言ったが、悔い改めない者に対してであって、いつでも、どこでも、誰にでも、ということではない。
治めることの大切さ
パウロは続ける。「あなたがたの中には、仲間の者と争いを起こしたとき、それを聖徒たちに訴えないで、あえて、正しくない人たちに訴え出るような人がいるのでしょうか。あなたがたは、聖徒が世界をさばくようになることを知らないのですか。世界があなたがたによってさばかれるはずなのに、あなたがたは、ごく小さな事件さえもさばく力がないのですか。」(Ⅰコリント 6:1,2)裁判官に六法全書がある、それ以上のものとして私たちには、聖書がある。「これらのことは、あなたがたが住みつくすべての所で、代々にわたり、あなたがたのさばきのおきてとなる。」(民数記 35:29)確かに、愛ではなく、律法的にさばくのはいけないが、善と悪を教える聖書に基づいて、正しく神の国を治めていくことは、しなければならないことである。これをせずして、一致できるわけがないのである!不義が通っているところには(無法がまかりとおっているところには)一致など生まれるわけがない。
治める者がいなかった士師の時代は、めいめいが自分の目に正しいと見えることを行なっていた。堕落とさばきつかさの台頭をくりかえしていた無秩序の時代を思えば、いかに治めることが大切か理解できることだろう。治める者が使徒や預言者と並ぶ務めの賜物として、あげられているのは、それだけ重要なことだからである。「神は教会の中で人々を次のように任命されました。すなわち、第一に使徒、次に預言者、次に教師、それから奇蹟を行なう者、それからいやしの賜物を持つ者、助ける者、治める者、異言を語る者などです。」(Ⅰコリント 12:28)「さばく力」それは、主からくる賜物である。神の知恵をもって治めるならば、麗しい教会が世の光となるだろう。
だれひとりとして、問題の解決にかかわろうとしない状態をパウロは、嘆き叱責する。「いったい、あなたがたの中には、兄弟の間の争いを仲裁することのできるような賢い者が、ひとりもいないのですか。」(Ⅰコリント 6:5)また、次のようにも言っている。「あなたがたは、正しくない者は神の国を相続できないことを、知らないのですか。だまされてはいけません。不品行な者、偶像を礼拝する者、姦淫をする者、男娼となる者、男色をする者、盗む者、貪欲な者、酒に酔う者、そしる者、略奪する者はみな、神の国を相続することができません。」(Ⅰコリント 6:9,10)「正しくない者(罪の中にある者)は神の国を相続できない」と言っているのである。クリスチャンの罪は、過去から未来にわたって、赦されているから、大丈夫などとパウロは言ってはいないのである。このことは、キリスト者であるコリントの人に言われたことであることを重視しなければならない。「神の国に入れない」と言っているのである。
「兄弟たちよ。もしだれかがあやまちに陥ったなら、御霊の人であるあなたがたは、柔和な心でその人を正してあげなさい。また、自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。互いの重荷を負い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。」(ガラテヤ 6:1,2)キリストの律法、神への愛と人への愛を全うするために、互いの重荷を負い合い、正していくことが神の国には必要である。「傷つくほうが悪い。」というメッセージを幾人かの指導者の口から聞いたことがある。耳を疑うような言葉である。何気ないことにもすぐに傷つくようだったり、ちょっとした言葉を誤解してだったりと、傷つくのが疑問に思えるようなケースだったとしても、傷つきやすい心を強めたり、認知のゆがみがあるかのワークが必要だろうし、「傷つくほうが悪い。」と断罪して更なる傷を与えることは、その人を死に追いやる可能性がある行為である。神の国は、弱肉強食の世界ではない。傷ついたほうにも問題がある場合もあるのかもしれないが、相手があってのこと、どっちもどっち、重要なことは各々の心、愛である。たとえ、「傷つくほうが悪い。」という雰囲気が蔓延しているところに、行きたがる人は、通常はいない。いたとすれば、自分は傷つくことはない強者だと自負している人だろう。
今までの個所で、パウロは「さばけ」と言っているが、他のところでは、パウロは、さばくことをとがめているし(ローマ 2:1-6, 8:1, 14:4, 8:33)、自分をさばくことすらしないと言っている(Ⅰコリント 4:3)。主イエスだって、さばいてはいけないと言って、自分の目の梁をそっちのけにして、他人の目のちりを除こうとする行為を指摘している(マタイ 7:1, ルカ 6:37)。さばけと言ったり、さばくなと言ったり、聖書はどっちを言っているのか、となるところである。神の国は、愛の国である。このときはこうすること、と単純にマニュアル化して決められるような単純なものではない。その心が、動機が、神への熱心でもなく、愛でもなく、ただ非難し、他人をさげすむような高慢から出たことであったなら、してはならないことである。
この罪の扱い方について、他の個所も見てみよう。「もし、あなたの兄弟が罪を犯したなら、行って、ふたりだけのところで責めなさい。もし聞き入れたら、あなたは兄弟を得たのです。もし聞き入れないなら、ほかにひとりかふたりをいっしょに連れて行きなさい。ふたりか三人の証人の口によって、すべての事実が確認されるためです。それでもなお、言うことを聞き入れようとしないなら、教会に告げなさい。教会の言うことさえも聞こうとしないなら、彼を異邦人か取税人のように扱いなさい。まことに、あなたがたに告げます。何でもあなたがたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたがたが地上で解くなら、それは天においても解かれているのです。」(マタイ 18:15-18)クリスチャンには、罪の赦しの権威までもが与えられているのである。何でもかんでも赦せばよいものではないのであり、また、何でもかんでもさばけばよいものでもない。
「つまずきが起こるのは避けられない。だが、つまずきを起こさせる者は、忌まわしいものです。この小さい者たちのひとりに、つまずきを与えるようであったら、そんな者は石臼を首にゆわえつけられて、海に投げ込まれたほうがましです。気をつけていなさい。もし兄弟が罪を犯したなら、彼を戒めなさい。そして悔い改めれば、赦しなさい。かりに、あなたに対して一日に七度罪を犯しても、『悔い改めます。』と言って七度あなたのところに来るなら、赦してやりなさい。」(ルカ 17:3)詳訳聖書で見ると、「気をつけなさい。<いつも自分で注意していなさい<互いに見張っていなさい>。もしあなたの兄弟が罪を犯し<的をはずし>たならば、彼にまじめに話し<彼を戒め>、悔い改めたならば<罪を犯したことを悔いていたら>、赦しなさい。」である2。罪の自覚も悔い改めもないのに、赦すようなことは、神はなさらない。話しても取り合おうとせず、罪を認めようともしない者の何を赦すのか、赦しの必要を感じていない人の何を赦すのか。キリスト教は、ひとりよがりに慢心する宗教ではない。キリストなる神も悔い改めのない者はお赦しになってはいないのである。神を超えて赦すことは、主にある者としてはしてはならないことである。
不適切な聖書解釈による実
あるクリスチャン女性が、礼拝するために教会に行き、礼拝堂に座って礼拝が始まるのを待っていた。そこへ、3日前に初めて交わりをもった信仰歴が長いスタッフの姉妹が近寄ってきた。「あなたのことを赦します。これを言わないといけないと思って…」目も合わせることなくあたふたと言い放ち、女性がポカンとしている間に離れた席に行ってしまった。言われた女性は、礼拝前に、「何のことを言われたのだろう?私、何かした???」「赦してもらわないといけないような何をしたのか?」とモヤモヤしてしまったという。赦しますと言った姉妹は、その女性に対し何かよくない思いを持っていたのかもしれないが、その思いは、その女性には関係のないことで――女性が何か失礼なことをしていたならば、まずそのことについて話さなければ正統な理由ゆえの思いかも女性にはわからないのである――、よくない思いを抱いた人と神との間の問題である。神の前に悔い改めて、良い関係を保って悔い改めの実を実らせていけばよいだけのことだったのだが、スッキリしたかったのだろうか、それとも、赦す自分の信仰を見せたかったのか、思いを相手にぶつけてしまったのである。その結果、言われた女性は、礼拝中、不可解な思いを払拭するのに時間がかかったのであった。
キリスト教は、十字架上のイエスが、「父よ。彼らをお赦しください。彼らは、何をしているのか自分でわからないのです。」(ルカ 23:34)ととりなされ、贖いを成し遂げられ、赦しを説く宗教であるが、何でもかんでも思いつくままに赦しを宣言したり、理由もわからない人にとりあえず謝っておけばよいというものではない。日本人は、「すみません」「ごめんなさい」と社交辞令のように言いがちであり、本当に赦してほしいと思って言っていない場合もあるので、使う時には、注意が必要である。また、神の赦しを説く説教者は、加害者の悪の行為に対しては甘く放置しておき、被害者のほうに赦すことばかり教えるというような偏った対応をしない配慮が必要である。悪を治める努力は必要で、また、傷をいやした上での赦しである。先ほどの話の赦すと言った姉妹は、女性に近づかなくなり、女性もまた、避けている姉妹にあえて話しかけることはなく、しばらくしてその教会を去った。赦しを宗教的に捉えた結果であった。
「あなたがたは、信仰に立っているかどうか、自分自身をためし、また吟味しなさい。それとも、あなたがたのうちにはイエス・キリストがおられることを、自分で認めないのですか。――あなたがたがそれに不適格であれば別です。――」(Ⅱコリント 13:5)罪の中にいるか、キリストの信仰に立っているかは、自分自身の心を吟味することである。キリストが内在するなら、キリストを十字架にかけた罪に対して、いいかげんにしておくことができないはずである。赦しは、罪を説き、罪を治める努力をしているところに起こる神のわざである。そこにしこりは残らない。悪を治めようとしないまま、お手軽に赦しなさいというのは、キリストの教えではない。何の宗教だろうか。「あからさまに責めるのは、ひそかに愛するのにまさる。憎む者がくちづけしてもてなすよりは、愛する者が傷つけるほうが真実である。」(箴言 27:6)愛という動機が大切である。
聖書にある実例
実際、神の人が、罪をどのように扱ったかを、旧約新約それぞれ見てみよう。旧約では、先程も少し触れたが、ダビデ王が、ウリヤの妻バテ・シェバと不品行の罪を犯し、罪をごまかすために、夫のウリヤを戦地で死ぬように計った例を見る。ウリヤを死に追いやり、ダビデは、バテ・シェバを妻とし、バテ・シェバは男の子を生んだ。主の預言者ナタンを通じて、罪とさばきが言い渡され、ダビデは、悔い改めた(Ⅱサムエル12章)。ダビデが罪を犯してから、子供が生まれ、病死するまで一年以上は経っていることになる。「あなたはこのことによって、主の敵に大いに侮りの心を起こさせたので、あなたに生まれる子は必ず死ぬ。」(Ⅱサムエル 12:14)ということが言い渡された時に、もうひとつの罪の刈り取りともいえる三男アブシャロムの謀反につながることを言われているのだが(Ⅱサムエル 12:11,12)、それはさらに数年、数十年の後のことである。このように、神の国に深くかかわる罪をナタンが、王であるダビデに、喜んで告げたはずがない。王の心次第では、殺されかねないのである。罪に対する痛み、悲しみ、神や神の民に対する愛ゆえに、罪とその刈り取りを言い渡すことができたのである。
新約では、バプテスマのヨハネを見てみよう。ヘロデ王が、自分の兄弟ピリポの妻ヘロデヤを妻としていたことをヨハネが「あなたが兄弟の妻を自分のものとしていることは不法です。」と告げた(マルコ 6:18)。自分の兄弟の妻をめとることは、兄弟をはずかしめる忌まわしい行為であって律法で禁じられていた(レビ 20:21)。ヨハネは、捕えられ、牢につながれ、祝宴の余興として、首をはねられ殺された。罪を侮る者にとって、ヨハネの死は、ばかばかしく見えるのだろうか。「のこのこ言わなくてもよいことを王に言いに行き、牢屋に入れられ、証しにならない死に方をした」とでも言うのだろうか。主イエスは、獄中のヨハネを「女から生まれた者の中で、バプテスマのヨハネよりすぐれた人は出ませんでした。しかも、天の御国の一番小さい者でも、彼より偉大です。」(マタイ 11:11)「実はこの人こそ、きたるべきエリヤなのです。」(マタイ 11:14)と言い表した。
パウロは、罪を扱わない教会について、言ったのである。「あなたがたは、聖徒が世界をさばくようになることを知らないのですか。世界があなたがたによってさばかれるはずなのに、あなたがたは、ごく小さな事件さえもさばく力がないのですか。」(Ⅰコリント 6:2)「いったい、あなたがたの中には、兄弟の間の争いを仲裁することのできるような賢い者が、ひとりもいないのですか。」(Ⅰコリント 6:5)
教会の一致のためには、さばく力、仲裁による問題解決、治める賜物が必要である。罪を説かなくなった教会では、悔い改めは起こらず、塩気がない状態となってしまう。世の光となるべき教会、聖書が語る真理への愛から出ている教えの内にとどまろう。

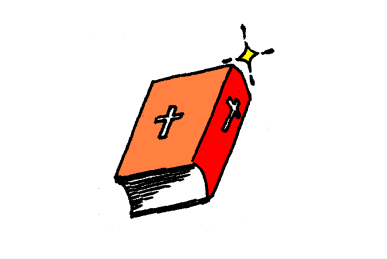



コメント