<– 前の記事:争いや動乱とともに広がるプロテスタント~個人が選択する信仰へ(1)
前回からの続きである。
ジェームズ1世からの激しい弾圧から逃れるため、また、その頃、イギリスでの経済不振と伝染病の流行が起こっていたことから、多くのピューリタンを含む人々(ピューリタンは半数以下)は、植民地を建設しようとメイフラワー号に乗って、新大陸アメリカに渡った。メイフラワー号が出発したのは1620年9月16日のことであった。66日間の厳しい航海を経て、11月に目的地より北のケープコッドに着いた。当初の目的地は当時のイングランドのバージニア入植地の北端にあたるハドソン川河口であった。バージニア入植地は、メイフラワー出発より13年前の1607年に全米最初のイギリス人移民地として、ジェームズタウンから入植を始めていた地であった。こうして、カルヴァンの改革を取り入れ、イギリス国教会に批判的だったピュリータンたち数十名は、純粋な信仰の国家建設を目指して、アメリカに入植した。
マルチン・ルターは、民衆と神の愛による真理に立って、カトリックの誤り(民を滅びの道に向かわせている免罪符による救い)を正そうと、宗教改革を手掛けたが、聖書が翻訳され、印刷術が発展していたこともあって、その改革に便乗し、独自の考えで派閥を作る者たちも出てきた。マルチン・ルターは、礼拝形式を心から礼拝を捧げるようにと見直し、「私は一つのモデルを提供する・・・」とモデルとしてまとめ、民衆に寄り添って、改革を進めていた。
そうしたところに、カルヴァンが改革を手掛け、市民生活に厳しい規律を求め、違反者を次々と捕らえて裁判にかけ、恐怖政治を実施していった。当時の教皇支配からの脱却や改革を望む人々は、「福音主義に基づくキリスト教改革の理念を示し、教理を体系的にまとめ、神学として整えた」カルヴァンのプロテスタントの教理を支持していくようになった。ルターの主眼点は、「罪に悩む人が、どうすれば救われるか」ということであったが、カルヴァンは、 「神の栄光が、世界と教会にどう現れるか」であった。この出発点にまず違いがある。
「労働は神への奉仕であり、労働による利益は自らのために消費されてはならず、より大きな神への奉仕の実現のために、すなわち生産の拡大のために用いられ、その結果資本の蓄積、増大が推進される」というカルヴァンの教えは、人々の心次第では、神を理由にして金銭を追い求める理由付けがしやすくなってしまうものである。カルヴァンは、カトリックからの批判を避けたく改革派信仰が正統的なキリスト教であることを示そうと、「聖書理解への案内書(手引き)」として、「キリスト教綱要」を出版し、体系的にまとめた。カルヴァンは、これを少なくとも5回以上(主要な版だけで)改訂している。1536年に出された初版本は、正統的なキリスト教であることを示そうと主要な教理を記しているものだったのだが、自身の解釈や自身の経験を踏まえて、完成を目指して改訂を重ねていき、1539年に大幅に改訂した。この改定で、初版の約3倍以上のボリュームとなり、神学論争への応答など神学的内容となり、予定論もこの時、初めて体系的に登場させた。1559年(初版本より23年後)に最終決定版を出し、成熟した体系神学の書物となった。
改訂を重ねてできあがった最終決定版は、聖書に書かれている言葉の基本的な解説ではなく、カルヴァンの解釈である。何年も引き継がれてきて、多くの神学者によって練られて完成したものではなく、「教理を体系的にまとめ、神学として整えた」のは、カルヴァン個人である。プロテスタントは、直接神につながる万人祭司を唱えている。よって、カルヴァンの神学も、個人個人が、神に祈りながら、神の愛に立ちながら用いていくものということとなり、その解釈は、始末されていない罪などがあると、様々な教理が生み出され、長年経過すると、数え切れない分派が存在することとなってしまう。聖書の一面を大切にし強調する教理を特性とし、互いに大事な存在として愛し合いながら、基本的な一致と協力をしていけば、麗しい神の国が形成されていくのだが、罪の存在を放置していくと、神の国は立ち行かなくなっていく。
神の言葉というものを律法的に捉え、人間の頭に納まるように限定してしまうと、変質してしまいやすくなる。カルヴァンの「労働による利益は、より大きな神への奉仕のため」との教えのその部分だけ取って都合よく解釈すると、金銭を追い求め利益を追求することが、神のためのようになる。聖書は、「金持ちが神の国にはいるよりは、らくだが針の穴を通るほうがもっとやさしい。」(マタイ 19:24、ルカ 18:25)、「金銭を愛することが、あらゆる悪の根」(Ⅰテモテ 6:10)ともあり、金銭を追い求めることに注意を与えている。「労働による利益は、より大きな神への奉仕のため」との教えは、金を追い求めることの是非が「神への奉仕の実現」という名目があれば良いもののように、白く塗りかえられられてしまいやすくなる(カルヴァンには、そういう意図は全くなかったのだろうが)。それは、「救いは既に神によって予定されている」という予定説と相まって、選民意識での高慢や搾取に発展しやすくなっていった(予定説も、カルヴァンは、民を励ます目的で教えたものだったが)。
「神に選ばれている私たち」という思想は、キリスト教以前、ユダヤ教以前、神がノアやアブラムを召し出された時から、その原型はある。「神が召してくださった」という事象をノアやアブラム、モーセたちのように神を恐れ謙虚に受け止めて、神のみこころを歩むという模範に倣うならば、すなわち「罪人にすぎない私たちを、神は選んでくださった」と謙虚に受け止め、神を愛しみこころを行い神に仕えていこうとするならば、麗しい神の国が形成され、良い実が周囲にも現れ、他の人々もその中に加わりたいとなる。しかし、罪を扱わずに野放しにし、罪をからめて高慢のパン種を膨らませつづけると、「神に選ばれている私たち」という選民意識は、「神に選ばれていない人たち」を作り出し、神から離れていっていることにも気づかなくなり、違う実を表していくことになる。そのような選民意識は、他国を植民地化し、奴隷として神から選ばれた者たちに仕えさせ、歯向かう者たちに残虐な行為を行ったとしても、「ひどいことをした」と悔いることはしなくなる。「神のものかどうか」という指標で見るため、悔い改めることもない。人間の罪を放置し発展した結果の姿だ。
日本人捕虜が見た西欧観
「アーロン収容所 西欧ヒューマニズムの限界」という書籍には、ビルマで英国の捕虜となった経験が綴られている。著者の会田雄次氏は、京都帝国大学文学部史学科、大学院を出て、大学講師をしている頃に、ビルマに出兵し、捕虜となった。日本に戻った後、大学教授となり、定年後は京都大学名誉教となった人物で、イタリア・ルネサンス研究の西洋史学者であり、戦後17年経った1962年京都大学教授の時に、いつか世に出したいと思っていたこの本を出版したそうである。人文学の観察眼を持つ研究者による著作である。
シベリア抑留の場合と異なり、英軍は捕虜に身体的暴力はふるわなかった。捕虜を「家畜」のように眺め(管理し)、「合理的」に搾り上げた。食事に供された下等米は、砕米でひどく臭い米であったのだが、ある時期にはやたら砂が多く、3割ぐらい泥と砂の場合もあり、歯をこわし、下痢をし、散々な目に会ったため、英軍に抗議した。すると、「日本軍に支給している米は、当ビルマにおいて、家畜飼料として使用し、なんら害なきものである」と返答があった。抗議したことへの嫌がらせの返答ではなく、英軍の担当者は真面目に不審そうに、そして真剣に答えたという。清掃係の捕虜が女性兵士の部屋を掃除する際にはノックは必要とされず、全裸であっても平気であり、人間ではなく「家畜」同様の視点での扱いであった。相手が日本兵でもインド兵でもビルマ人でも「東洋人に対する彼らの絶対的な優越感は、全く自然なもの」だったという。著者は、そのような文化をキリスト教の教えに見たということを記している。「動物は人間に使われるために、利用されるために、食われるために、神によって創造されたという教えである。人間と動物の間にキリスト教ほど激しい断絶を規定した宗教はないのではないだろうか。」1そのような考えが根底にあるとすれば、東洋人などはよくて「ペット」で、それ以上の扱いは期待できないということになる。
この本には、東洋人とはあまりにも違う英国人の様子が書かれていた。これは、異国にいた兵士たちという尋常ではない環境下でのことである。英国人の皆が同じと見てはいけないが、反日教育を受けた国の人々の中に、反日感情が根付いているように、そうなりやすい文化的な教育による思想があるのは、否定できない。東洋人がキリスト教を受け入れられない原因の一端がここにあるようだ。
ルターがなそうとした宗教改革は、ヒューマニズム(人間中心主義・人文主義。神や宗教の権威よりも人間の理性、尊厳、価値を重んじる思想)とともに広がっていき(カルヴァンは、ヒューマニズムの深い教養を身につけたヒューマニストであった)、プロテスタント社会を形成していった。ヒューマニズムは、隣人愛のように受け取ることもできそうだが、人間愛に重きを置くと、キリストの愛とは別物になっていく。イエスを思ってペテロがとった行動に、「下がれ。サタン。あなたは神のことを思わないで、人のことを思っている。」とイエスが言われたことがあったが、サタンは神から離すためには、巧妙に人間的な愛に偽装することもある。
キリストの愛から離れたキリスト教は、自分たちファーストになり、他から見れば、その傲慢さ、他への冷酷さがつまずきとなる。まして、自分たちファースト(言い換えると自己中心)がキリストの名を使った宗教を理由とするなら、そのつまずきは計り知れない。
神の教え「愛」からの逸脱と罪の放置のサイクルが招く結果
人間の罪は神のサイクルを繰り返している。「『神の言葉(みこころ)』があって、『人間の罪による堕落』が進み、罪が行きつくところまで蔓延し、『追放(体系の崩壊)』を招き、神のことばに立ち返った者たちが置かれた『新しい体制の中で悔い改め神に立ち返る』」というサイクルである。このサイクルが終わる時が来る。「追放(体系の崩壊)」し、悔い改め神に立ち返るという道がなくなる時が来る。その時、キリストが来臨され、最後の審判となるだろう。
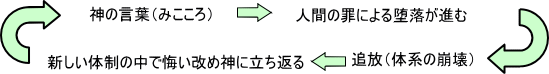
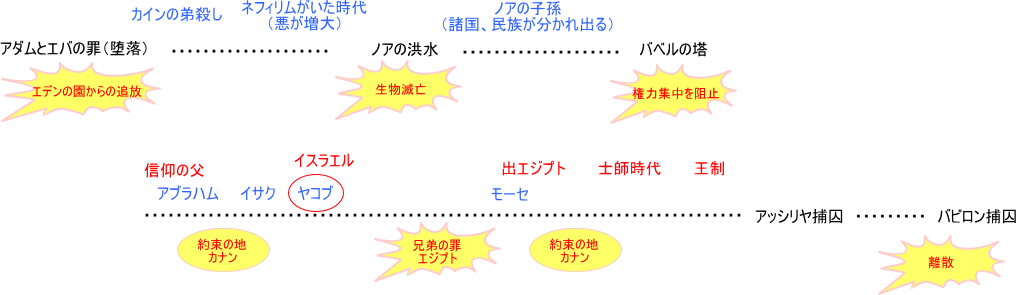
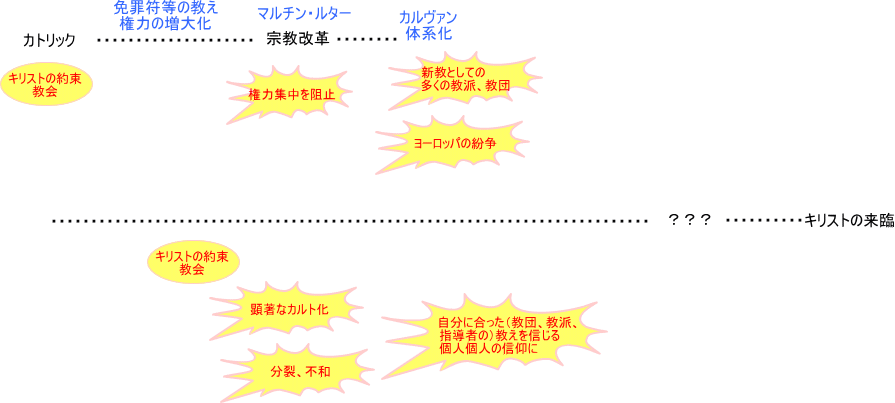
神の民が神よりも王を望んだ時、神は「王の権利」を説明して、王制をとることを許された。初めの王サウルは、見目麗しくこれこそ王だ!と民が認める素質を持った人物であった。神に選ばれ、神に従うことを誓ったサウルだったが、神の言葉を自己流に解釈し、それをサムエルからとがめられた時に、「民は羊と牛の最も良いものを惜しんだのです。あなたの神、主に、いけにえをささげるためです。」(Ⅰサムエル 15:15)とアダムのように他に責任を転嫁し、それも「神、主に、いけにえをささげるため」と神を理由に言い訳をした。形は神に従う体をなしながら、罪の本質を知らず、サムエルが指摘しても、罪を犯していることにも気づかないサウルに対し、神はサウルが懇願しても退け、厳しいまでの措置を取られたのであった。この後のサウルの歩みは、ダビデを妬み、自分を守るのに必死であった。サムエルは、「主が王位からサウルを退け(Ⅰサムエル 15:26)、イスラエル王国を引き裂いて、これをあなたよりすぐれたあなたの友に与えた。(Ⅰサムエル 15:28)」とサウルに告げたが、サウルは、死ぬ時までイスラエルの王として戦った。信仰よりも自分の面目を重視したサウルは神に退けられた。その後、イスラエルは北と南に分裂した。神が王位から退けたサウルがその後も死ぬまでイスラエルの王であったのは、主のことばが間違っていたわけではない。主の中では、罪を知らず、罪のまま歩み、自分の面目を一番とし、主の指摘があっても悔い改めようともしないサウルを「退け」と言われたこの時、王位から退けられたのである。「神の賜物と召命とは変わることがありません。」(ローマ 11:29)とあるが、王位から退けられたサウルが王として命を終えたのは、変わることのない主のみこころがあったからである(変わることがない召命があり、召命による立場の継続と神の内にあるかどうかは別物である)。
ローマ 11:29の前にパウロは「兄弟たち。私はあなたがたに、ぜひこの奥義を知っていていただきたい。それは、あなたがたが自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。その奥義とは、イスラエル人の一部がかたくなになったのは異邦人の完成のなる時までであり、こうして、イスラエルはみな救われる、ということです。」(ローマ 11:25,26)と言っているが、旧約聖書に描かれた神の民イスラエルを通して、神は、罪の重大さとその根深さと罪がもたらす結果は滅びであるということを、私たちに、徹底的に教えられている。「もし不信仰を続けなければ、つぎ合わされる」(ローマ 11:23)「もしも、枝の中のあるものが折られて、野生種のオリーブであるあなたがその枝に混じってつがれ、そしてオリーブの根の豊かな養分をともに受けているのだとしたら、あなたはその枝に対して誇ってはいけません。誇ったとしても、あなたが根をささえているのではなく、根があなたをささえているのです。」(ローマ 11:17,18)「イスラエルはみな救われる」とあるが、神の民であっても、自動的にどんな人でも「みな」ではない。「不信仰を続けなければ」であり、異邦人がキリストを信じて、キリストにつがれたのは、イスラエルがあってのことであるので、型を示すために国を失い放浪の民となったイスラエルを貶めたり、自分たちを誇ってはいけないのである。イスラエルを神の民の型として、罪の根深さや罪の結果の滅び、神の愛が示されていなかったなら、異邦人であるローマ人やそこから伝えられていった私たちの救いはなかったのである。※ ここで述べている「イスラエル」は、現代のイスラエル国家の国民ではない。
分裂しつつ広がって行ったプロテスタント
パウロの異邦人宣教から発したローマ教会が教皇制を通り、その体制の中に悔い改める力がなくなっていった頃、マルチン・ルターによって、方向の道筋が変わり、ヨーロッパから世界に広がり、誰もが聖書を読め、真理について聖書や書物を調べることができるようになった。救いの福音は聖書と共に、キリスト教という宗教によって聖く広がって行ったのではなく、罪と相まって、いろいろな教団や教派が競い合い、奪い合い、争いを起こしながら、広がって行った。「神は、みこころにかなう人には、知恵と知識と喜びを与え、罪人には、神のみこころにかなう者に渡すために、集め、たくわえる仕事を与えられる。」(伝道者 2:26)
神というお方は、組織化という人間的な枠に納められるようなお方ではなく、そのみこころは、基本的な事は示せるかもしれないが、教理として体系化(マニュアル化)できるものではない。初代教会の使徒たちもルターも体系を作ることはしなかった。教理として体系化できるものであれば、キリスト自身(もしくは使徒たち)がそのことを成していっただろうが、主はそういったことには触れられなかった。むしろ、文字に仕える律法を廃棄されていかれた。聖書のみを残された。神は、人が作った宮に住まわれるお方ではない。神を人間の頭に合わせて小さくしてはいけない。
ルター派以外のプロテスタントは、カルヴァンの教えが基準となっている。カルヴァンの教えは、受け取る人間側の解釈次第では、「豊かさは神の恵みだ。」「信者を獲得する伝道の実は祝福だ。」と金銭や人数の多さに目を向けることにつながっていく。教えを律法化し、マニュアルのように理解すると、一匹一匹の羊の特性を見て神の愛をこめてお世話をするよりも、そんな面倒なことはせず、羊が定められた教えの基準にそっているかどうかマニュアル的に管理してしまう。そのようになると、カルト化指導者からのパワハラを受け、自尊心も奪われ、ぼろぼろになっている被害者の相談に、「赦しは、重要な教えだ」という教理に基づき、ろくに話を聞かず、「いつまでも、(傷を)言っているのは罪です! 許しなさい。」と抑え込み、さらなる傷を与えたとしても、自分は神にあって正しいことを言ったにすぎないと、キリストの愛から離れていることに気づくこともない。これは、一つの例えであるが、このようなマニュアル的な牧会は危険である(羊の命を奪いかねない)。
ルターは95か条の命題からもわかるように、改革を訴えたのは、罪と悔い改めの必要に基づいた改革であった。罪は自分も他人も傷つけ、心を麻痺させ、霊的死に至らせる。「悔い改めなさい。天の御国は近づいたから」から始まり、福音を告げ知らせられたイエスの宣教は、神の愛から出ていた。愛というのは、マニュアル化できるものではない。
愛に立っていない教えの氾濫と、誰でも自由に聖書研究ができるような世の中になったこと、統率者がいないことで、異端が生まれやすくなった。愛によらない宣教は、つまずきをももたらすことになる。つまずいた人たちは、福音に耳を傾けることはしなくなってしまうかもしれない。
あたりまえのように教えられている教えは、聖書のイエス・キリストを遣わされた神の教えか、「神は愛である」とある神から出た教えか、吟味することができるよう、誰もが聖書を読め、インターネットが普及し、真理について聖書や書物を調べることができるような世の中となった。どれを選ぶかの自由意思が与えられている。神は、キリスト教徒になるかどうかではなく、「神は愛である」という神が形を取って世に示してくださった「キリスト」なる神を信じているか、何をどう信じ、どう行動したかを、個人個人に問われることだろう。完全ではない私たち人間ではあるが、見出した真理は、誇らずに感謝しつつ受け止め、何度失敗しても、神の愛に立ち返り、「神を愛し、隣人を愛せよ」と言われたキリストの律法を忘れないように、歩んでいこう。
- アーロン収容所 西欧ヒューマニズムの限界 会田雄次著 中公新書 p64 ↩︎



コメント